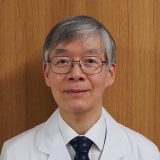指定難病「ALS」の進行抑制を確認、iPS細胞が切り拓く“新たな治療”の可能性 京都大学

京都大学iPS細胞研究所らの研究グループは、「iPS細胞(人工多能性幹細胞)を活用して発見したALS(筋萎縮性側索硬化症)の治療薬の候補を患者に投与する第2段階の臨床試験で、半数以上の患者で進行の抑制が確認された」と発表しました。この内容について中路医師に伺いました。

監修医師:
中路 幸之助(医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター)
研究グループが発表した内容とは?
京都大学iPS細胞研究所らの研究グループが発表した内容について教えてください。
![]() 中路先生
中路先生
これまでに京都大学iPS細胞研究所らの研究グループは、ALS患者のiPS細胞で病態再現と薬剤スクリーニングを実施し、「ボスチニブ」という慢性骨髄性白血病の治療薬に強い抗ALS病態作用があることを見出していました。第1相試験は2019~2021年に実施されており、ALS特有の有害事象が認められなかったことや、投与期間に一部の患者さんでALSの進行の抑制が認められたこと、その目印となる可能性のある指標があったことが明らかになったことで今回の第2相試験が実施されました。今回の臨床試験は、26名のALS患者を対象に実施され、ボスチニブを200mg/日もしくは300mg/日を投与しました。
その結果、ALSの承認薬であるエダラボンの臨床試験のプラセボ群に基づく基準と比べて、運動機能障害の強さを示すALSFRS-Rのスコアの低下が抑制されていることがわかりました。また、ボスチニブを24週間にわたって投与したところ、試験に参加した26人のうち、少なくとも13人の患者についてALSの進行の抑制が認められる結果が得られました。安全性評価では、ALS特有の有害事象はありませんでしたが、下痢や肝機能障害などが認められました。
研究グループは、「今後、iPS創薬による第1相試験及び第2相試験の結果に基づいて、次の計画を検討していきます」とコメントしています。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)とは?
今回の研究テーマになったALSについて教えてください。
![]() 中路先生
中路先生
ALSは指定難病に位置付けられている病気で、手足やのど、舌や呼吸に必要な筋肉の力が徐々に失われます。筋肉そのものではなく、筋肉を動かす神経、運動ニューロンが主に障害を受けます。一般的に、筋肉を動かす指令が伝わらなくなることで筋肉は弱っていきますが、視力や聴力などの体の感覚、内臓機能などは影響が出ないとされています。
2020年度の特定医療費(指定難病)受給者証所持者数によると、1万514人がALSにかかっていることが判明しています。男性患者がやや多く、女性と比べて1.3~1.5倍です。60~70代が最もかかりやすい一方で、稀ですが若い世代でも発症することがあります。はっきりとした原因は解明されておらず、神経の老化との関連や興奮性アミノ酸の代謝異常、酸化ストレス、タンパク質の分解障害、ミトコンドリアの機能異常などの学説があります。ALS全体の約10%は家族内で発症することが分かっており、家族性ALSと呼ばれます。
研究グループが発表した内容への受け止めは?
京都大学iPS細胞研究所らの研究グループによる発表への受け止めを教えてください。
![]() 中路先生
中路先生
本研究の特記すべき点は、実臨床で用いられている既存の薬剤の難病への効果を新技術を用いて証明したことです。ただし、研究の限界として、症例数が20数例と少ないことに加え、対象が発症後2年以内でALSの重症度基準で重症度1または2の軽症の患者さんに限られており、発症から比較的時間が経過した中等症~重症の患者さんへの効果は不明です。また、観察期間が24週と短く、長期効果に関してもわかりません。今後、第3相試験での良い結果の報告を期待します。
まとめ
京都大学iPS細胞研究所らの研究グループは、「iPS細胞を活用して発見したALSの治療薬の候補を患者に投与する第2段階の臨床試験で、半数以上の患者で進行の抑制が確認された」と発表しました。今後も臨床試験が順調に進み、ALS患者へ新たな治療薬が届くことに期待が集まっています。