
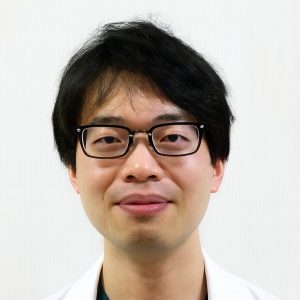
監修医師:
栗原 大智(医師)
目次 -INDEX-
交感性眼炎の概要
交感性眼炎(こうかんせいがんえん)は、一方の眼に重いケガ(眼外傷)や眼の手術を受けた後に、もう片方の健康な眼の内部(ぶどう膜)に炎症が生じる疾患です。発症のきっかけは多くの場合、眼球を貫通する外傷(穿孔性外傷)とされ、硝子体手術などの眼内手術後に起こることもあります。交感性眼炎の発症頻度自体は低いとされ、発生率は眼の手術後で約0.1%、穿孔性外傷後でも0.2~0.5%程度と報告されています。最近では、手術技術の進歩や、外傷後早期からのステロイド治療による加療により、本症の発生はかなり予防できるようになり発症例は減少しています。
交感性眼炎の原因
交感性眼炎が起こるメカニズムは完全には解明されていませんが、自己免疫反応が関与しているとされています。通常、眼球内の組織は血液-眼関門によって守られており免疫の攻撃を受けにくい状態です。ところが、外傷や手術で眼の内部(網膜や脈絡膜など)の組織が体内に露出すると、免疫細胞がそれらを異物と認識し攻撃する抗体やリンパ球が作られてしまいます。その結果、ケガをしていない側の眼の組織まで免疫によって攻撃され、両眼に炎症が起こると考えられています。このように自身の免疫が眼を攻撃してしまうため、交感性眼炎は自己免疫疾患の一種といえます。病名の交感性は、片方の眼の炎症にもう片方の眼が共鳴(交感)して炎症を起こすことに由来しています。
交感性眼炎の前兆や初期症状について
交感性眼炎の典型的な初期症状としては、視力の低下、視界に虫やゴミなどの浮遊物が飛んでいるように見える(飛蚊症)、眼の充血、眩しさを強く感じる(羞明)、そして場合によっては眼の痛みなどがあります。とくに近くのものを見る際にピントが合いづらくなることが初期のサインとなることがあります。これは炎症によって虹彩や毛様体(ピント調節を行う部分)が障害されるためと考えられます。
症状は片眼から始まり、放置すれば数週間から数ヶ月のうちにもう片方の眼にも同様の症状が現れます。この潜伏期間は典型的には2~12週間程度で、報告によれば約80%の患者さんは受傷後3ヶ月以内、90%は1年以内に発症しています。しかし、発症までの期間にはばらつきがあり、外傷から長期間経っていても油断できない病気です。両眼に炎症が及ぶため症状は左右両方に現れますが、初期には原因となった方の眼のほうが重度の炎症を呈する傾向があります。そして、交感性眼炎そのものは感染によるものではないため、発熱や全身の症状は通常伴いません。これらの症状があればまず眼科を受診するようにしましょう。
交感性眼炎の検査・診断
交感性眼炎の診断では眼の受傷・手術歴と両眼の臨床所見が診断の決め手となります。問診で過去の眼外傷や手術の有無を確認し、精密検査によって炎症の程度や広がりを評価します。その上で、ほかの原因(感染症や別のぶどう膜炎)がないかを調べ、総合的に判断して診断を行います。
視力検査
交感性眼炎では視力低下の程度が病状の指標となるため、診断時だけでなく治療経過中も定期的に視力検査を行います。とくに健眼(ケガや手術のない方の眼)の視力低下は発症の重要なサインです。視力がどの程度落ちているかは予後の予測や治療の強さを決める上でも参考になります。
眼底検査
散瞳検査(瞳孔を広げる目薬を使った眼底検査)によって、網膜や視神経、脈絡膜の状態を直接観察します。交感性眼炎では網膜や視神経、脈絡膜に特徴的な所見がみられます。また、眼底検査はぶどう膜炎の重症度や病変の広がりを把握するために欠かせません。治療中の病態の改善を観察する上でも重要です。
光干渉断層計(OCT)
OCT検査では網膜や脈絡膜の断面構造を非侵襲的に撮影します。交感性眼炎では網膜下の液体貯留や脈絡膜の肥厚を高解像度で確認できます。また炎症により網膜の一部に構造の乱れが生じますが、治療に反応してそれらが修復されていく経過もOCTで観察できます。このようにOCTは炎症活動性の指標、治療効果の判定に有用です。
フルオレセイン蛍光眼底造影(FA)
造影剤(フルオレセイン色素)を腕の静脈から注射し、眼底の血管の様子を連続撮影する検査です。FAは網膜・脈絡膜レベルの微細な変化を把握でき、交感性眼炎と類似した疾患との鑑別や、病状経過の記録に役立ちます。
交感性眼炎の治療
交感性眼炎の治療では、早期発見と早期治療が視力予後を左右します。治療の基本はステロイド(副腎皮質ステロイド)による炎症の抑制であり、必要に応じて免疫抑制剤を併用します。場合によっては炎症の元となる受傷眼そのものを外科的に摘出することも検討されます。以下、それぞれの治療と最近の研究動向について詳しく解説します。
ステロイドによる初期治療
交感性眼炎と診断した場合、まずは高用量のステロイドで炎症を抑えます。具体的には全身投与(内服または点滴注射)によるステロイド治療が基本となります。投与例として、プレドニゾロン換算で1日あたり1mg/kg程度の容量を用い、症状が落ち着くまで投与します。
重症例ではステロイドパルス療法(ステロイドの大量点滴を短期間行う治療)を行うこともあります。併せてステロイド点眼も頻回に行い、眼の表面からの炎症コントロールを図ります。炎症が強い場合には後部テノン嚢下注射や硝子体内注射といった局所へのステロイド投与(トリアムシノロンアセトニドなど)を追加し、眼内の炎症を直接的に抑えることもあります。ステロイドによる治療開始後、状態が改善したら徐々にステロイドの量を減らしていきます。一般に2~3ヶ月かけてゆっくり減量し、再燃(ぶり返し)がないか経過観察します。
免疫抑制療法
ステロイドだけでは長期間の維持が難しい場合や、副作用の懸念からステロイドを早めに減量したい場合に、免疫抑制剤を併用します。交感性眼炎では初期からステロイドと免疫抑制剤を併用することもあります。免疫抑制剤は効果発現までに数週間以上を要するものが多いため、早めに併用治療を開始します。
治療効果が安定すれば、ステロイドを中止して免疫抑制剤のみの維持療法に移行することもあります。ただし、免疫抑制剤にも感染症のリスクや肝機能障害・腎機能障害などの副作用があるため、定期的な血液検査で安全性を確認しながら慎重に投与を続けます。
外科的治療(眼球摘出)
交感性眼炎によって、すでに受傷眼の視力が回復不能と考えられる場合があります。そのような場合、炎症の抑制と健眼の発症予防のために受傷眼の眼球摘出(摘出手術)を検討することがあります。
その他治療
近年では、生物学的製剤と呼ばれる分子標的治療が注目されています。具体的には、炎症性サイトカインであるTNF-αを阻害するインフリキシマブ(レミケード)やアダリムマブ(ヒュミラ)がほかの治療に反応しない交感性眼炎で使用され、視力の改善や炎症寛解に効果を示した報告があります。また、インターロイキン6(IL-6)という別の炎症物質を抑えるトシリズマブ(アクテムラ)が、特に黄斑浮腫(網膜中心部のむくみ)が残る症例に対して有効だったとの報告もあります。さらに、眼局所への新たな治療として徐放性ステロイドインプラント(デキサメタゾンやフルオシノロンの眼内留置)が海外では使用され始めています。これらの生物学的製剤やステロイドのインプラントはまだ限られた難治例での使用にとどまりますが、今後より多くの患者さんに適用可能な治療となることが期待されています。
交感性眼炎になりやすい人・予防の方法
交感性眼炎の予防で重要なのは、まず発症のきっかけを作らないことです。つまり、眼のけがを防ぐことが予防方法となります。金属や木材を切削する作業では防護メガネを着用する、強いボールや肘が飛んでくる可能性のあるスポーツではスポーツ用ゴーグルを使用する、化学薬品を扱う際は保護めがねやフェイスシールドを用いる、といった基本的な安全対策が大切です。交通事故による眼外傷も少なくないため、シートベルト着用など、基本的な安全対策が重要です。
次に、眼内手術後の注意についてです。眼科手術を受けた後は、医師の指示通り定期検診を受け、術後経過観察を必ず受診するようにしましょう。また、手術を受けた眼だけでなく反対側の眼にも異常がないか自分で自覚症状に気を配ります。もし視力低下や飛蚊症の増加、かすみ、眩しさなど少しでも「あれ?」と感じる症状があれば、すぐに担当の眼科医に連絡してください。交感性眼炎は早期に発見して治療を始めれば失明を防げる病気です。そのため、手術後だけでなく過去に眼の大きなケガをした経験がある方も、反対眼の様子に注意を払いましょう。特に受傷後1年以内はリスクが高い時期ですので、定期的に眼科でチェックを受けることをおすすめします。
参考文献
















