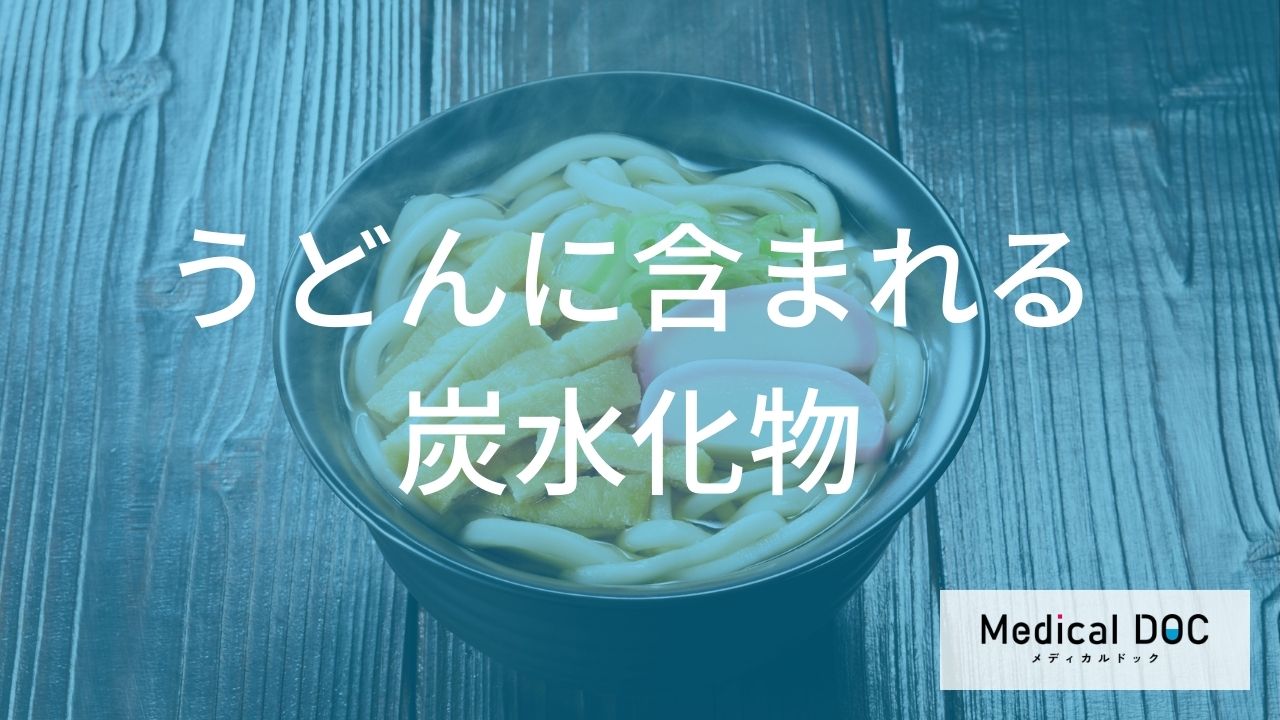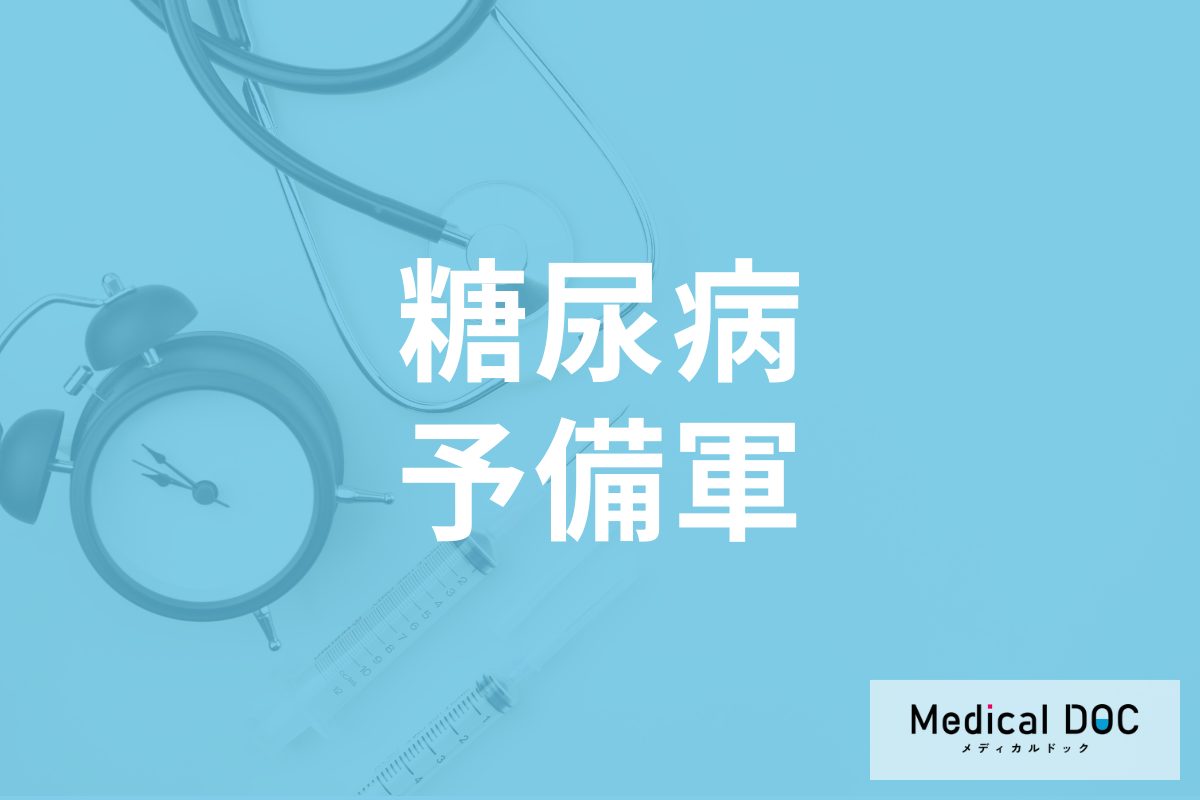「高血糖」を疑う症状・考えられる病気はご存知ですか?医師が監修!

血糖値が通常よりも高くなってしまう高血糖は、糖尿病・心筋梗塞・肝硬変など重大な病気の危険をはらんでいます。
適切な血糖値を保つことは健康においてとても重要です。糖尿病などで高血糖を繰り返すと合併症を引き起こす可能性も高いため、高血糖の症状を見逃さないことが大切です。
この記事では、高血糖の症状だけでなく、原因・危険な数値・血糖値の上昇を緩やかにする方法も詳しくご紹介します。健康を保つため、早期発見のためにもぜひ参考にしてください。

監修医師:
竹内 想(名古屋大学医学部附属病院)
目次 -INDEX-
高血糖の症状

高血糖の症状で多くみられるものには下記が挙げられます。
- 口渇(のどの渇き)
- 多飲
- 多尿
- 急激な体重減少
- 疲れやすい
- 足などの怪我が治りにくい
上記の症状が気になる場合は、高血糖が疑われます。これらの症状の1つ1つは小さなことのように感じやすく、放置してしまう方も少なくありません。しかし、糖尿病・心筋梗塞・肝硬変などの病気につながっている可能性も高いです。なかには糖尿病を放置したことによる深刻な合併症を併発したり、重度になると意識障害を引き起したりする可能性もあるため注意が必要です。
思い当たる症状がある方は病院を受診するとよいでしょう。ただし、なかには自覚症状のない方も少なくないため、定期的な健康診断などで血糖値を調べておくことも大切です。
高血糖の原因

食事によって摂取した炭水化物などの糖質は、消化吸収されてブドウ糖として体内に吸収されます。このブドウ糖が血液内に過剰に残ってしまう状態が高血糖です。
大きな原因として下記が考えられます。
- 食べ過ぎ(糖質過多)
- 運動不足
- ストレス過多
- インスリンの分泌不足・作用不足
無意識のうちに高血糖を引き起こしているなら、多くの場合は食べ過ぎや運動不足が原因です。食後には血糖値が上昇しますが、食べ過ぎは急激な血糖値の上昇につながり高血糖を引き起こしやすくなります。食べてすぐに寝てしまう・空腹状態が続いてからの食事・1日2食しか食べない…などの習慣がある方は注意しましょう。運動不足の傾向がある方も、エネルギーであるブドウ糖の消費が減るため高血糖になりやすいです。
また、ストレスがかかると分泌されるホルモンには血糖値を上昇させる働きがあるため、過剰なストレスも高血糖を引き起こす場合があるでしょう。これらの原因による高血糖はどなたにでも起こり得るもので、一般的に糖尿病と呼ばれている2型糖尿病の方の大半もこれに当てはまります。しかし、なかにはブドウ糖を細胞に届ける働きのインスリンと呼ばれるホルモンが不足している・うまく作用していないなどのケースがあるため注意が必要です。
これは主に1型糖尿病の方に当てはまります。放置すると高血糖だけでなく低血糖の危険もあり、急激な血糖値の上昇による糖尿病ケトアシドーシス(糖尿病昏睡)も引き起こしかねません。1型糖尿病が原因の高血糖は自然に治癒する可能性はなく、放っておくと命にかかわるため必ず病院を受診しましょう。
血糖値はいくつから危険?

血糖値の基準の値を超えている場合、高血糖と判断されます。健康であると判断できる血糖値は、一般的に70〜140mg/dLを基準とします。食前・食後を含み、適切な食事や適切なインスリンの働きによって70〜140mg/dLの範囲内に収まっていることが大切なポイントです。これを超えてしまい危険とされる数値は、いくつかの段階に分けられます。
- 糖尿病とされる基準
- 血糖値300以上
- 血糖値500以上
それぞれ詳しくご紹介します。
糖尿病の基準となる数値
糖尿病かどうかの診断は、血糖値とHbA1c(ヘモグロビンA1c)の値を測定し行います。HbA1c(ヘモグロビンA1c)は1~2ヶ月間の血糖値の平均値を算出した際の指標になる値で、HbA1c(ヘモグロビンA1c)・血糖値ともに血液検査で測定することが可能です。血糖値は空腹時に測定し、下記のように区切って診断します。
- 100~109mg/dL:正常高値
- 110~125mg/dL:境界型
- 126mg/dL以上:高確率で糖尿病が疑われる
正常高値は正常値よりやや高く、今後糖尿病になる可能性があるため注意をしておきたい段階です。境界型はいわゆる糖尿病予備軍として、悪化しないよう生活主観に気を配る必要があります。126mg/dLを超えていると、糖尿病である確率がかなり高いといえるでしょう。
また、食後の血糖値が200mg/dLを超えている場合も高確率で糖尿病が疑われます。HbA1c(ヘモグロビンA1c)の場合は4.6~6.2%が正常値のため、6.5%以上だと糖尿病が強く疑われる数値です。
血糖値が300を超えるとどうなる?
血糖値が300を超えると明らかな高血糖状態となり、自覚症状が現れる方も少なくありません。口渇と呼ばれる強いのどの渇きが代表的です。他に、多飲・多尿・疲労感なども自覚しやすい症状です。
もしもこれほどの高血糖状態が長期にわたって繰り返されたり続いたりすると、合併症に伴う症状も現れる場合があります。神経障害による足のしびれ・網膜症に伴う目のかすみ・腎症に伴うむくみ・感染症による発熱など、放っておくと危険な合併症も少なくありません。気になる症状に気づいた際は、早めに病院を受診してください。
血糖値が500を超えるとどうなる?
血糖値が500を超える著しい高血糖状態になると、意識障害に陥る可能性があります。意識障害に陥る前兆として、血糖値が300を超えると顕著になる口渇・多飲・多尿がみられることが多いです。
その結果として脱水症状を起こす確率も高く、電解質のバランスが崩れ、腹痛・下痢・全身の強い倦怠感などが現れるでしょう。さらに血糖値が上がると意識障害・ショック・痙攣などが起こり、昏睡状態に至ります。治療が遅れると命を落とす危険性もあるため、このような症状がみられたら一刻も早く治療を受けてください。
血糖値の上昇を緩やかにする方法

高血糖はさまざまな症状が出るだけではありません。合併症を患ったり、けがや病気が治りにくかったりと長期的にみても危険です。放置していると糖尿病ケトアシドーシスなど命にかかわる重篤な状態になりかねません。
高血糖だとわかった際には、血糖値の急激な上昇を防ぐ努力が必要といえるでしょう。血糖値の上昇を緩やかにする方法は主に生活習慣の改善・食事に注意すること・血糖値の急上昇を抑える効果が期待される飲み物を取り入れることなどが挙げられます。それぞれ詳しく解説いたします。
生活習慣を改善する
一般的に「糖尿病」というと2型糖尿病を指すことが多く、2型糖尿病は生活習慣病の1つとしてもよく知られています。このことからもわかるように、高血糖の原因として大きいのが生活習慣の乱れです。
早食いや食べてすぐ寝る習慣のある方、運動不足の方などは特に高血糖になりやすいため注意しましょう。有酸素運動で代謝をあげたり、トレーニングで筋力をつけたりするのも有効です。適度な運動は高血糖対策にはもちろん、健康な体づくりに欠かせません。ストレスも高血糖の原因になるため、夜更かしは避け適切な睡眠をとるなど、健康的な生活を心がけましょう。
食事に注意する
食事は血糖値にダイレクトに影響するため、下記の習慣がある方は特に注意してください。
- 食べ過ぎ
- 早食い
- 食後すぐに寝てしまう
- 間食が多い
- 単品メニュー(炭水化物)が中心の食事になりがち
- 野菜の摂取量が少ない
- 甘いもの・お酒などを好んでいる
- 食事を抜く
食べ過ぎ・早食いは血糖値の急激な上昇を引き起こします。高血糖を防ぐには、ゆっくりよく噛んで適量の食事をとることが重要です。また、食事の糖質(炭水化物)量にも気をつけましょう。お米・小麦・砂糖などの糖質は、消化吸収されブドウ糖として体内のエネルギーになります。しかし、過剰になってしまうと余剰分が血液内に残ってしまうため高血糖になります。栄養バランスが整うよう、主食だけでなく主菜・副菜も意識し野菜やたんぱく質もしっかり摂取することが大切です。
また、朝食を抜くなど、食事を抜く習慣も高血糖の大きな原因です。食事を抜くとエネルギーが不足がちになり、次の食事の際に体が急いでエネルギーを補給しようとします。すると血糖値が急上昇してしまい高血糖につながるため、注意が必要です。できるだけバランスのよい食事を3食しっかりとりましょう。
血糖値の上昇を緩やかにする飲み物
食事だけでなく飲み物にも気を遣いましょう。飲み物に含まれるポリフェノールの量やGI値などの成分を味方につければ、血糖値の急激な上昇を防ぐことが可能です。下記の飲み物は血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できる代表例です。
- 緑茶
- 紅茶
- 黒豆茶
上記のお茶はポピュラーなので、日常的に飲む方も少なくないでしょう。カテキンやポリフェノールには血糖値の上昇を緩やかにする・エネルギー代謝をアップさせるといった効果があります。そのため、高血糖の予防効果が期待できるでしょう。また、桑の葉茶・グアバ茶・ヤーコン茶なども同様の効果が期待できるといわれています。牛乳・乳製品など低GI値の飲み物も食後の血糖値の上昇を緩やかにしてくれるので、食事と一緒に摂取することをおすすめします。
GIとは、食品が糖質をどの程度吸収するかを表す指数です。カロリーとは関係なく、低GI値であればあるほど血糖値が上がりにくいです。また、コーヒーに含まれるクロロゲン酸類のポリフェノールにも血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できるといわれています。カフェインは一時的に血糖値を上げるともいわれていますが、日常的にコーヒーを飲む習慣が糖尿病の発症リスクを下げるという研究結果もみられます。
食前・食後に飲むのではなく、食事と一緒にコーヒーを飲む方が食後の血糖値の上昇を緩やかにするのでおすすめです。砂糖を入れると血糖値が上がってしまうため、ブラックか、何か入れるとしてもミルクのみにしましょう。ただし、そもそもカフェインの摂りすぎはよくないため、飲みすぎないよう注意してください。
すぐに病院に行った方が良い「高血糖」症状は?
- 激しい口渇や多尿がある、全身倦怠感で動くことが難しい場合
- 意識障害やけいれん、振戦などがある場合
これらの場合には、すぐに病院受診しましょう。
行くならどの診療科が良い?
主な受診科目は、内科、糖尿病内科、内分泌内科です。
問診、診察、血液検査や尿検査などが実施される可能性があります。
病院を受診する際の注意点は?
持病があって内服している薬がある際には、医師へ申告しましょう。
すぐに病院を受診できない場合には、市販の消炎鎮痛薬の内服や湿布の貼付でも痛みが緩和されます。
治療をする場合の費用や注意事項は?
保険医療機関の診療であれば、保険診療の範囲内での負担となります。
まとめ

本来、血糖値はインスリンなどのホルモンの働きによって正常な範囲に保たれています。
しかし、ちょっとした生活習慣の積み重ねやストレスなどによって高血糖が続くと、思わぬ大きな病気につながってしまいます。
放置すると重篤な合併症のリスクもあり、最悪の場合は死に至るケースもあるため注意が必要です。食事や運動など生活習慣に気を配り、高血糖のリスクを下げましょう。
なかには体内のインスリンが不足している・作用が弱いなどの問題が隠れているケースもあります。
定期的に健康診断を受け、気になる症状がある方は医療機関を受診することが大切です。高血糖の悪化を防ぎ、早期に治療を行うよう心掛けましょう。
高血糖症状の病気
関連する病気
- 急性膵炎
- 慢性膵炎
- 膵臓癌
- 糖尿病
- 妊娠糖尿病
- 先端巨大症
- クッシング症候群
- アルドステロン症
- 褐色細胞腫
- 甲状腺機能亢進症
- グルカゴノーマ
- ソマトスタチノーマ
- 慢性肝炎
- 肝硬変
- アルコール性肝障害
- 薬剤性(ステロイド、インターフェロン、サイアザイド系利尿薬、β遮断薬、経口避妊薬など)
- 先天性風疹
- サイトメガロウイルス感染症
- Epstein-Barrウイルス感染症
- Coxackie Bウイルス感染症
- Mumpsウイルス感染症
- ダウン症候群
- Prader-Willi症候群
- Turner症候群
- Klinefelter症候群
- Wolfram症候群
- Werner症候群
- <セルロプラスミン低下症
- 脂肪萎縮性糖尿病
- 筋強直性ジストロフィー
- Friedreich失調症
- Laurence-Moon-Biedi症候群
参考文献