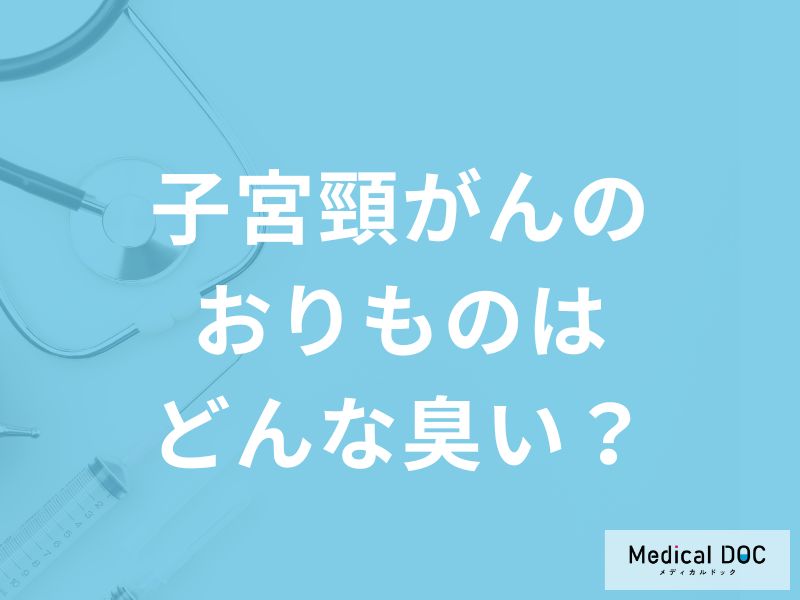「くも膜下出血の生存率」はご存知ですか?予後が悪化する要因も医師が解説!

くも膜下出血の生存率とは?Medical DOC監修医がくも膜下出血の予後が悪化する要因・症状・初期症状・原因やなりやすい人の特徴などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師:
佐々木 弘光(医師)
目次 -INDEX-
「くも膜下出血」とは?
くも膜下出血とは、脳内の「くも膜下腔」と呼ばれるスペースに出血する病気です。原因はいくつかありますが、そのほとんどが脳動脈瘤とよばれる脳の中の血管にできた「こぶ」によるものです。この脳動脈瘤がある日突然破裂して発症します。代表的な症状は突然発症するとても強い頭痛や嘔吐、重症な場合は意識障害などの症状を呈します。現代でも発症すると致死的で、重症な経過を辿ることの多い危険な疾患です。
ここではくも膜下出血の予後や症状等について解説していきます。
くも膜下出血の生存率
退院時の状態と長期生存率
くも膜下出血の年間の発症率は人口10万人あたり10-30人程度と言われ、決して高くはない頻度です。しかし発症してしまうと、初期の段階でも約30%程度の人が死亡するとされる致死率・後遺症率ともに高い重篤な疾患です。
近年の統計でも、くも膜下出血で病院に搬送されて死亡した、または重度の寝たきり状態となった(modified Rankin Scale 5-6レベルといいます)人の割合は32.1%、日常生活に何らかの介護が必要となった(modified Rankin Scale 3-4レベルといいます)人の割合は16.8%とされています。
脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血は、何も処置をせずに経過を見た場合、最初の1か月で20-30%が再び破裂して重症化するとされます。そして特に最初の破裂から24時間以内での再破裂が多く、再破裂してしまうと致死率が70-80%程度と上昇してしまいます。そのためガイドラインでも、最初の破裂から遅くとも72時間以内での緊急処置(開頭術やカテーテル治療による止血処置)が推奨されています。長期的な生存率については、年齢や重症度、合併症など、後述する予後を悪化させる因子の影響によって大きく左右されるため、単一的なデータはありません。
参考として、50歳のくも膜下出血の平均余命は20-25年程度であったとの秋田県からの研究報告や、60-70歳代の重症くも膜下出血の平均生存期間は5年前後であったという海外からの報告もあり、60歳以上になってくると一般的な余命の半分以下になってしまう可能性もあります。一方で50歳以下の若年で、後遺症の少ないくも膜下出血であった場合は、5年生存率も8-9割程度と通常に近い長期余命も期待できます。従って、やはり発症時の重症度や入院期間中の合併症の発生などがその後の生存率にも大きく影響してくるといえます。
くも膜下出血の予後が悪化する要因
発症時の重症度
くも膜下出血の予後に大きく影響する因子として特に重要なのが、発症時の重症度です。脳卒中の統計報告によると、搬送時点で中等度以上の昏睡状態(Japan Coma Scale Ⅱ以上といいます。)であるくも膜下出血の患者さんは約50.9%で、うち31%が最も重度の意識障害であったとされています。
動脈瘤の破裂による出血量が多い場合や、場所によっては脳内に出血して直接的に脳細胞が破壊されるような大きな血腫を伴う場合もあり、より重度の意識障害や後遺症を残します。さらに最重症例では、搬送されてももうすでに手遅れで手術が不可能な状態であったり、原因不明の心肺停止で搬送されて後からくも膜下出血が判明したりする場合もあります。そしてこれらのくも膜下出血の重症度を表す指標はいくつかあるのですが、そのグレード(段階)が高いと重症であり、より致命的になって救命確率は下がりますし、当然、その後の生存率・後遺症率等の長期予後も悪化するとされています。
年齢
くも膜下出血全体の自宅退院できた割合は52.4%とする報告もありますが、うち65歳から74歳までの前期高齢者で44.2%、75歳以上の後期高齢者では28.6%と、より高齢になるほど自宅退院できる割合が下がり、予後が悪化していることがわかります。
脳血管攣縮
くも膜下出血を発症し、再破裂防止のための緊急手術を乗り越えた後、数日経過して起きる合併症があります。それは脳血管攣縮という現象で、発症4~14日目程度までの期間に生じる可能性があります。具体的にはくも膜下出血による血液が、脳の血管を刺激して攣縮させる(血管が痙攣して細くなる)ことで、脳の血管が詰まり二次的に脳梗塞を起こしてしまう現象です。そして脳梗塞を生じると手足の麻痺や嚥下障害、呂律困難、言語障害など重篤な後遺症を生じ、自宅退院を困難にさせます。この現象は特に出血の量が多い場合により起きやすく、重症化しやすいとされていますが、仮にそれまで症状がなかった患者さんでも突然生じて、一気に状態が悪化してしまう危険性もあるため、決して油断はできない合併症です。脳卒中の統計でも脳血管攣縮を合併した患者さんはそうでない患者さんと比べて何らかの後遺症を残す割合が8-10%程度増加しているとされます。
水頭症
くも膜下出血の急性期治療を乗り越え、退院が見えてきた時期に生じる可能性のある合併症がもう一つあります。それは発症から1か月程度経過してから生じてくる、水頭症という病気です。これは脳内に広がった出血が、脳の中にある脳脊髄液という液体の流れを悪くして、脳に脳脊髄液がたまって生じる合併症です。ふらつきや歩行障害、物忘れや自立した生活が困難になる認知機能障害、トイレに間に合わなくなる尿失禁、といった症状が代表的です。より重症で出血の量が多いくも膜下出血や60歳以上の高齢者、といったことが発症リスクと言われています。水頭症になってしまうと薬で治すことはできません。脳にたまった髄液をお腹の中などに代わりに流すため、シャント術と呼ばれる体の中に機械を埋め込む手術が必要となります。従って、この水頭症の発生も自宅退院を困難にする要因の一つです。
くも膜下出血の代表的な症状
突然の頭痛・嘔吐、失神など
出血によって脳の中の圧力が高まり、強烈な頭痛を中心として、嘔吐や失神・意識障害などの様々な症状を呈します。特に脳動脈瘤は突然破裂するため、首の後ろを中心に突如として激烈な痛みが走り、それが持続します。例えるなら、よく「突然、後ろからバットで誰かに殴られたような」とか、「突然、雷が落ちてきたような(雷鳴様頭痛)」とか、「今まで経験したことのないような」といった表現がされるくらいの唐突で急激な頭痛を生じます。また発症時間がある程度明確なことも特徴的です。その他、急激な頭痛によって嘔吐などの随伴症状を生じたり、さらに重症の場合は意識を失ったり、その場で心肺停止に陥ったりする可能性もあります。
くも膜下出血の前兆となる初期症状
一過性の頭痛、瞼が下がる、視力低下、複視
時々、動脈瘤が破裂しかかっている状態、またはほんの少しだけ出血した状態、の場合にみられる前兆症状(切迫破裂や警告頭痛といいます)もいくつかあります。具体的には、本格的な破裂が起きる数日前からの突然の軽~中等度の首後ろの頭痛や肩凝りといった症状で、吐き気やめまいを伴う場合もあります。また破裂の直前に動脈瘤が急激に大きくなる場合があり、動脈瘤の位置によっては急増大したことで周辺にある神経を押さえつけて、急に片方の瞼が下がってきたり、視力が低下したり、物が二重に見えて目の動きがおかしくなったり、といった症状を認める場合があります。これらの症状は動脈瘤が切迫破裂の状態にあるときに見られ、20%程度にみられるとされます。そして前兆症状が見られた場合は数日~数週以内に動脈瘤の大きな破裂が生じてしまう危険性があるため、躊躇せず早期に脳神経外科を受診するようにしましょう。
くも膜下出血の主な原因
脳動脈瘤
くも膜下出血の原因の約80%が脳動脈瘤の破裂とされます。しかし脳動脈瘤は大きなものを除き基本的には無症状のため、気づかれずに突然破裂する点が非常に厄介です。また脳動脈瘤ができる原因ははっきりわかっていませんが、女性や家族歴(血縁者に脳動脈瘤と言われている人や、くも膜下出血を起こした人がいる)のある人がリスクと言われています。
脳動静脈奇形
脳動脈瘤以外にも、脳動静脈奇形と呼ばれる血管が異常に発達してつながっているような病気によるものが約6%程度とされます。この疾患も突然破裂して出血することもありますが、頭痛や痙攣、運動麻痺といった他の症状から事前に発見される場合もあります。
脳動脈解離
さらに頻度は低くなりますが、脳の血管が高血圧などによって裂けて出血し、くも膜下出血の原因となる場合もあります。特に椎骨動脈解離といって、首の骨である頸椎の横を通る椎骨動脈という血管が裂けるケースが多く、これは40-50代の中高年で、高血圧などが誘因となり発症することが知られています。また頸部を強く振るなど、首への激しい動作も解離の原因となる場合があります。
くも膜下出血になりやすい人の特徴
生活習慣による影響
くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤が見つかった場合、破裂しやすくなるリスクについてはいくつか言われています。報告によって異なる結果もありますが、日本のガイドラインでは喫煙、高血圧、過度の飲酒(1週間に150g以上の飲酒)がリスクと言われています。従って、普段から高塩分な食事を好んだり、喫煙や過剰飲酒をしたりする人は生活習慣を見直すように心がけましょう。肥満については、くも膜下出血の発症と逆相関するとのデータもありますが、BMIが30以上の肥満では出血リスクが高いとする報告もあります。また男性の場合はコレステロール値の上昇がくも膜下出血のリスクを増大させるという報告もありますので、脂っこい食べ物は避けるなどの意識が必要です。
性差や人種、家族歴による影響
そもそも日本人という人種はくも膜下出血のリスクが高いと言われています。また脳動脈瘤が1か所ではなく多発している場合も出血リスクが高くなります。性差で言うと、男性よりも女性に多い傾向があります。
その他に、一親等以内に脳動脈瘤と言われた血縁者がいる場合は、その4%に脳動脈瘤を認めるという家族性も報告されているため、近親者に脳動脈瘤やくも膜下出血の患者さんがおられる場合は、脳ドックなどでの精査も検討してよいでしょう。
くも膜下出血の予防法
脳ドックの受診
そもそも脳動脈瘤の多くは無症状であり、気づかずに破裂して重症な状態になるため、事前に見つけておくことが最大の予防法といえます。そして発見には脳の血管が確認できる頭部MRI・Aや造影CT等が必要となるため、脳ドックを受診したらたまたま発見された、というケースも多くあります。もし脳動脈瘤を認めた場合は専門である脳神経外科を受診し、破裂を予防するための治療を行うべきかを判断されます。動脈瘤が小さい場合は定期的な画像検査で経過観察をすることもありますが、大きい場合は、残念ながら薬では治すことはできませんので、開頭による動脈瘤のクリッピング術やカテーテルによる脳動脈瘤コイル塞栓術といった外科治療が必要になります。
「くも膜下出血の生存率」についてよくある質問
ここまでくも膜下出血の生存率などを紹介しました。ここでは「くも膜下出血の生存率」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。
くも膜下出血を発症すると即死する確率は高いのでしょうか?
![]() 佐々木 弘光医師
佐々木 弘光医師
くも膜下出血で病院に搬送されて死亡した、または重度の寝たきり状態となった人の割合は32.1%、日常生活に何らかの介護が必要となった人の割合は16.8%とされています。また脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血は24時間以内に再破裂する危険性が高く、仮に再破裂すると致死率が70-80%と一気に跳ね上がってしまいます。従って、最初の破裂から遅くとも72時間以内での緊急手術が必要となる緊急疾患です。
くも膜下出血はどれくらいの期間で完治しますか?
![]() 佐々木 弘光医師
佐々木 弘光医師
くも膜下出血の緊急手術が終わったあとも発症から4-14日目までは脳血管攣縮期といって脳血管が細くなり脳梗塞を生じる危険性があるため、入院して厳重に経過観察します。また発症から1か月程度経過した段階で水頭症と呼ばれる合併症を生じてくる可能性もあります。これらをふまえると、くも膜下出血の退院までには最低でも1ヶ月程度の入院が必要となります。さらに後遺症によって自宅退院が難しく、リハビリの継続が必要な場合は数か月~半年以上の入院期間になることもあります。
編集部まとめ
ここまでくも膜下出血の生存率などについてまとめてきました。くも膜下出血は、ある日突然、強烈な形で襲ってきます。そして発症すると、約3割の人が寝たきりや死亡などの状態に陥り、さらに合併症も含めて1か月以上の長期入院を余儀なくされるような非常に重篤な疾患です。一方で原因の多くを占める脳動脈瘤は、基本的には無症状で気づかれないということも非常に厄介です。そのため一度、脳ドックなどの検査を受けて、自分の脳の健康状態とともに、脳動脈瘤などの血管の異常がないか、確認しておくことが大切かもしれません。
「くも膜下出血」と関連する病気
「くも膜下出血」と関連する病気は3個ほどあります。
各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。
脳神経科の病気
- 脳動脈瘤
- 脳動脈解離
- 脳動静脈奇形
様々なデータはありますがくも膜下出血は生命予後が悪い疾患の一つです。精査や人種、家族歴は自分ではどうしようもないリスク要因となりますが。生活習慣は改善させることが可能です。発症予防を目的に生活習慣を見直すことは重要です。
「くも膜下出血」と関連する症状
「くも膜下出血」と関連している、似ている症状は7個ほどあります。
各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。
動脈瘤が破裂しかかっている状態、またはほんの少しだけ出血した状態、の場合にみられる前兆症状としてこれらの症状が現れることがあります。疑わしい場合にはすぐに病院を受診して検査をするようにしましょう。