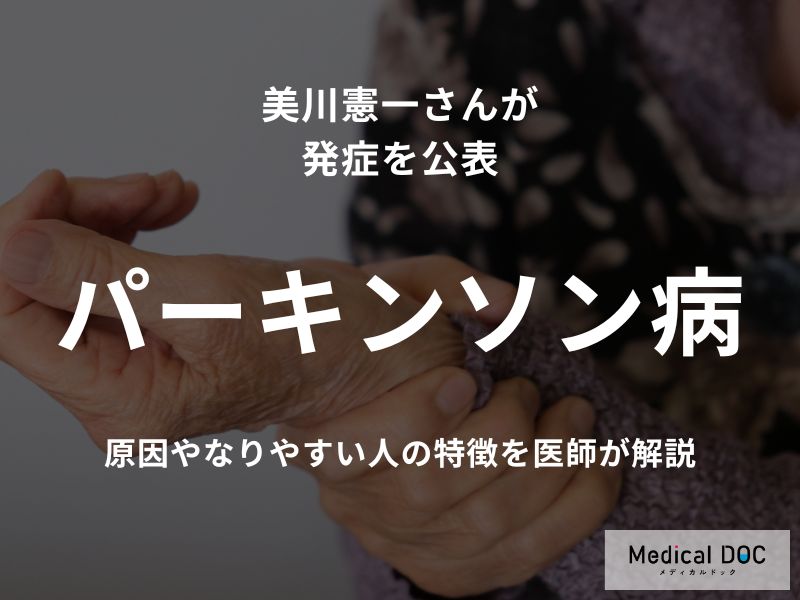超加工食品は「パーキンソン病」死亡リスクを高める 超加工食品の“コワい健康被害”とは

フランスの国際がん研究機関(IARC)らの研究グループは、食品の加工度と死亡リスクの関連性に関する調査結果を発表しました。この結果は、医学雑誌「The Lancet Regional Health-Europe」に掲載されています。この内容について田頭医師に伺いました。

監修医師:
田頭 秀悟(たがしゅうオンラインクリニック)
研究グループが発表した内容とは?
フランスの国際がん研究機関らの研究グループが発表した内容を教えてください。
![]() 田頭先生
田頭先生
フランスの国際がん研究機関らによる研究は、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、イギリスの10カ国、52万1330人を対象にした多施設前向きコホート研究をもと実施されました。食品の加工度と全死因および特定の死因ごとの死亡率との関連を調査した結果となります。ただし、ギリシャのデータは分析から除外されたため、最終的な分析対象は9カ国、42万8728人となっています。
平均15.9年間の追跡調査の結果、超加工食品の摂取量が多いほど、全死因死亡率に加え、循環器疾患、脳血管疾患、虚血性心疾患、消化器疾患、パーキンソン病の死亡率が有意に上昇することが明らかになりました。その一方、超加工食品を未加工または最小限の加工食品に10%置き換えることで、全死因死亡率、循環器疾患、脳血管疾患、消化器疾患、パーキンソン病のリスクの低下が示されました。なお、がんやアルツハイマー病との有意な関連は認められませんでした。
だたし、この研究にはいくつかの懸念点があります。まず、食事データは各国で異なる調査方法を用いて収集されており、摂取量の正確性にばらつきがある可能性があります。また、データは1992~2000年に収集されており、現代の食品加工技術や食習慣の変化を反映していません。これらの点を考慮し、より最新のデータを用いた追加研究が求められます。
研究テーマに関連する疾患とは?
今回の研究テーマで取り上げられたパーキンソン病について教えてください。
![]() 田頭先生
田頭先生
パーキンソン病は、振戦や動作の遅れ、筋肉のこわばり、転びやすさなどが特徴の神経変性疾患です。主に50歳以上で発症し、中脳の黒質にあるドパミン神経細胞の減少が原因とされています。また、便秘やうつ、立ちくらみなどの非運動症状もみられるため、適度な運動や生活習慣の見直しも重要です。特に転倒を防ぐため、住環境の整備や歩行訓練が推奨されます。
パーキンソン病の基本的な治療は薬物療法で、ドパミンを補うL-ドパがよく使われますが、長期間の使用で効果の変動や副作用が生じることもあります。また、手術療法やデバイス補助療法も選択肢の1つです。
症状が気になる人は早めに専門医を受診し、適切な治療と生活の工夫を進めていきましょう。
超加工食品に関する研究内容への受け止めは?
フランスの国際がん研究機関らの研究グループが発表した内容への受け止めを教えてください。
![]() 田頭先生
田頭先生
9カ国にまたがる大規模な多施設コホート研究で、食事調査の正確性における限界や基準の古さ、各国での非統一性などの注意点はありながらも、一定の説得力のある結果が示されていると思います。
超加工食品と健康の関係は未解明な部分も多く、一口に超加工食品と言っても様々なものがあり、一概に語りにくいところがあります。ただ、そんな中でも超加工食品の全体的特徴としては「味覚を強く刺激する」「栄養が削ぎ落とされやすい」「人体にとって異物の側面がある」という3つが挙げられると思います。特に「味覚を強く刺激する」というのは、言い換えれば「消費者が美味しいと感じるように作られている」ということです。美味しいという感覚が強まれば、脳内でドーパミン分泌が刺激されます。中毒性の高い超加工食品もあることを加味すれば、この刺激が過剰に繰り返されることがパーキンソン病のリスク上昇に一役買っているのかもしれません。また、「栄養が削ぎ落とされやすい」「人体にとって異物の側面がある」というのは、体内での炎症を引き起こし、それが修復されにくくする環境作りに寄与している可能性もあります。
がんやアルツハイマー病が増えなかったという結果は不思議ですが、今回の調査が妥当だという仮定に立てば、超加工食品が刺激するシステムが、がんやアルツハイマーに関わる部分と異なっているということなのかもしれません。いずれにしても超加工食品の摂りすぎには気をつけたいものですね。
編集部まとめ
今回紹介した研究は、超加工食品の摂取と死亡リスクの関連を明らかにし、食生活の改善が健康に与える影響を示唆しています。特に循環器疾患や神経変性疾患との関連が指摘され、未加工または最小限の加工食品の摂取が推奨されます。一方で、調査方法の違いやデータの古さといった課題もあり、さらなる研究が求められます。食生活は健康維持に直結する要素の1つです。日々の食習慣を見直し、バランスの取れた食事を心がけましょう。