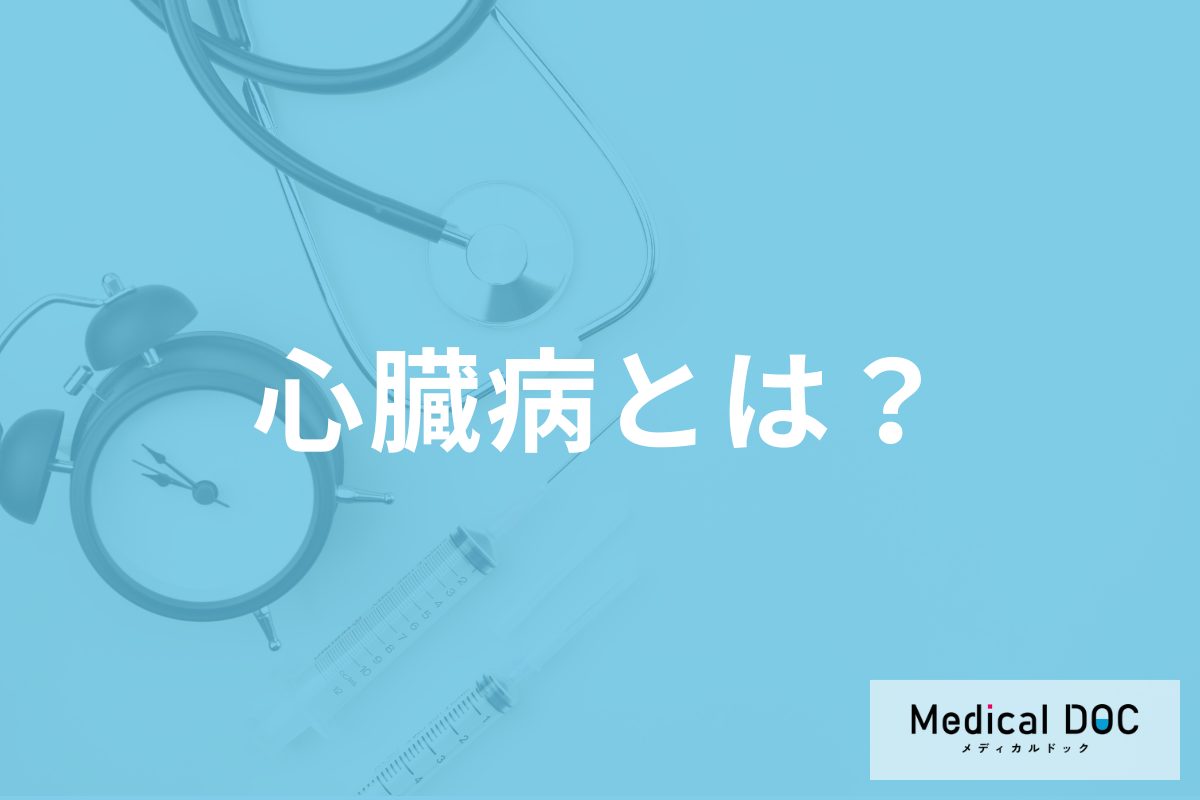「胃が張る」原因はご存知ですか?医師が監修!

胃が張る、重苦しいという症状に悩まされることはありませんか。症状はあってもどの薬を飲むべきかがわからないこともあります。
また症状が続くと、重い病気なのではないかと、とても心配です。
ここでは、胃が張るという症状の原因と対処法、症状から考えられる病気や胃薬の飲み方について解説します。
胃が張るという症状が改善されない場合は、大きな病気が隠れている可能性もあるため、速やかに医師の診断を受けましょう。

監修医師:
中路 幸之助(医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター)
目次 -INDEX-
胃が張る症状の原因と対処法
胃が張って圧迫されるような感じがあり苦しい症状は、「膨満感」といわれることもあります。軽い症状であれば特に何もせずに済ませてしまうこともあるかもしれませんが、症状が続くととても不快です。胃が張る症状は様々な原因から起こり、胃が原因ではないこともあります。中には早急に治療が必要となる病気が原因のこともあるので、十分注意しましょう。特に強い腹痛や息苦しさがある場合、急に強い膨満感が起こった場合は、速やかに医療機関の受診をおすすめします。
空腹時に胃が張る場合の原因と対処法
空腹時に胃が張る場合は、胃の粘膜が荒れていることが原因です。さらに痛みがある場合は、胃の粘膜を胃酸が刺激している可能性があります。症状が続く場合は、胃潰瘍の可能性もあるため早めに医師の診断を受けましょう。空腹時だけではなく、食間に胃が張ったり、いつまでも食べ物が胃に溜まっていたりする感じがあるような場合は、胃の働きが悪くなっていることが考えられます。食べ物の消化に必要な胃酸の分泌が低下したり、消化したものを送り出す蠕動運動が弱くなったりすることが原因です。胃の働きが悪くなる原因としては、以下のものが挙げられます。
- 加齢
加齢に伴い胃の働きが弱くなり、消化に時間がかかります。そのため胃の中に食べ物が長くとどまり、胃が張るようになります。
- ストレス
自律神経のバランスが崩れることで胃の働きが低下するため、同様に膨満感などの症状が起こります。
暴飲暴食
脂っこい食事をした場合は消化に時間がかかるため、胃が張る症状や不快感が気になることがあります。
これらの原因の対処法は以下の通りです。
- 食べすぎに注意する
- 食べる時間に注意する
- 脂っこいものやアルコールなど、胃に負担のかかる食べ物を控える
- ゆっくりよく噛んで食べる
- ストレス解消をする
- 休息を十分に取る
胃や腸に負担がかかったままの状態にならないよう、日頃の生活を見直してみましょう。これらの方法でも改善しない場合や、強い痛みを伴う場合は、医療機関の受診を検討しましょう。
食後に胃が張る場合の原因と対処法
食後に胃が張る症状がある場合は、「機能性ディスペプシア」という病気が考えられます。機能性ディスペプシアの主な症状は、食後に胃がもたれる・食事開始後すぐに胃が張る感じがある・みぞおちの痛み・みぞおちが焼ける感じがするというものです。機能性ディスペプシアは、これらの不快感が続いているにもかかわらず、検査をしても異常が見つからないことが多いという特徴があります。緊急性はありませんが、不快な症状が長く続くため苦痛です。胃の動きを良くし消化を助ける消化促進薬や、胃酸の分泌を抑える薬を飲むことで症状が落ち着くこともあるため、気になる場合は一度受診したほうがいいでしょう。また、睡眠不足や食生活が影響していることも多いため、生活習慣を見直してみることも重要となります。
胃が張って痛い場合の原因と対処法
胃が張ってしまい痛みを伴う場合は、腸の働きが低下しガスが溜まることが考えられます。食事の際、空気も一緒に飲み込んでしまうことでお腹にガスが溜まってしまうこともあります。早食いの場合は特に注意が必要です。また、暴飲暴食をした時に腸内細菌のバランスが崩れて悪玉菌が増え、異常発酵を起こすことによりガスが増えることもあります。特に女性の場合は、冷え・運動不足・デスクワークなどにより腸の働きが低下し、ガスが溜まりやすいことが多いといわれています。ガスが溜まることにより胃の張りや痛みを感じる場合は、ゆっくりよく噛む・食べすぎを防止する・冷えを防止するなどの対処法を試してみましょう。
胃が張る症状で考えられる病気
ここからは、胃が張る症状で考えられる病気について解説します。いずれも詳しい検査や治療が必要になる病気です。必要となる検査には、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)・大腸内視鏡検査・カプセル内視鏡検査・腹部CT検査などがあります。気になる場合はすぐに受診を検討しましょう。
がん
胃が張る症状で一番心配な病気は「がん」です。胃がんの場合、がんにより胃の中や出口が狭くなることで胃が張る症状や胸やけ・吐き気・便秘・下痢などの症状が出てきます。また、胃腸の働きが低下しガスが溜まり、胃が張る症状が出ることもあります。胃が張る症状に加え、胸が圧迫されることによる息苦しさや呼吸困難などの呼吸器症状、倦怠感や足のむくみなどが出現する場合は、腹水が原因です。胃がん以外でも、大腸がんによる腸閉塞・膵臓がんによる十二指腸狭窄、女性の場合は卵巣がんなどでも胃が張ることがあります。がんは早期発見や早期治療が望まれるため、定期健診を受けることが予防のために重要です。またがんではありませんが、上腸間膜動脈症候群により血管が十二指腸を圧迫し、症状が出ることもあります。こちらもすぐに対処が必要な病気となります。少しでも気になる症状がある時は速やかに医療機関を受診しましょう。
胃炎
胃炎には急性胃炎と慢性胃炎があります。それぞれの原因と対処法は以下の通りです。
- 急性胃炎
突然みぞおちのあたりに痛みを伴う場合、急性胃炎が考えられます。原因は暴飲暴食・ストレス・食中毒・アルコールなどです。胃の機能が低下するため胃が張る症状も起こります。また吐き気や下痢を起こすことも多いです。重度になると嘔吐・吐血・下血の可能性があります。同様の症状では、急性胃潰瘍と診断されることもあります。これらは検査をしないと判断できませんので速やかに医師の診断を受けましょう。治療は、まずは原因を除去することです。軽症の場合は併せて薬物療法を行います。重症で出血を伴う場合は、止血をする治療が必要となり、状態により入院が必要となることがあります。
慢性的に胃の粘膜に炎症が起こっている状態です。胃が張る症状や胃痛も起こります。ピロリ菌や慢性的なストレスなどが原因です。食生活を見直したりストレスを解消したりなどの対処法がありますが、急に痛みや胃が張る症状が強くなる場合は速やかに受診しましょう。
胃炎は良く聞く病気で、日常の生活習慣やストレスが大きく関係します。一度生活習慣を見直してみましょう。良く聞く病気とはいえ放置すると大きな病気の原因となることもあるため注意が必要です。気になる症状が続いている場合は、一度医療機関を受診することをおすすめします。症状に応じた薬物療法などの治療が必要です。
過敏性腸症候群
腸に炎症などの病気がないにもかかわらず腹痛や不快感が続き、それに伴い便秘や下痢の症状が続く病気です。便の性状・頻度から下痢型・便秘型・混合型・分類不能型の4つに分類されます。下痢型は男性に多く、便秘型は女性に多いといわれています。腸にガスが溜まり、胃が張ることがあるのです。検査等では腸に異常が認められず原因不明です。ストレスにより、腸が痛みを感じやすかったり、過敏な状態になったりすることが影響しているのではと考えられています。また、細菌やウィルス感染による感染性胃腸炎にかかった後、腸内環境が変化することも原因として考えられています。過敏性腸症候群の患者さんは、腸内細菌が異常に増殖することがあり、その状態は小腸内細菌異常増殖症と呼ばれています。主な治療は、食事療法・運動療法・薬物療法です。気になる症状が続いている時は、一度受診を検討しましょう。
逆流性食道炎
胃の内容物や胃酸が逆流することにより、食道に炎症が起こることでみぞおちの不快感・胸やけ・胃が張るなどといった症状が起こるものです。通常は食道と胃のつなぎ目に下部食道括約筋というものがあり、胃から食道に内容物が戻ることはありませんが、加齢・食べすぎ・肥満などの影響で下部食道括約筋が緩むと逆流が起こります。お腹の症状だけではなく、声がかすれることやよく咳が出るなどの症状が起こることもあります。逆流性食道炎は内視鏡での診断が可能なため、気になる場合は受診しましょう。治療薬により症状を軽くすることができますが、併せて次のような対処法が有効です。
- 食べすぎを防ぐ
- 早食いをしない
- アルコールや喫煙を控える
- 食後2時間~3時間は横にならない
- 横になる場合は枕を高くする
適切な治療をするとともに、このような方法を行い生活習慣を改善していくことが大切です。気になる症状がある場合は、医療機関の受診をおすすめします。
胃が張るときに市販の胃薬を飲んでもいい?
胃が張って辛いときは、胃薬を飲めば楽になるかもしれないと考えるのではないでしょうか。胃薬は薬局でも手軽に買うことができますが、どの胃薬を飲めばいいか迷ってしまうことがあり心配です。ここでは、市販薬を飲んでもいいのか、どの種類の市販薬を飲むといいのかについて解説します。
飲み過ぎ・食べ過ぎが原因の場合
飲みすぎ、食べすぎによる消化不良で食後の胃もたれがある場合は、健胃剤や消化酵素剤という種類の胃薬がおすすめです。健胃剤には主に漢方が配合されており、香りや苦味で唾液の分泌が促進され、同時に胃の働きを良くする効果があります。また消化酵素剤は、直接消化を促進させる働きがあるため脂っこい食事の後や食べすぎた後の胃もたれにおすすめです。パッケージを確認し、用法や用量を正しく守って飲みましょう。
原因に心当たりがない場合
はっきりした原因がなく症状もよくわからない時は、まず総合胃腸薬を試してみましょう。複数の効果のある成分が配合されており様々な症状に対応可能な薬ですが、その分緩やかな効き目となります。明らかな症状がある場合はその症状に合った薬を飲む方が効果的です。もし原因がはっきりせず市販薬を飲んでも症状が改善されない場合は、なんらかの病気の可能性もあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
ストレスで胃が張ることがある?
ストレスは、胃が張る症状の原因としてよく挙げられるものです。ストレスや疲労により、自律神経が乱れることで胃腸の働きが弱くなり、食物やガスが溜まることで症状が出てきます。胃腸の働きを制御している要因が自律神経のため、ストレスは胃の症状と密接に関係しているのです。胃腸の状態を保つためにも、ストレスをあまりため過ぎないように心がけましょう。自分なりのストレス解消法を見つけられるといいですが、適度な運動を心がけたり、朝日光を浴びたりすることもおすすめです。
まとめ
今回は、胃が張るという症状について解説しました。胃が張るといっても様々な原因があり、どのような時に症状が出るかによっても対処法が異なります。
良くあることだからと放置してしまうと、大きな病気を見逃してしまうこともあるのでとても危険です。
症状に合った市販薬も多く売っているので、まずは市販薬を試して改善するかを試すことも対処法のひとつとなります。
改善しない時や強い痛みの時は、速やかに医療機関の受診を検討しましょう。