
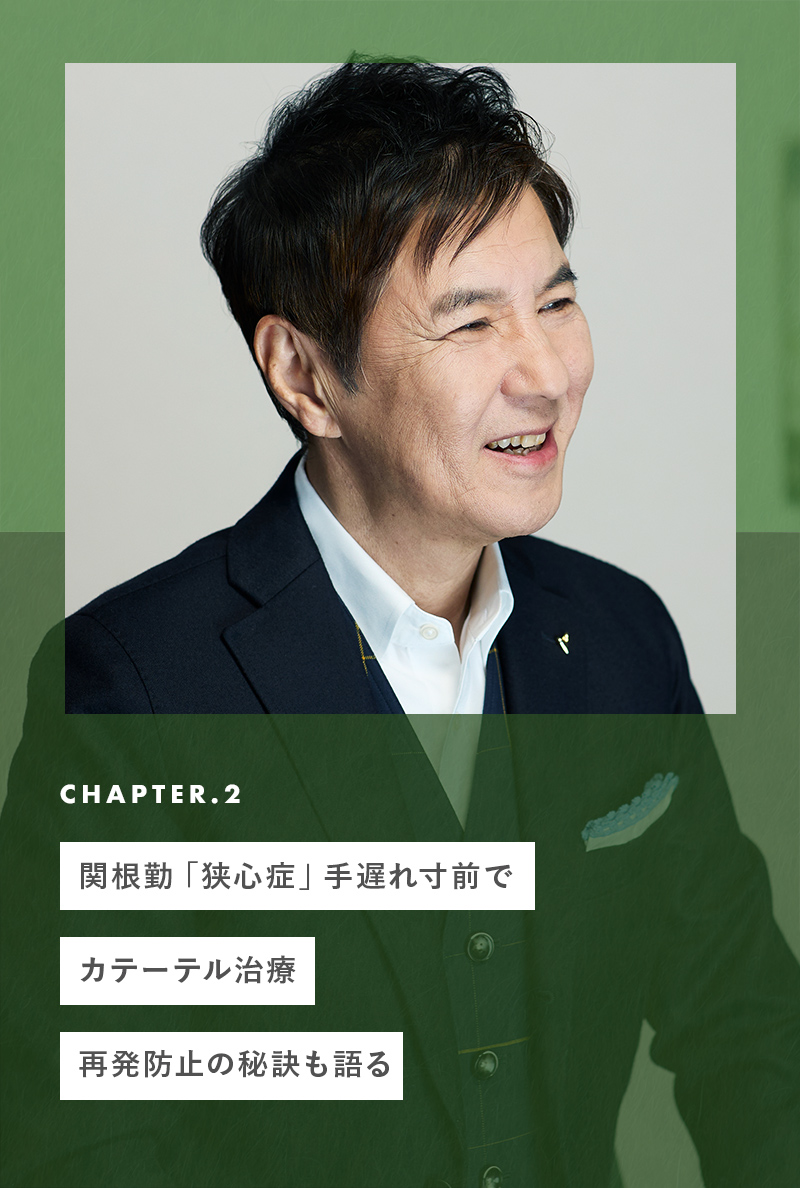
小泉先生
関根さんは狭心症が発覚し、どのような治療をされましたか?
 関根さん
関根さん
カテーテル治療をしました。
小泉先生
カテーテル治療に抵抗はありませんでしたか?
 関根さん
関根さん
私は 50代前半の頃にやっていた医療番組でカテーテル治療について知っていたので、治療に対して抵抗はありませんでした。
小泉先生
術後の経過はいかがでしたか?
 関根さん
関根さん
カテーテルを入れるために手首を2mm切っただけだったので特に問題もなく、次の日から仕事も再開できました。
小泉先生
以前は太ももの太い動脈から治療することが多かったのですが、今ではより細い血管から治療ができるようになりました。医療技術の進歩のおかげだと思います。
 関根さん
関根さん
私がカテーテル治療の経験を公表したところ、同じような治療をした人たちから声をかけられるようになり、周囲にこんなにもカテーテルやステント治療を受けた人がいることに驚きました。おかげで、ステントフレンドが増えました。
小泉先生
医療技術の進歩によりカテーテル治療も大きく進化しており、バイパス手術よりもカテーテル治療の症例数が多くなっています。
 関根さん
関根さん
狭心症の代表的な治療方法について教えてください。
小泉先生
代表的な治療方法は薬物療法、心臓カテーテル治療、バイパス手術の3つです。
 関根さん
関根さん
薬物療法とはどういった治療なのでしょうか?
小泉先生
薬物療法は狭心症そのものを治す治療ではなく、症状が起きた時にそれを鎮めるような治療です。
 関根さん
関根さん
カテーテル治療についてはいかがですか?
小泉先生
一般的におこなわれるカテーテル治療はバネ状のステントを冠動脈に挿入し、それを風船で膨らませて冠動脈を広げるという治療です。
 関根さん
関根さん
バイパス治療についても教えてください。
小泉先生
詰まって狭くなった心臓の血管に迂回路、つまりバイパスを作る治療法です。
 関根さん
関根さん
バイパス手術になると本当に大変ですね。どんな人が適応になるのでしょうか?
小泉先生
冠動脈は3本あり、その根本が詰まった場合や3本全てが狭くなった場合は適応となります。また、血管が硬くてカテーテル治療ができない人にもバイパス手術は適応となることが多いですね。
 関根さん
関根さん
最終手段に近いわけですね。
小泉先生
そうですね。関根さんは現在、再発防止のために心がけていることはありますか?
 関根さん
関根さん
食生活には気をつけるようにしています。
小泉先生
具体的にはどのような点に気をつけていますか?
 関根さん
関根さん
コレステロール値が高かったので、バターを控えてパンにはオリーブオイルを使うようにしています。野菜を食べるのが苦手でしたが、できるだけ食べるようにしています。普段から便秘気味で、これが心臓にも良くないなと感じたので、ヨーグルトにグラノーラを加えて食べたり、青汁を飲んだりすることで便秘が解消しました。
小泉先生
非常に大切なことだと思います。
 関根さん
関根さん
運動はしたほうがよいですか?
小泉先生
体の血液循環を良くして動脈硬化を防ぐことが非常に大切なので、運動習慣は重要です。また、運動すると脈が速くなりますが、冠動脈が細くなってくると血流不足で症状が出やすくなり早期に異常を発見できる可能性もあります。そういった意味でも運動は大切だと思います。
 関根さん
関根さん
普段から運動していれば異常に気づきやすいということですね。
小泉先生
そうですね。早期発見につながります。関根さんは定期的に受診されていますか?
 関根さん
関根さん
3ヵ月に1回の頻度で受診しており、血液検査の結果は全て正常の範囲内です。
小泉先生
よくコントロールされているということですね。関根さんのように一度発症した人は再発しやすくなります。再発を防ぐためには飲み薬をきちんと服用し、食事や運動に気を付けて規則正しい生活を送ることが大切です。
 関根さん
関根さん
私の場合は番組の企画で詳しい検査をしたのですが、一般的には何歳からどのくらいの頻度で検査を受けたらよいのでしょうか?
小泉先生
動脈硬化による病気は年齢とともにリスクが高くなります。特に男性は女性に比べて動脈硬化が早く進むことも多いので、50歳以上の男性は検査を意識的に受けることが大切だと思います。
 関根さん
関根さん
それは体質によるものですか?
小泉先生
女性は女性ホルモンが出ている間は動脈硬化が起こりにくいと考えられています。しかし、閉経後には動脈硬化が進行しやすくなるため、60歳を過ぎたら特に注意が必要です。
 関根さん
関根さん
定期的に検査を受けることが大切ですね。
小泉先生
そのとおりですね。糖尿病や脂質異常症、喫煙歴がある50〜60代の方は定期的な健康診断だけでなく、さらに詳しい検査について主治医と相談することが大切です。
 関根さん
関根さん
狭心症が番組の企画で発覚したのは本当にラッキーでした。家族歴が自分の病気に影響することもあるので、その点にも気をつけることが大切だと感じました。笑うことが健康によいと言われているので、笑いを忘れずに規則正しい生活を心がけていきたいですね。ありがとうございました。

