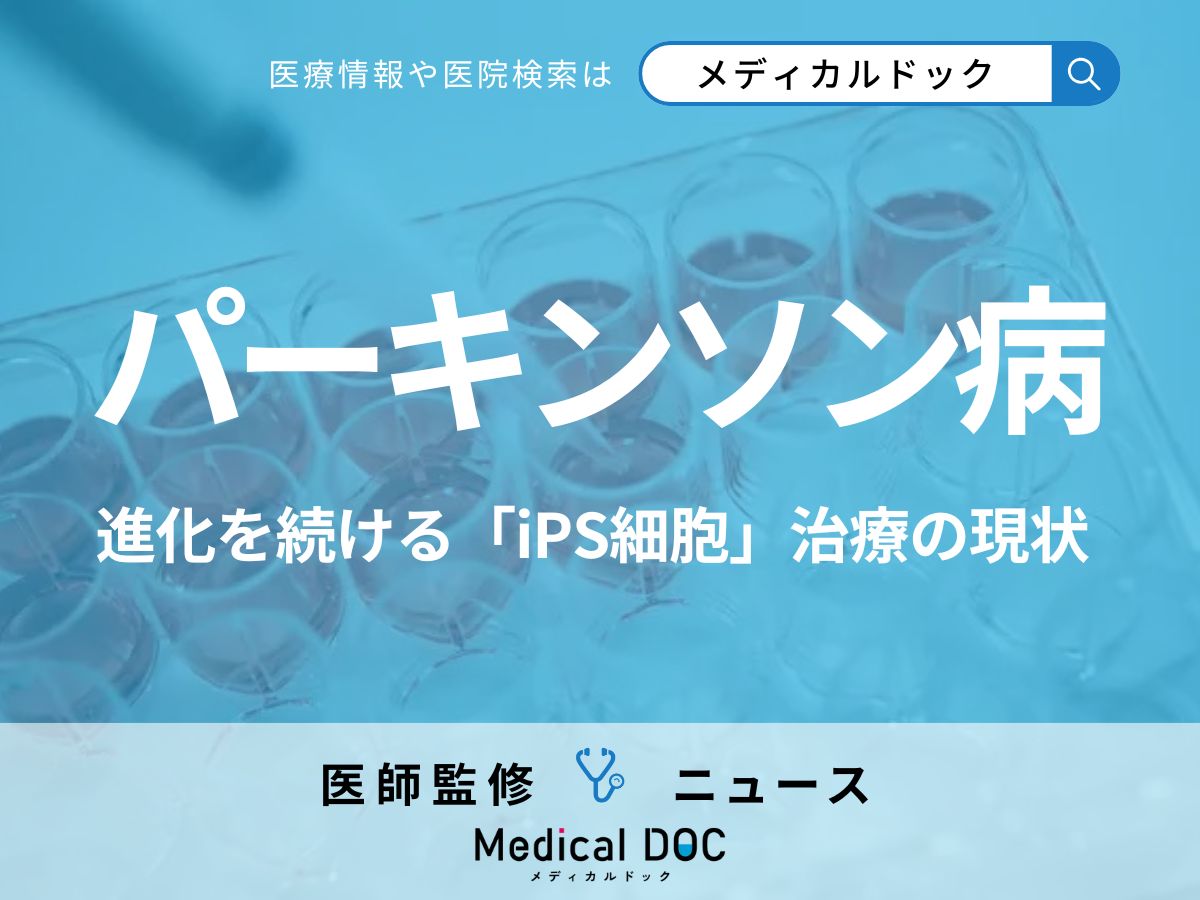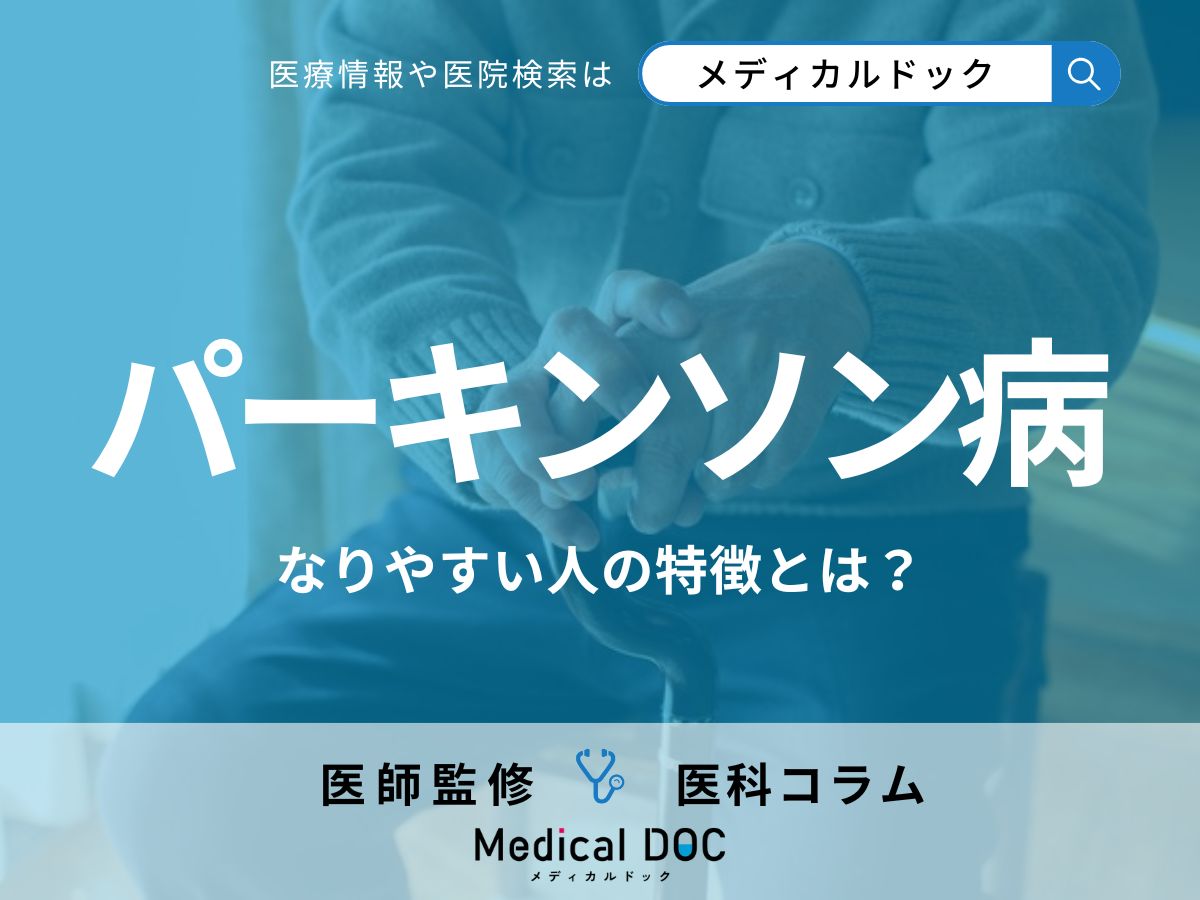「パーキンソン病」予防に“コーヒー”が効果的! カフェインとの関連性を報告 蘭研究

オランダのユトレヒト大学らの研究グループは、「コーヒーを飲むことがパーキンソン病のリスク低下と有意に関連していた」と発表しました。「コーヒーに含まれるカフェインなどが、神経保護作用に関係している可能性が示された」としています。このニュースについて中路医師に伺いました。

監修医師:
中路 幸之助(医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター)
研究グループが発表した内容とは?
今回、オランダのユトレヒト大学らの研究グループが発表した内容について教えてください。
![]() 中路先生
中路先生
今回紹介するのはオランダのユトレヒト大学らの研究グループが発表した内容で、研究成果は、学術誌「Neurology」に掲載されています。
研究グループは、パーキンソン病リスクを低下させることにコーヒーの摂取が関連することが複数の研究で示唆されているものの、カフェインおよび代謝産物とパーキンソン病の発症予防との関連を示した研究はないことに注目しました。
研究グループは、ヨーロッパの18万4024人を対象に解析を実施しました。対象者のうち593例が追跡期間中にパーキンソン病を発症しました。対象者をコーヒーの摂取量ごとに4グループに分けて解析をおこなった結果、最もコーヒーを飲むグループはコーヒーを摂取しないグループと比べて、調整後ハザード比が0.63と最も低くなりました。なお、カフェインレスコーヒーの摂取とパーキンソン病との関連は認められなかったそうです。また、中央値で8年後にパーキンソン病と診断された281人に限定して解析を実施したところ、最もコーヒーを飲むグループはコーヒーを摂取しないグループと比べて、調整後ハザード比が0.54となり、リスク低下とより強い関連が明らかになりました。
研究グループは、今回得られた成果について「カフェインが含まれるコーヒーを摂取すると、パーキンソン病の発症リスクを低下させることが示された。コーヒーによる神経保護作用は摂取量に依存的で、カフェインや主要な代謝産物が大きく寄与している可能性がある」と結論づけています。
パーキンソン病とは?
オランダのユトレヒト大学らの研究グループによる発表で取り上げられた、パーキンソン病について教えてください。
![]() 中路先生
中路先生
パーキンソン病は厚生労働省の指定難病で、神経難病の中で最も患者数が多い疾患です。人口10万人あたり100~120人の患者がいると言われており、発症年齢は50~60歳代で、日本では男性よりも女性の方が多いとされています。パーキンソン病の大半は非遺伝性で、遺伝性は5~10%です。
パーキンソン病の4大症状として、体が震える「振戦」、筋肉の緊張が強くなって手足の動きがぎごちなくなる「固縮」、動作が遅くなる「寡動・無動」、転びやすくなる「姿勢反射障害」が挙げられます。運動障害にあたる4大症状以外の非運動症状としては、嗅覚低下、便秘、頻尿や排尿困難、立ちくらみ、起立性低血圧、睡眠障害、記憶障害、うつ、幻覚・妄想などがあります。
研究グループが発表した内容への受け止めは?
今回、オランダのユトレヒト大学らの研究グループが発表した内容についての受け止めを教えてください。
![]() 中路先生
中路先生
オランダの研究グループは、カフェイン含有コーヒーの摂取はパーキンソン病のリスクを低下させることを報告しました。また、コーヒーによる神経保護作用は摂取量に依存的であると報告しています。これらは大変興味深い研究結果と考えられます。今後、カフェインおよびそれぞれの主要代謝産物が、具体的にどのようにして神経保護に関わっているかのさらなる研究も検討されます。しかし、今回の研究は大規模な縦断コホート研究ではあるものの、既存のデータを用いた後ろ向き解析であることから、コーヒー摂取とパーキンソン病との本当の因果関係は不明です。今後、前向きのさらなる検討が必要であると考えられます。
まとめ
オランダのユトレヒト大学らの研究グループは、「コーヒーを飲むことがパーキンソン病のリスク低下と有意に関連していた」と発表しました。パーキンソン病は高齢化によって患者数が増加していく傾向があるだけに、今後より注目が集まる研究と言えそうです。