ALSで声を失ったニャンちゅう声優・津久井教生。「生きればいいじゃん」妻と歩む“不治ではない”未来(2/2ページ)

「難病であって不治ではない」ALS研究30年の青木正志教授が語る治療法開発への挑戦と希望

![]() 津久井さん
津久井さん
青木先生は長年、ALSを含む難治性の病気の治療法に関する研究にご尽力されていますが、そもそもどのようなきっかけでこの分野の研究を志されたのでしょうか。
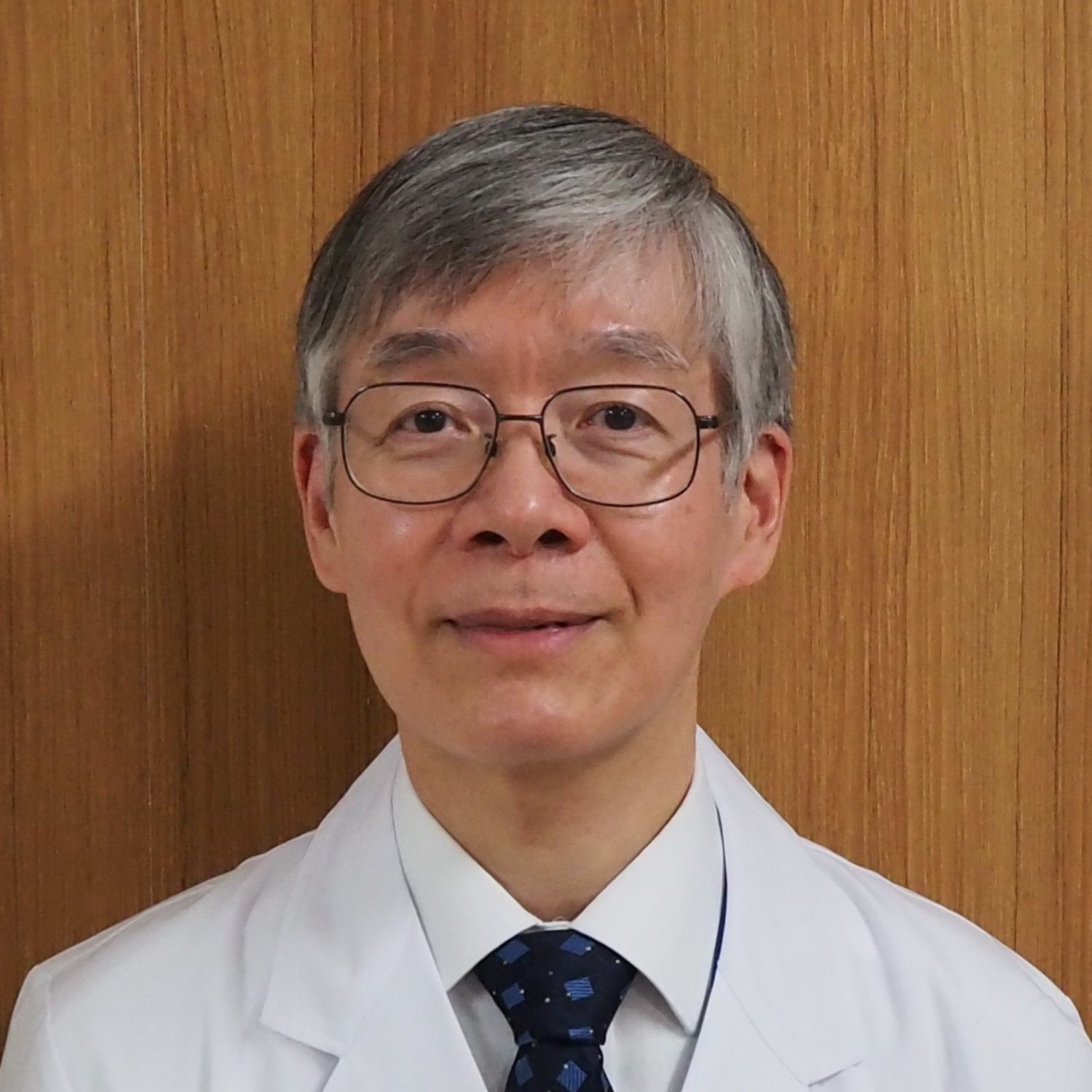 青木先生
青木先生
私がALSのことを考え始めたのは、医学部の学生の頃です。病院のベッドサイドでいろんな患者さんのことを見る中で、一番大変だと感じたのが、「病気はどんどん進んでいく、でもそれに対して何もできない」という現実でした。その代表格が、この筋萎縮性側索硬化症、ALSだったのです。「こういう病気を治せるようになったらどんなに素晴らしいことか」と、ある意味単純にこの研究をやりたいなと思ったのが最初だと思います。治らない病気の人がいるのなら、そういう病気を治したい。そういう思いで神経内科に入ったというのもあります。
![]() 津久井さん
津久井さん
先生は日本神経治療学会の理事長や東北大学脳神経内科の教授といった重責を担われている一方、以前「根本治療がない現状に、医師として無力さを感じる」「患者さんに申し訳ない」といった言葉を口にされていたと伺いました。そうした「責任」とどのように向き合い、日々の原動力に変えてこられたのでしょうか。
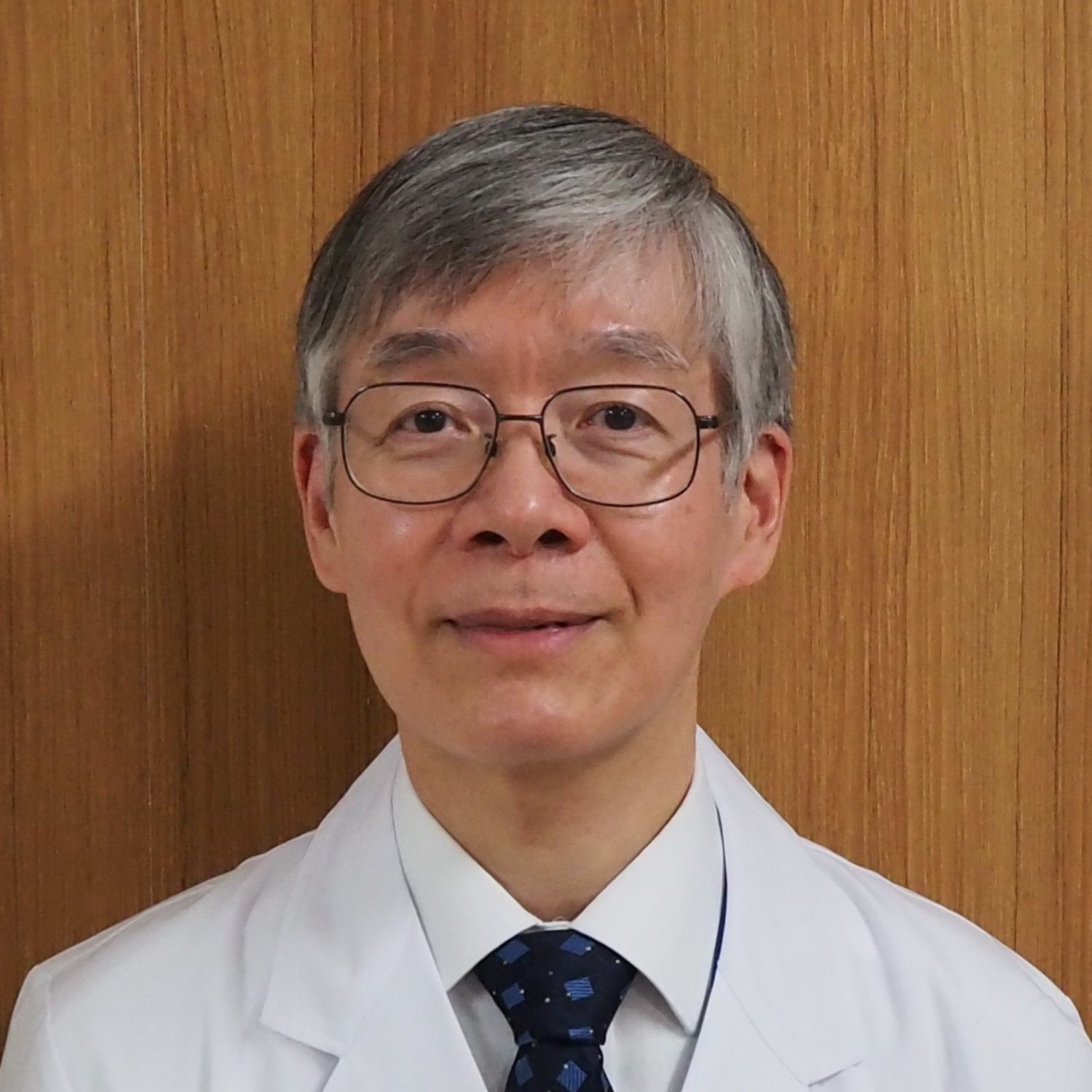 青木先生
青木先生
今学生にはこう質問をしています。「治せる病気を治す医者と、治せない病気を治したいと思っている医者、どっちになりたい?」と。若い子ほど、「自分は治せる病気を治したい」と答えます。しかし、医者をやっていくなかで、「治せない病気こそ自分たちが頑張らなきゃいけないんじゃないか」と考える人も出てきます。多くの患者さんが「ALSです」と言われた後も頑張っています。そこに我々は応えなければいけないというか、患者さんと一緒に頑張っていかなければいけないと感じています。
![]() 津久井さん
津久井さん
研究がうまくいかず、心が折れそうになることはありませんか。
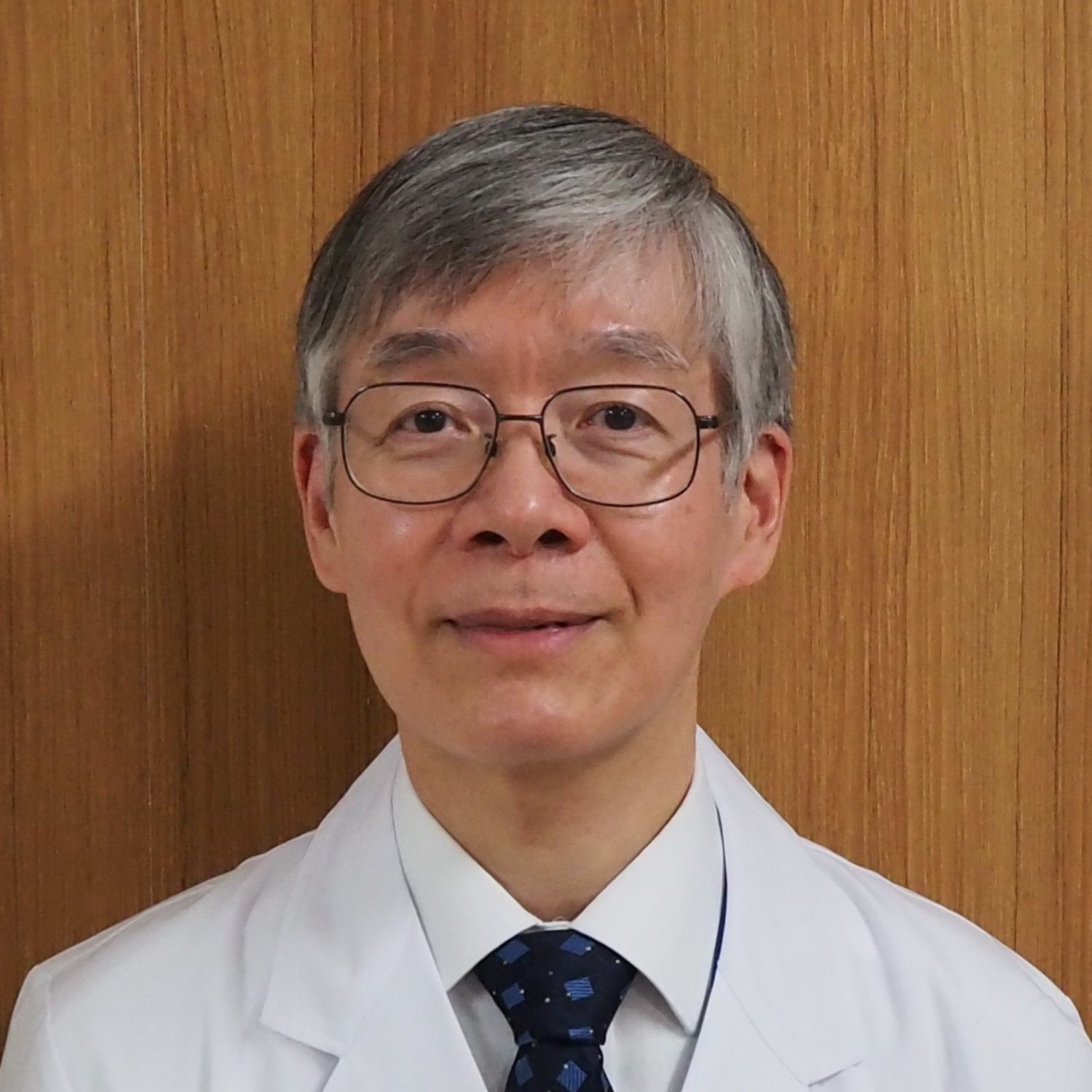 青木先生
青木先生
研究がなかなかうまくいかないと、「何やってるの」みたいな感じで言われることもあります。しかし、研究者として心が折れそうになったときも、「私たちは研究の成果を待っていますから」と患者さんから励まされるわけです。それはありがたいですよね。患者さんに支えてもらっているという感じです。
![]() 津久井さん
津久井さん
先生は長年、JaCALS(ジャッカルス)というALS患者登録システムの構築と運営に関わってこられました。全国に散らばっていたデータを集約したことで、研究や薬の開発はどのように変わったのでしょうか。
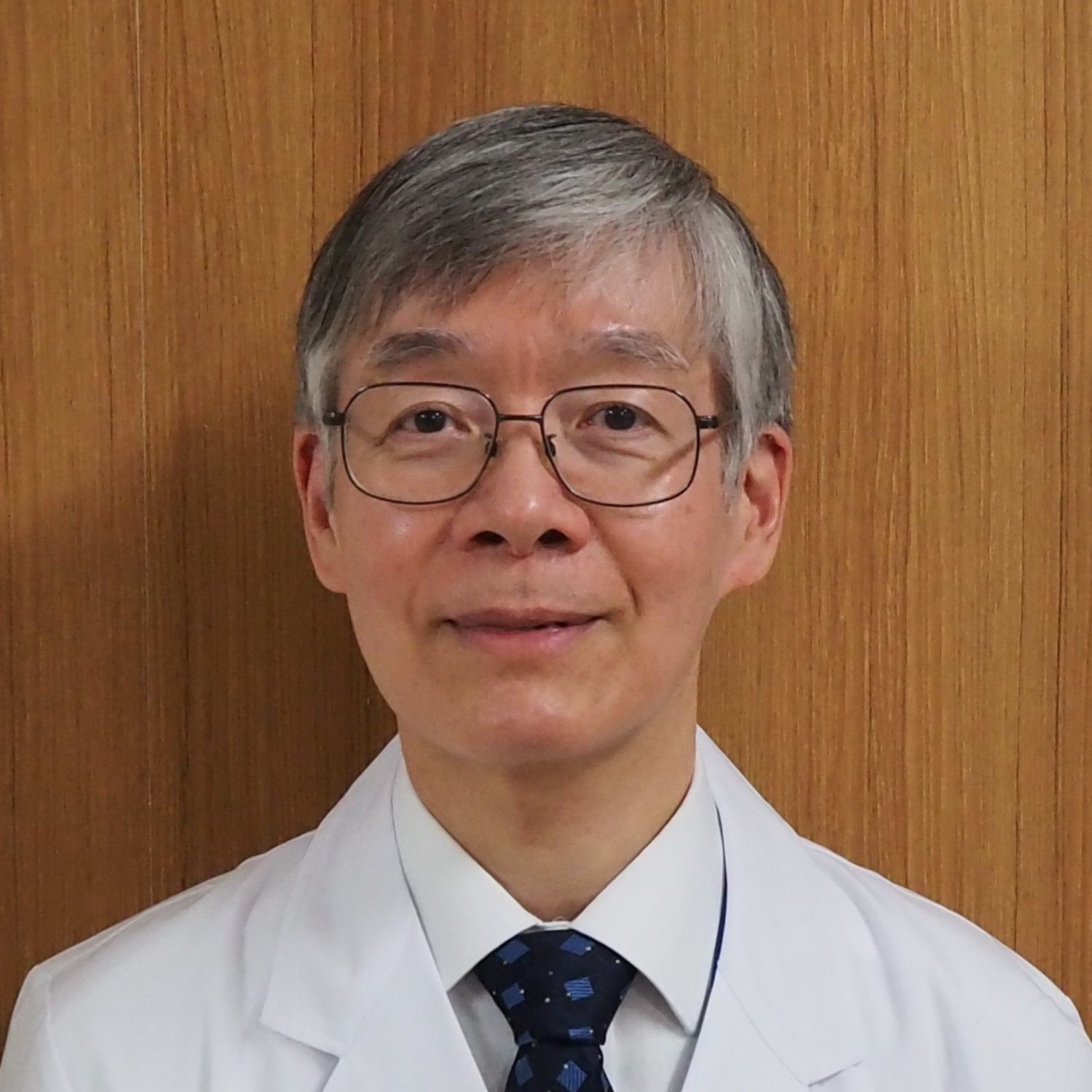 青木先生
青木先生
ALSは希少疾患で、国内の患者さんは現在1万人ほどです。全国に散らばっているので、臨床データがなかなか集まりにくく、一つの病院だけではデータが十分に集まりません。どのように病気が進んでいくか、どういう薬が良くて悪いか、研究で判断するためには登録制度が必要でした。JaCALSは希少疾患における登録制度の草分け的存在です。3000例近くの登録は海外でもあまりないぐらいです。こういう長い積み重ねが貴重なデータになってくると思います。そしてこれは、患者さんのご協力があって成り立っているものです。
![]() 津久井さん
津久井さん
患者として、このシステムに協力することが将来の治療にどう繋がっているのか、とても関心があります。
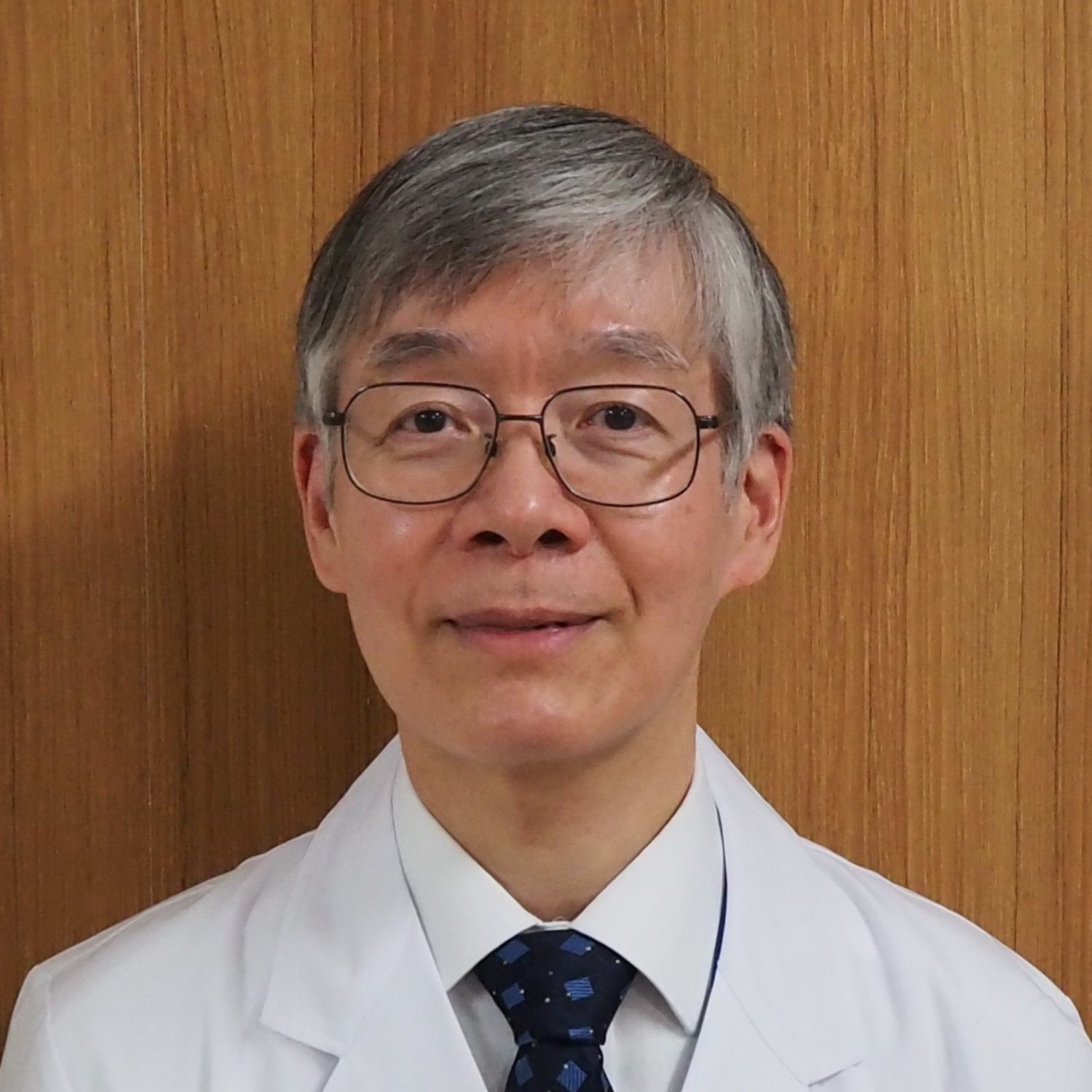 青木先生
青木先生
データが集まってこないと次の治療に進むことができません。登録制度の運営にはお金も人手もかかるので、公的に研究の助成を受けたり、産学連携で製薬会社にデータを使ってもらう代わりにお金を入れてもらったりと、そのような工夫をしながら運営しています。
![]() 津久井さん
津久井さん
東北大学は歴史的にALS研究の世界的拠点であり、多くの発見がここから生まれていると聞きました。原因遺伝子の発見は実際の治療薬開発においてどのような手がかりとなるのでしょうか。
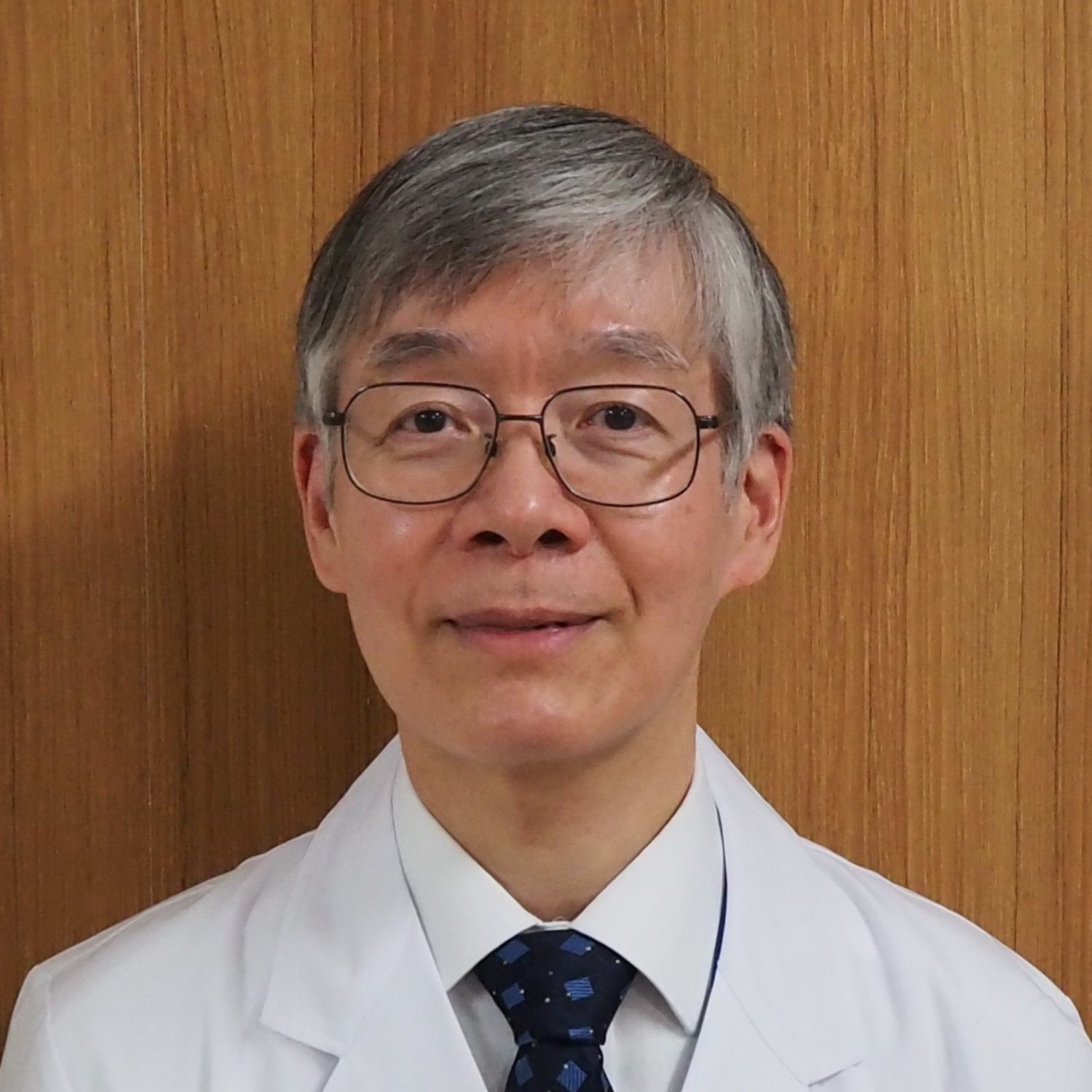 青木先生
青木先生
ALSの中には5%ぐらい、20人に1人ぐらい家族性のALSという方がおられます。そういう家系から遺伝学的解析で原因遺伝子にたどり着くことができます。最初に分かったのは、1993年の「SOD1」という遺伝子の変異です。その遺伝子の機能を抑え込む「トフェルセン」というお薬が2024年に使えるようになり、一部の家族性ALSの患者さんは、ある程度病気の進行が抑えられるかもしれないというところまで来ています。SOD1の次に標的になりそうなのが「FUS」という遺伝子変異で、日本では2番目に多い原因遺伝子です。この遺伝子変異に対する薬の開発も進んでいます。このように、家族性のALSの治療は世の中に出てきていますね。
![]() 津久井さん
津久井さん
家族性ではない、孤発性のALS研究についても教えていただけるとうれしいです。
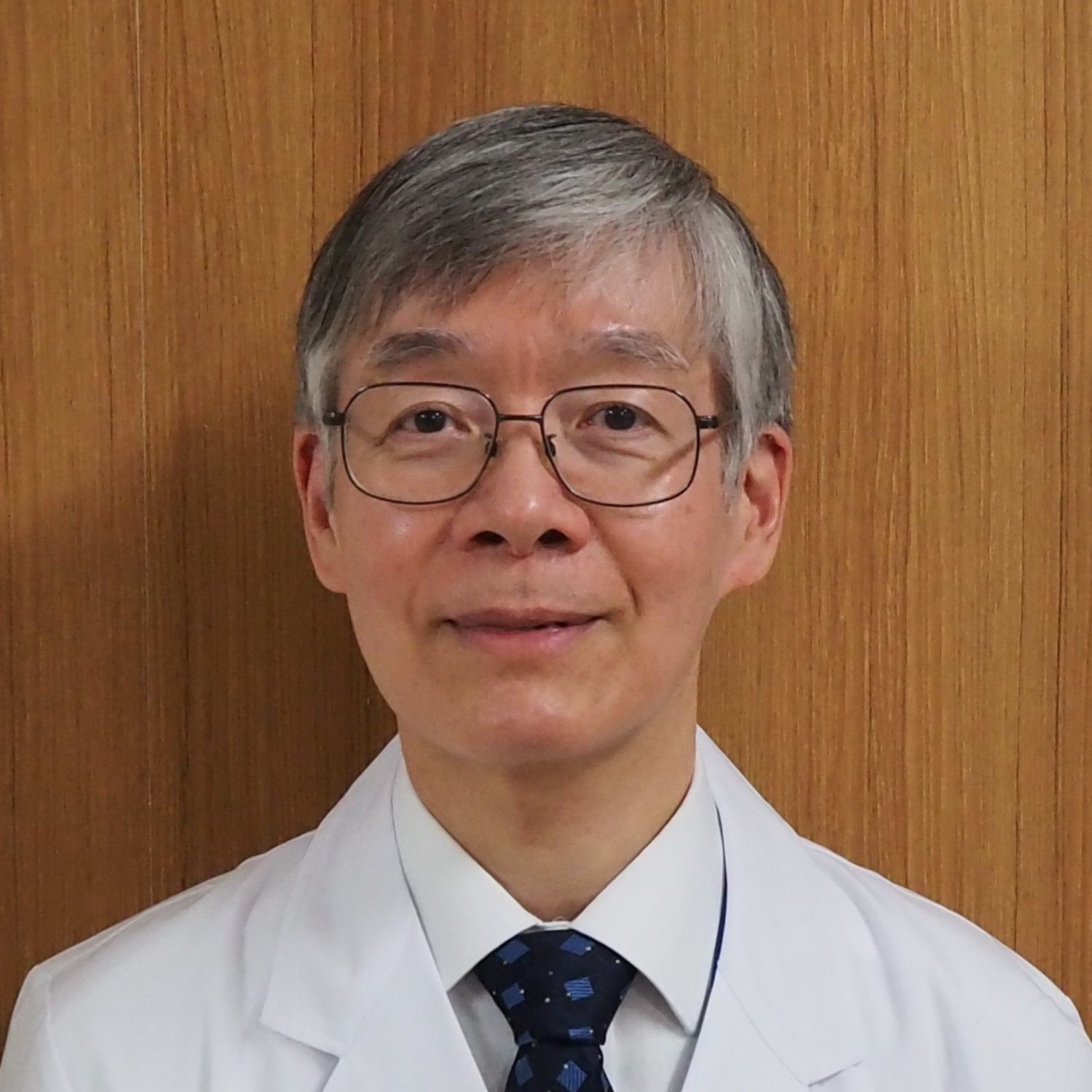 青木先生
青木先生
孤発性も家族性と病態は相当似ているんじゃないかと考えています。研究は必ずしも家族性のALSのみを研究をしているのではなく、両方進めていると考えていただいた方がいいかと思います。ただ、原因が分かっているものからのほうが研究しやすい面はあります。病気というのは、持って生まれた体質プラス環境ですので。何がきっかけでALSになるかは、なかなか分からないものです。何万人と患者さんが集まれば環境要因の解析もできるかもしれないのですが、今の手法ではなかなか難しいです。しかし、そのうちできるようになってくるかもしれません。
![]() 津久井さん
津久井さん
先生は神経細胞を保護するタンパク質「HGF(ヘパトサイトグロースファクター=肝細胞増殖因子)」を用いた治療法の開発、特に脊髄へ直接投与するという画期的な治験を主導されていると聞きました。有望な治療の「種」があっても、それを多くの患者さんが使える薬にするまでには、壁があるのでしょうか。
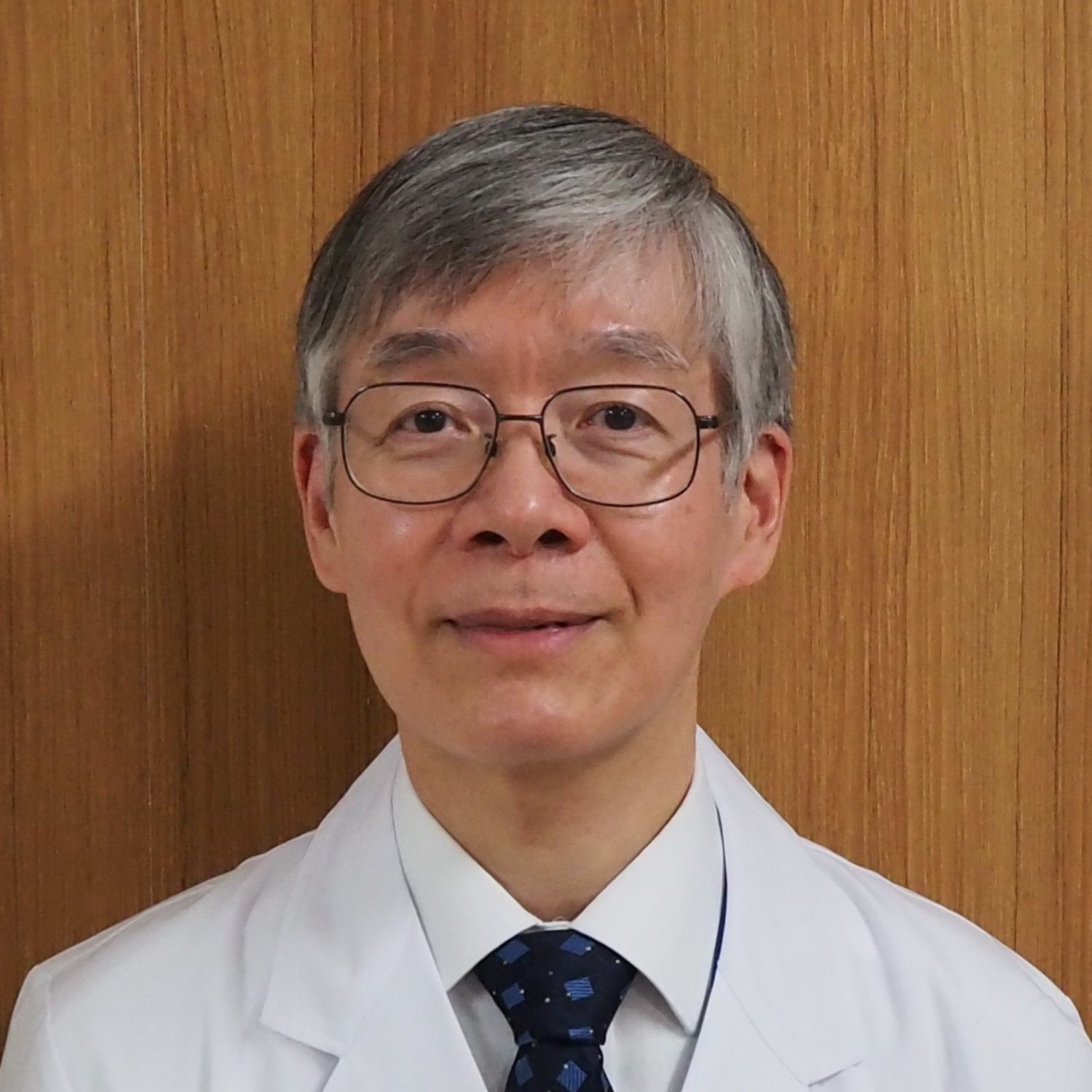 青木先生
青木先生
HGFというのは元々肝臓の再生因子です。肝臓は人体で唯一再生できる臓器で、それはこのHGFがあるからなのです。HGFは中枢神経系にもあって、運動ニューロンの発達にも使われている強力な再生誘導因子です。動物実験でも運動ニューロンに保護的に働き、治療に使えることが分かってきました。HGFによる治療の難しさの一つは、「髄腔内投与」という、背中に針を刺して投与しなければならない点です。我々はリザーバーという装置を背中に埋め込んで、2週間に一回、点滴していこうと考えています。
![]() 津久井さん
津久井さん
実際に治療を受ける際、どのような課題があるのでしょうか。
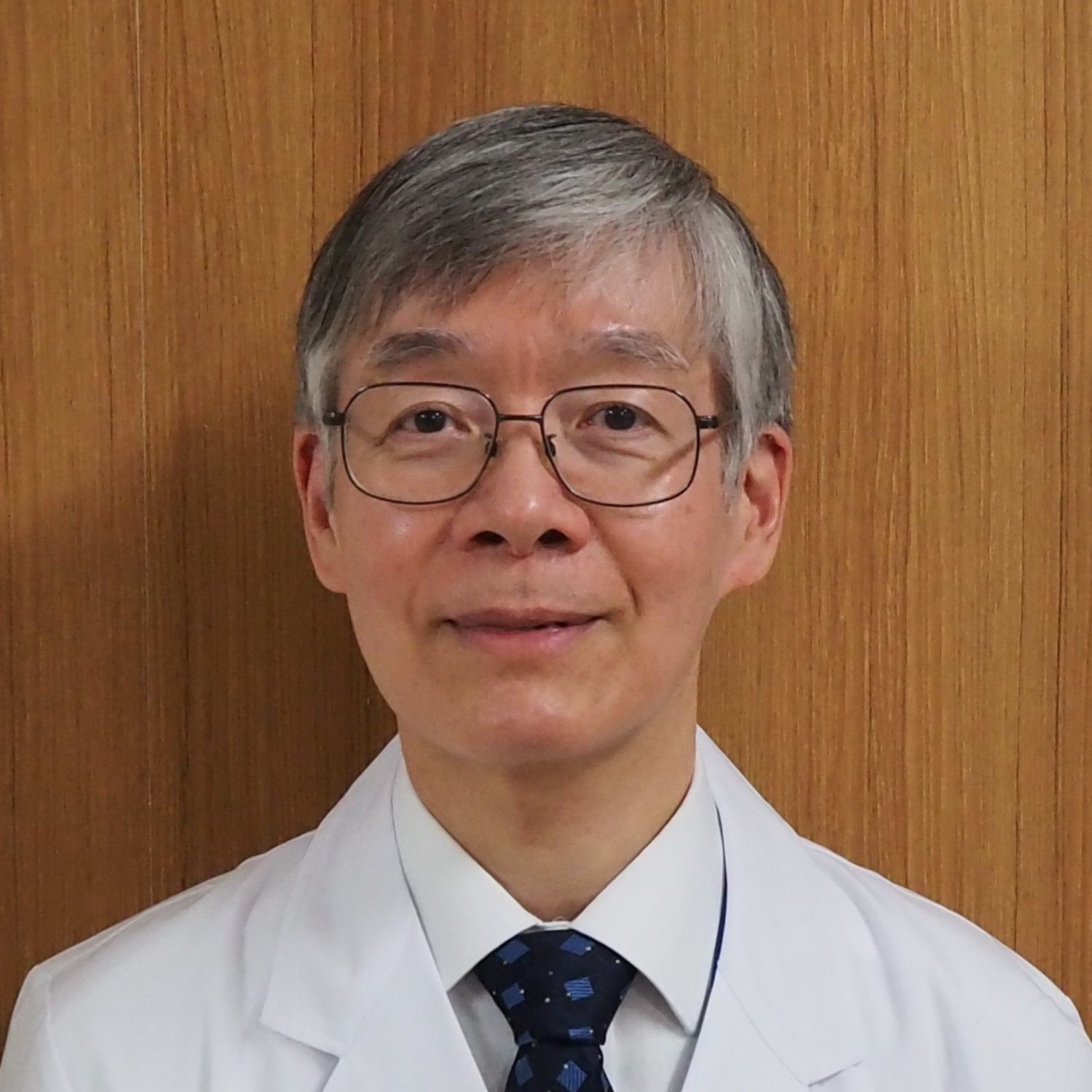 青木先生
青木先生
そのリザーバーが動いてしまったり抜けてしまったりする問題があるのです。今のHGFはタンパク質ですので、投与後にどんどん代謝されてしまいます。ですから2週間に一度、持続的に投与する必要があり、その課題が乗り越えられるかという局面にぶつかっています。脊髄損傷の患者さんの場合、HGFによる治療は一回の投与でいいのでうまくいきそうな段階にあります。結構いい結果が出ていると言えます。そこで承認が取れれば、ALSの承認も近くなると考えています。
![]() 津久井さん
津久井さん
ALSが進行して入院した際、付き添いが認められているはずなのですが、病院で難色を示されることがあるようです。QOLもそうですが、たん吸引などで命に関わる場合もあります。医療現場での考え方もあると思いますが、善処していただけるとうれしいです。
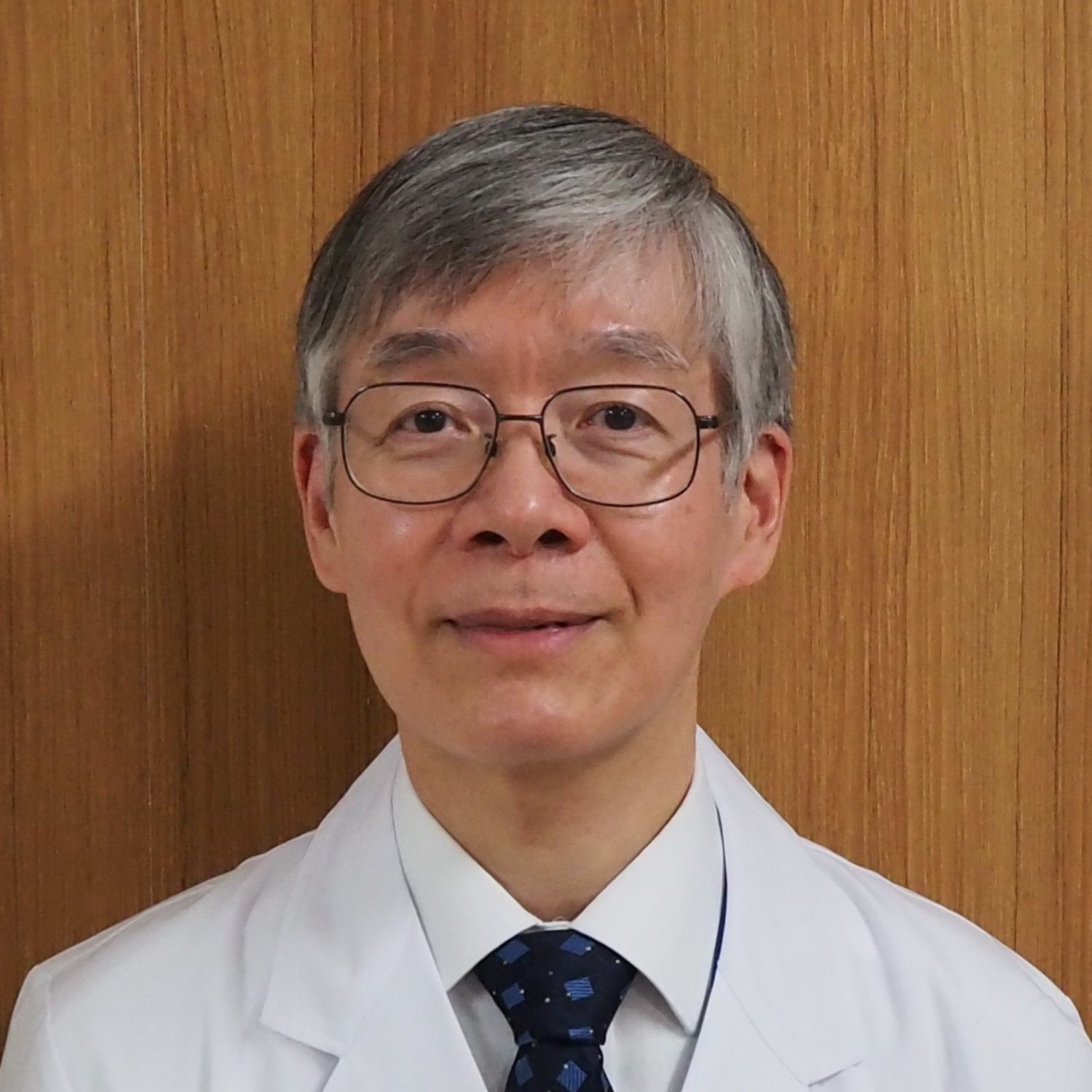 青木先生
青木先生
コミュニケーションが困難な人に対しては、補助する人の付き添いを認めることは多いです。ただし、それが当たり前になると「患者さんが入院したときに必ず付き添ってください」といったことが家族の負担になりかねません。入院したときに家族を少し休ませてあげたいという思いもあるわけです。病院の付き添いはすごく大変です。寝るところもないですし、日中だけだとしても通わなければならなりません。ですので、ケースバイケースですし、できるときは病院のスタッフが頑張るというふうに考えている病院は多いと思います。いろいろな事情があり、病院側としても日々悩んでいるところです。
![]() 津久井さん
津久井さん
先生は、ALSなどの病気を「難病ではあるが、不治ではない」と表現されていました。この言葉には、科学的にどのような希望、そして患者さんへのメッセージが込められているのでしょうか。
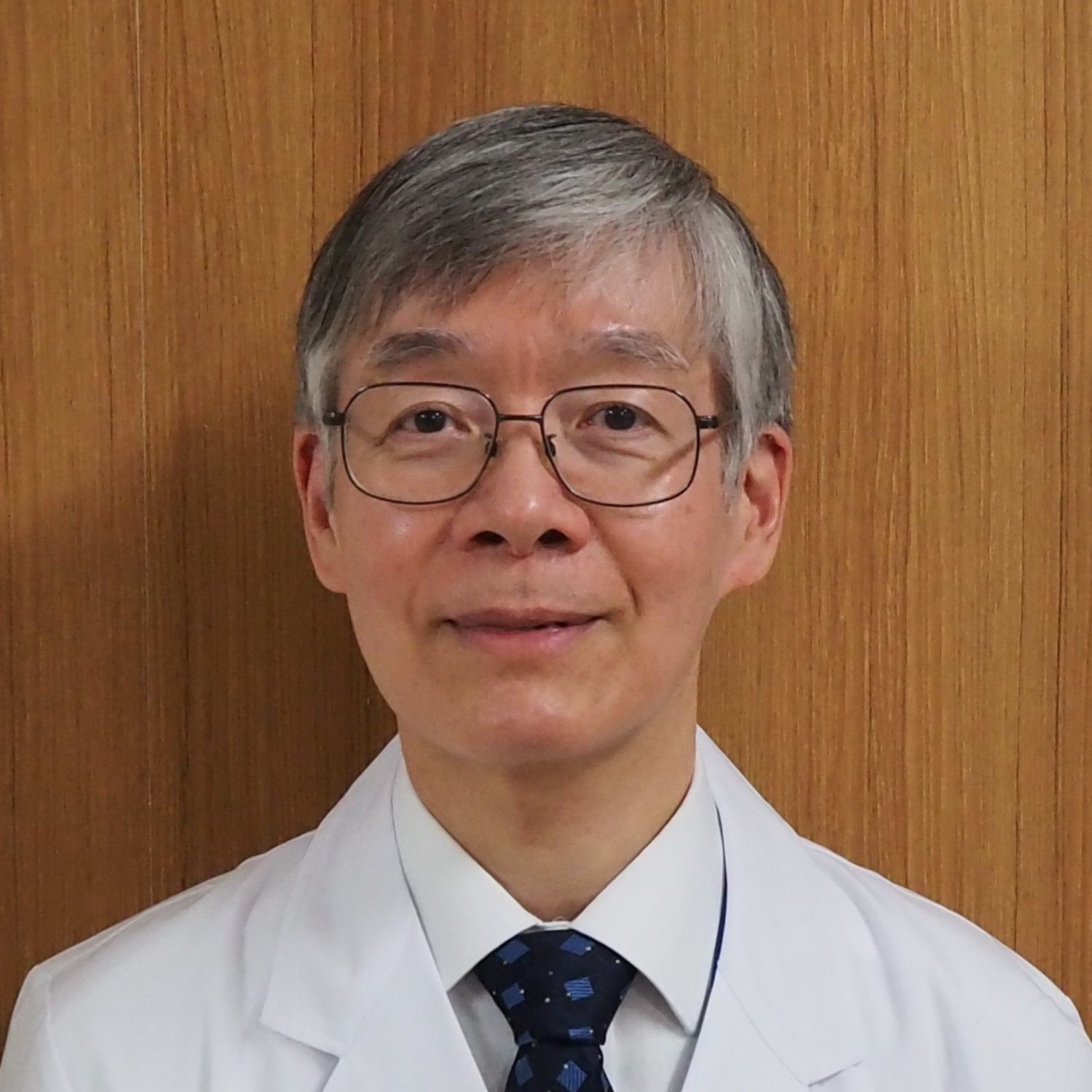 青木先生
青木先生
昔、難病だと思われた病気がどんどん治るようにもなってきていますよね。今は難病かもしれないけど、将来にわたって難病とは限らないということもあります。重症筋無力症という病気があって、「重症」ってついているのですけど、今は医療が進歩して軽症の人が増えてきました。患者さんには、「昔は重症だったから重症筋無力症という名前がついているけど、今は必ずしも『重症』ではないのです」と説明します。だから自分が今「難病だ」と言われたからといって、諦める必要はないと考えています。ALSと言われたらもうおしまいかといえば、そんなことはありません。患者さんがまだまだ生きたいと思えば、平均寿命以上に生きている患者さんもたくさんいらっしゃるわけですから。難病と不治というのはちょっと違うかなというふうに考えています。
![]() 津久井さん
津久井さん
医師という職業は大変な仕事だと思います。治療法がないと説明していても、なんとかしてほしいと患者は訴えます。早く治療法を見つけてくださいと求め続けます。日々研究を重ねて、いろいろなチャレンジをして、現代医学の知識をフル活用しても解明に至っていないのが、難病に指定されている病気です。この難しい病を解明しようとなさっている青木先生を始めとする医師の皆さんを、心より応援しています。私も難病の一つのALSの患者として、あきらめないでALSの治療法が開発されていくことを望み続けたいと思います。
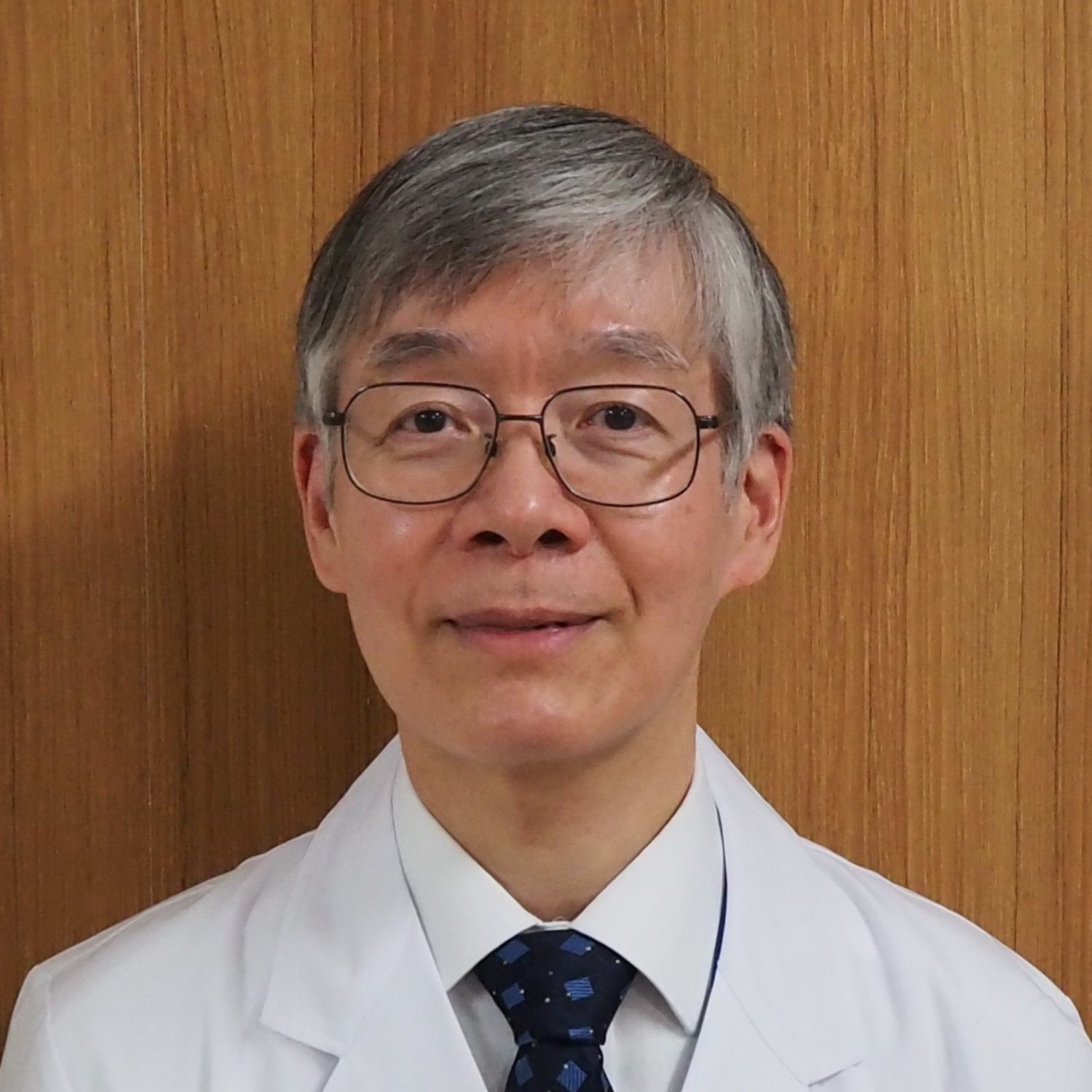 青木先生
青木先生
患者さんの頑張っている姿を見ると、自分たちも頑張らなきゃ、患者さんにできることは何かと考えます。お互いに一緒のものに向かって闘っていくんだという、そういう関係を構築していきたいと考えています。
![]() 津久井さん
津久井さん
少しだけ、私の弟の話をさせてください。2016年に弟はスキルス性胃がんで天に召されました。がんの存在が分かって闘病を始めて半年後のことでした。こんな理不尽なことがあっていいのかと思いました。弟も無念だったと思います。そしてその事を教訓にして、健康には人一倍気をつけていたつもりでした。しかし3年後の2019年にALSに罹患して公表しました。「なんで?」という思いはあります。
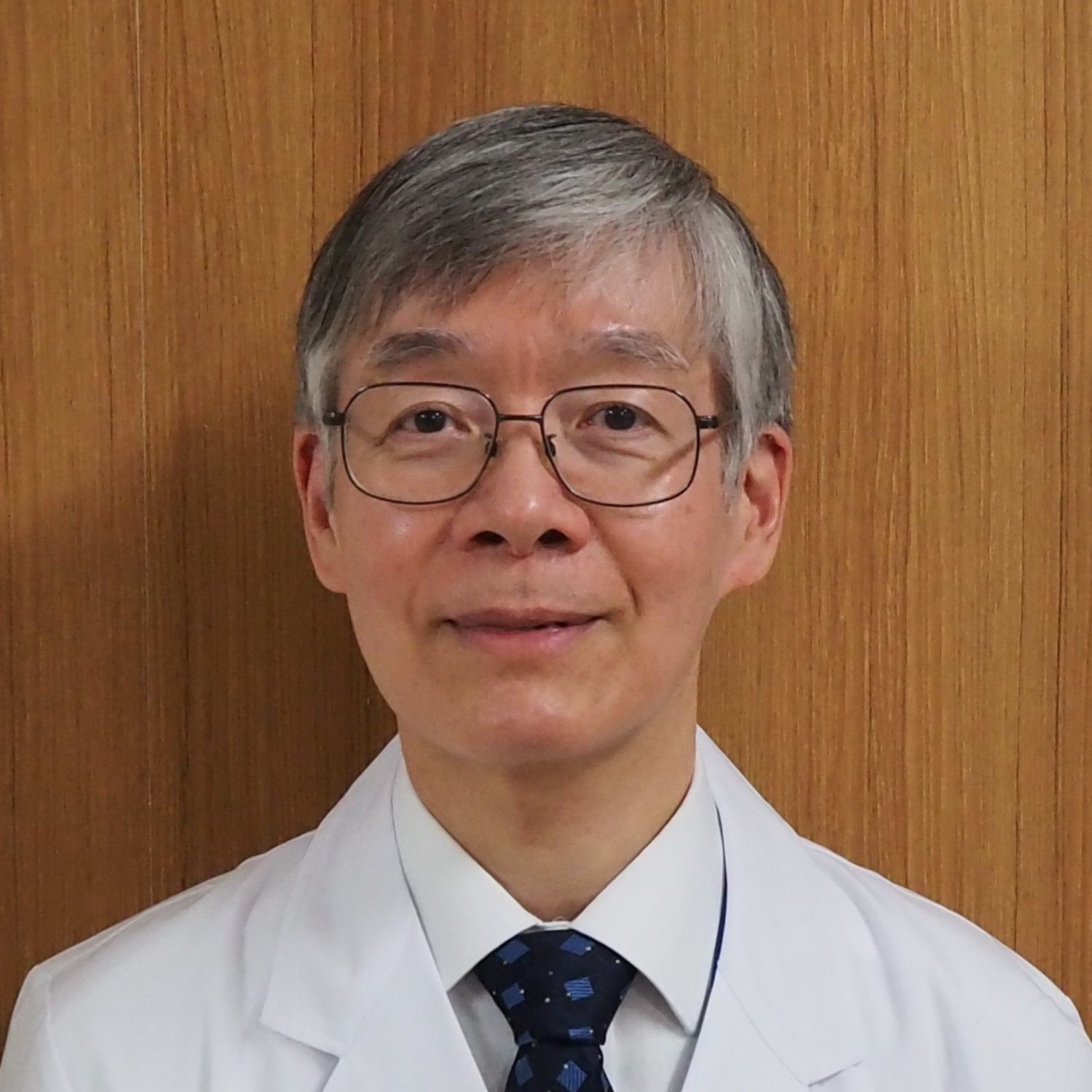 青木先生
青木先生
そのようなお気持ちを抱えながら、どのように前を向いてこられたのでしょうか。
![]() 津久井さん
津久井さん
このような病気に罹患している人たちのなんと多いことかと感じています。一人ではない、皆さん闘病しているのです。弟もそうでしたが、あきらめてはいけないと思います。一人にならずに周囲とコミュニケーションをとって、今できることをやっていくことが大切なのだと思います。
編集後記
取材を通じて最も心に残ったのは、津久井さんご夫妻の前向きな姿勢でした。「できなくなったこと」を嘆くのではなく、「どうすればできるか」を考える。その考え方が、日々の暮らしに小さな喜びを生み出しています。また、青木先生の「難病であっても不治ではない」という言葉には、研究者としての揺るぎない信念を感じました。病と向き合う患者と、治療法を追い求める医師。両者が支え合い、共に歩む姿は、困難に直面するすべての方への希望のメッセージとなるはずです。















