「仙腸関節痛」の治療法や完治するまでの期間はご存知ですか?【医師監修】
公開日:2025/03/16
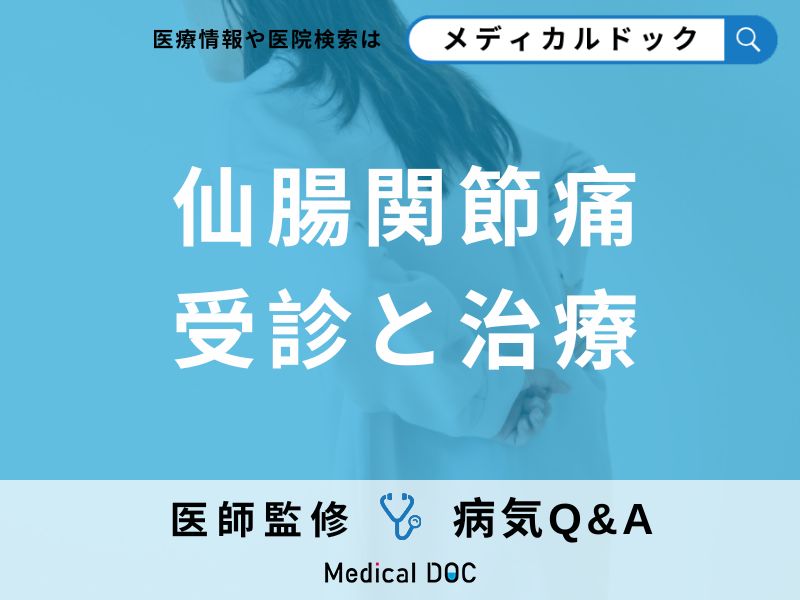
厚生労働省が実施した国民生活基礎調査(2019年)有訴者率(病気やけが等で自覚症状を持つ者の割合)によると、腰痛は男性では第1位、女性では肩こりに次ぐ第2位でした。
しかし、一言で腰痛といっても様々で、部位・疾患によって治療法・リハビリ内容も変わってきます。
仙腸関節痛というのは聞きなれない病名かもしれませんが腰痛の一種であり、あなたが今抱えている痛みは、もしかするとそれに分類されるかもしれません。
こちらでは仙腸関節痛の何科に受診すれば良いか・検査・治療についてもご紹介致しますので、ご自身の症状と照らし合わせてご覧ください。

監修医師:
郷 正憲(徳島赤十字病院)
プロフィールをもっと見る
徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。
※この記事はMedical DOCにて『「仙腸関節痛」になると現れる症状・原因はご存知ですか?医師が監修!』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。
目次 -INDEX-
仙腸関節痛の受診と治療

仙腸関節痛を疑う場合は何科を受診すれば良いでしょうか?
仙腸関節痛は腰痛の1つですので、疑いのある場合に受診する診療科目は整形外科です。
しかし、画像検査での発見が難しいため、見逃されやすく注意が必要です。仙腸関節部を含む臀部の痛みに関して、患者さんは腰痛として訴えることがありますが、医師は腰痛の認識がない場合もあるためしっかりと経過と症状を伝えることが大切になります。
しかし、画像検査での発見が難しいため、見逃されやすく注意が必要です。仙腸関節部を含む臀部の痛みに関して、患者さんは腰痛として訴えることがありますが、医師は腰痛の認識がない場合もあるためしっかりと経過と症状を伝えることが大切になります。
仙腸関節痛はどのような検査で診断されるのでしょうか?
わずかな動きしかない仙腸関節は、MRI・CT・レントゲン等の画像検査では診断が困難なのが現状です。そこでまずは、画像所見と症状からその鑑別を行います。
そして、仙腸関節痛の診断で時に重要とされているのが、患者さん自身の症状と触診です。検査・診断には以下の方法が用いられます。
そして、仙腸関節痛の診断で時に重要とされているのが、患者さん自身の症状と触診です。検査・診断には以下の方法が用いられます。
- ワンフィンガーテスト:患者さん自身の人差し指で痛みの部位を指し示してもらう方法。日常生活の中で、どのような姿勢でどこが痛むのか示してもらう。
- 仙腸関節への疼痛誘発テスト:医師の手によって仙腸関節や骨盤の前方部分(鼠径部)を圧迫する方法。圧迫することで捻じれが増強し、痛みが増すため診断の補助となる。
- 仙腸関節ブロック:最終的に仙腸関節からくる痛みが疑われれば、仙腸関節ブロック(局所麻酔を使った痛み止め注射)を行い、効果のある場合は仙腸関節痛と診断される。
治療方法について教えてください。
まず行われるのは、以下の保存的治療です。 多くの場合、この保存療法が有効なことが報告されています。
- 安静:負荷のかかる動作を控えて安静にしてもらうことで痛みの沈静化を図る。(これは長期間の安静が良いということではなく一定期間である)
- 鎮痛剤の使用:疼痛の程度・状況により選択される。
- 骨盤ゴムベルト:骨盤周囲を抑えることで、仙腸関節痛を一時的に抑える効果がある。仕事復帰等の再発予防にも使われる。
これらの治療で改善がみられない場合には、以下の方法が選択されることもあります。
- 仙腸関節ブロック:仙腸関節に局所麻酔を注射し、痛みの軽減を図る。
- AKA(関節運動学的アプローチ)博田法:素手で関節の動きを改善する方法。これは行っている医療機関が少ないことや、技術者によって治療効果に差が生じるという問題点がある。
- 仙腸関節固定術:長期の保存療法でも効果がなく、日常生活に支障をきたしてしまう場合に選択される手術。
完治するまでの期間を教えてください。
同じ仙腸関節痛であっても、その方の関節の状態・痛みの程度・日常生活の様子・仕事内容・年齢等によって、完治するまでの期間にも差があるので一概には言えません。
1~2回の治療で完治する方もいれば、年単位で長期の治療が必要な方もいます。治療と同時に、日常生活の中で、引き金となっている動作をどれくらい避けることができるかで完治までの期間も大きく変わります。仙腸関節に負担がかかり続けて痛みを慢性化させてしまわないことが重要です。
1~2回の治療で完治する方もいれば、年単位で長期の治療が必要な方もいます。治療と同時に、日常生活の中で、引き金となっている動作をどれくらい避けることができるかで完治までの期間も大きく変わります。仙腸関節に負担がかかり続けて痛みを慢性化させてしまわないことが重要です。
編集部まとめ

仙腸関節痛について詳しくまとめました。仙腸関節痛を引き起こしてしまう原因をしっかり知っておくことで、発症を防ぐことも十分にできます。
日常生活における動作の1つ1つをもう一度見直して、痛みの原因を取り除いていきましょう。
また症状が出た場合は、どこにでもある腰痛だと放置せずに早めに受診し、早期診断・適切な治療を受けて慢性化・難治化しないようにしましょう。



