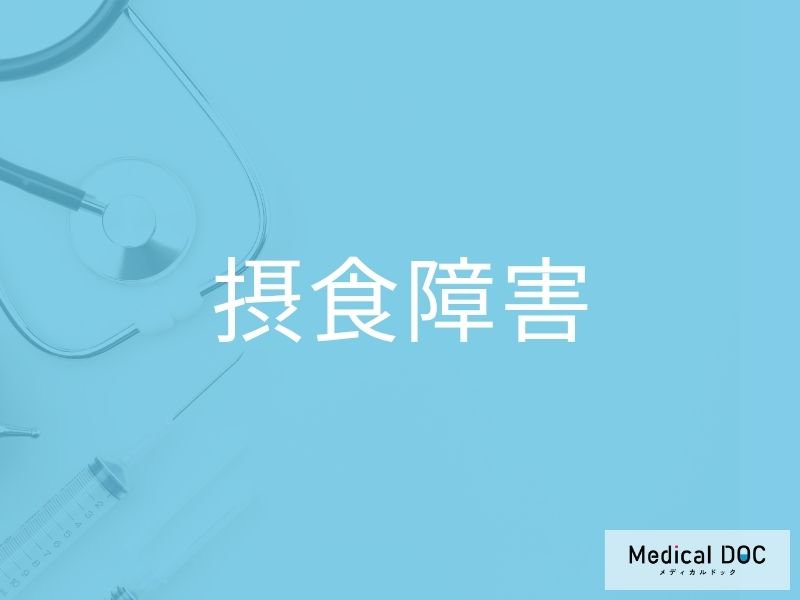

監修医師:
伊藤 有毅(柏メンタルクリニック)
精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。
保有免許・資格
医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医
目次 -INDEX-
摂食障害の概要
摂食障害は、体型や体重を過度に気にして極端に食事を減らしたり、ストレスから過食したりする精神障害です。この障害は、10代〜20代の若い女性に多く見られるのが特徴です。摂食障害の患者さんは、食事や体型に対する異常な考え方や行動を持ち、それが生活全般にわたって影響を及ぼします。たとえば、体重の増減に対する過度な恐怖や食べ物に対する過剰な制限、そして過食とそれに続く嘔吐や下剤の使用などです。これらの行動は、健康に重大なリスクをもたらし、栄養不良や内臓の損傷を引き起こすことがあります。摂食障害は、神経性やせ症と神経性過食症の大きく2つのタイプに分けられます。
神経性やせ症
神経性やせ症は、体重や体型に対する恐怖から強迫的に体重減少を求めるのが特徴です。自分が過度に痩せていることを異常と認識できず、食事量をどんどん減らしてしまいます。一方で、食べないことの反動により過食嘔吐を繰り返し、体重増加を防ごうとする患者もいます。自殺率が高く精神疾患のなかでも死亡率が高い疾患です。
食事量の激減は、低栄養による極度の脱水から心疾患や腎不全を引き起こします。また、低栄養状態で急に食物を摂取すると、再栄養症候群という合併症を引き起こし、心不全・呼吸不全・腎不全などの症状があらわれます。さらに、低血圧・無月経・便秘・低体温などさまざまな問題が生じる危険な疾患です。
神経性過食症
神経性過食症は、過食がやめられず体重増加を防ぐために嘔吐や下剤を使用する特徴があります。これらの行動は人前では行わないため周りに気付かれにくいです。特徴的な身体症状として、嘔吐による唾液腺腫脹・吐きダコ・食道の出血などが見られます。また、過度な嘔吐や下剤の使用による電解質異常が原因で不整脈を起こす場合があります。不整脈は命に関わり、過食嘔吐を繰り返すと徐々に危険性が高まっていくため、早期に治療を開始しなければなりません。
摂食障害の原因
摂食障害の原因は多岐にわたり、単一の要因だけでは説明できません。例えば、完璧主義な考え方、勉強や部活などのストレス、人間関係の悩み、家庭内でのストレスなどがあります。このような心理的要因、社会的要因が複雑に絡み合って発症に至ります。
心理的要因
心理的要因としては、完璧主義、低い自己評価、不安やストレスの対処方法が関与します。これらの心理的特性が、摂食行動に異常をきたす原因となることが多いです。また、トラウマや虐待の経験も、摂食障害のリスクを高める要因となります。
例えば、運動や趣味でストレスを発散するのは健康的ですが、過食によりストレスを発散するのは身体に悪影響を及ぼします。そのため、適切なストレス発散方法を覚えることが大切です
社会的要因
社会的要因では、特に現代社会における「痩せているほど美しい」という文化の影響が指摘されています。メディアや広告で描かれるモデルのような理想的な体型が、特に若い女性に強い影響を与え、摂食障害を引き起こすのです。また、周りの友達がモデルのような体型の人ばかりで社会的なプレッシャーを感じ、摂食障害の引き金となることもあります。
摂食障害の前兆や初期症状について
摂食障害の前兆は、食事に対する異常な関心や行動の変化として現れます。これらの症状を早期に察知し、早期治療と予防が必要です。
一般的な初期症状として、急激な体重減少と体重増加が挙げられます。食事の摂取量を極端に制限する、過食と嘔吐を繰り返すなどの行動が見られるでしょう。。また、食事の時間や内容に対して異常にこだわるようになり、食事を避けるための言い訳を頻繁にすることもあります。
さらに、食事に対する異常な儀式的行動も見られます。たとえば、食べ物を非常に小さく切り分ける、特定の順序で食べる、食べる前にカロリーを厳密に計算するなどの行動です。これらの行動は、食事のコントロールを強く意識していることを示しています。
精神的な症状としては、気分の変動やイライラ感、抑うつ症状が見られます。また、体重や体型に対する過度の不満や恐怖感も初期症状の一つです。これらの症状は、患者さんの生活全般にわたって深刻な影響を与えるため、早期の対応が必要となります。
これらの症状がみられた場合、心療内科、精神科などを受診して適切な検査・治療を受けることをおすすめします。
摂食障害の検査・診断
摂食障害の検査・診断は、主に問診や身体検査が行われます。摂食障害では食事や行動に関する変化があるため、医師は問診で患者さんの食事に対する態度や行動、心理状態を詳しく尋ね、摂食障害の判断材料としているのです。
身体検査では血液検査や尿検査が行われます。これらの検査は、栄養不良や電解質異常、内臓機能の低下など、摂食障害による身体的な影響を評価するために行われます。特に、低カリウム血症や低ナトリウム血症は、重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
医師だけでなく精神科医や心理士との面接も、診断で重要な役割を果たします。患者さんの心理状態やストレス要因、摂食行動に関する詳細な情報を収集し、診断を確定させるための材料にします。診断基準には、DSM-5やICD-10が用いられ、これらの基準に基づいて摂食障害の種類や重症度を評価します。
摂食障害の治療
摂食障害の治療は、身体とこころの二つの側面からアプローチが必要です。治療は多職種のチームによって行われ、医師や看護師、栄養士、心理士などが連携して患者さんの回復をサポートします。
摂食障害の患者は、自分が摂食障害であることを認識できていない場合があるため、摂食障害という疾患について説明し、理解してもらう必要があります。まずは患者との信頼関係を構築していき、その後に治療について説明するよう段階を踏んで行きます。今までの認識を一から修正するのは難しいため、いかに動機づけをして治療に向き合ってもらえるかがポイントです。
心理療法では、認知行動療法(CBT)がよく用いられる治療法です。認知行動療法は、摂食行動に関する誤った考え方や信念を修正し、健康な思考パターンを形成することを目的としています。また、対人関係療法(IPT)なども効果的な治療法として注目されています。
身体的な治療としては、まず栄養状態の改善が必要です。摂食障害によって栄養不良や電解質異常が生じている場合、適切な食事指導や栄養補助を実施していきます。食事療法は、個々の患者さんの状況に合わせて計画され、段階的に健康な食事習慣を取り戻すことが目標です。
精神状態に応じて薬物療法の使用も検討していきます。抗うつ薬や抗不安薬は、摂食障害に伴う抑うつや不安の症状を軽減するために用いるのですがあくまで補助的な位置づけであり、心理療法と併用して行われるのが一般的です。
摂食障害になりやすい人・予防の方法
摂食障害になりやすい人には、いくつかの共通した特徴があります。例えば、完璧主義や低い自己評価、過度のストレスを感じているなどは摂食障害のリスクが高いです。また、友達や家族から体型や体重に関して悪く言われた経験が、発症の要因になる場合もあります。
摂食障害を予防するには
摂食障害を予防するには「早期の教育とサポート」「ストレスの管理」「定期的な健康診断」の3つの方法があります。
早期の教育とサポート
早期の教育とサポートの目的として、特に若年層が健康な食習慣や体型に対する正しい認識を持ってもらうことが大切です。そのため、学校や家庭で適切な教育を行い、サポートすることが摂食障害の予防に役立ちます。
ストレスの管理
ストレスの適切な管理方法を学ぶことが予防に効果的です。摂食障害では、不安を感じやすく肯定的な感情が弱いため学校や家庭内など対人関係でストレスがたまります。そのためストレスやプレッシャーに対処する方法を学ぶことで、摂食障害のリスク低減が可能です。そのサポートとして心理カウンセリングや支援グループも、予防と早期発見において重要な役割を果たします。
定期的な健康診断
医療機関や学校での定期的な健康診断は早期発見と予防に効果的です。摂食障害の過食による嘔吐は周囲に気づかれないように行うことが多く、症状を発見しづらいです。特にリスクの高い個人やグループに対しては、定期的なスクリーニングやカウンセリングを行うことで、摂食障害の発症を未然に防ぐことができます。
関連する病気
- 神経性食思不振症
参考文献













