
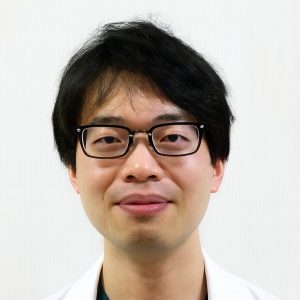
監修医師:
栗原 大智(医師)
目次 -INDEX-
硝子体混濁の概要
硝子体混濁を正しく理解するために、まずは硝子体(しょうしたい)について知る必要があります。硝子体とは、眼球内にあるゼリー状の透明な組織で、水晶体の後ろ側にあります。主な成分は水であり、コラーゲン線維とヒアルロン酸を成分としています。硝子体は加齢などにより、網膜を牽引したり、濁ったりすることで目の病気を発症します。
本来は硝子体は無色透明なゼリー状組織ですが、全体が混濁してしまうとかすみや視力低下などの症状が現れます。また、その混濁が部分的であれば、虫やゴミが飛んで見える飛蚊症、部分的な視野欠損などの症状がみられる場合があります。
硝子体混濁の原因
硝子体混濁の原因は主に5つが原因となります。
- 先天性の混濁
- 変性の混濁
- 炎症性の混濁
- 出血性の混濁
- 腫瘍性の混濁
一般的な硝子体混濁は加齢による変性混濁が挙げられます。しかし、この硝子体混濁が見えにくさなどの原因になることはほとんどありません。また、炎症性の混濁はぶどう膜炎や眼内炎が原因となり、出血性の混濁は眼底出血や硝子体出血が原因となります。腫瘍性の混濁は、眼内悪性リンパ腫などが原因となることが知られています。
ぶどう膜炎
ぶどう膜炎は、目の中の「ぶどう膜」(虹彩、毛様体、脈絡膜)に炎症が生じる疾患で、視力低下や目の痛み、充血、飛蚊症などの症状を引き起こします。原因には、感染性(ウイルスや細菌など)や自己免疫性(ベーチェット病、サルコイドーシスなど)、特発性(原因不明)のものがあります。診断には、視力検査や眼底検査、血液検査、画像検査などを用います。治療法は、ステロイドや免疫抑制薬による薬物治療が中心で、感染性の場合は抗菌薬などを併用します。重症例や合併症では手術が検討されることもあります。
眼内炎
眼内炎は、目の内部(硝子体や網膜など)に炎症が生じる疾患で、視力が大きく下がってしまうため緊急での対応が必要です。主な症状は、急激な視力低下、目の痛み、強い充血、光を眩しく感じる(羞明)などです。原因は、手術や外傷、注射後の細菌や真菌による感染が主ですが、まれに血流を介した感染や内因性の炎症もあります。診断は視力検査、細隙灯顕微鏡検査、眼底検査、超音波検査、硝子体液の培養などで行います。治療は、抗菌薬や抗真菌薬の投与が基本で、重症例では硝子体手術が必要となる場合もあります。早期の適切な治療が視力の回復に重要であり、放置すると失明のリスクが高まります。
眼内悪性リンパ腫
眼内悪性リンパ腫は、結膜や眼窩などの眼球周辺組織や眼球内のリンパ球ががん化し、異常増殖することで発生する血液のがんの一種です。この病気では、眼内を満たすゼリー状の組織である硝子体が混濁したり、光を感じる網膜に白い病変が現れたりするのが特徴です。また、脳への転移が起こりやすく、眼科疾患の中でも予後が悪い病気として知られています。発症率は低く、年間100万人あたり約4人とされています。
眼内悪性リンパ腫は炎症性疾患であるぶどう膜炎と症状が類似しているため、鑑別が難しい疾患としても有名です。そのため、硝子体の細胞診を含む複数の検査が診断に必要です。標準的な治療法はまだ確立されていませんが、放射線療法や硝子体内注射が有効とされています。また、再発や治療抵抗性の場合には化学療法も実施されており、治療成績の向上が期待されています。
硝子体混濁の前兆や初期症状について
硝子体混濁の原因は加齢によるものが多いため、自覚症状はないことがほとんどです。しかし、硝子体混濁の原因によっては、下記のような症状が見られます。
- 見えにくい(視力低下)
- 目が痛い(眼痛)
- 目が赤い(充血)
- 虫やゴミが飛んで見える(飛蚊症)
また、これらの症状は原因によって出てくる症状が異なることがあり、また進行とともに徐々に悪化してくる恐れがあります。これらの症状があれば、まずは眼科を受診しましょう。原因を調べるためにほかの診療科を案内することもあります。
硝子体混濁の検査・診断
硝子体混濁の診断は問診や視診に加えて、硝子体混濁自体の状態を観察することで診断されます。硝子体混濁で行われる検査は以下の通りです。
視力検査
視力検査は眼科検査の基本であり、改善の程度を推し量ることが可能です。加齢に伴う硝子体混濁は、視力に影響しないことがほとんどです。しかし、出血性混濁や炎症性混濁、腫瘍性混濁の場合は視力低下をきたすことがあります。
眼圧検査
眼圧は目の硬さを調べる検査です。硝子体混濁はぶどう膜炎などの原因によっては眼圧上昇を引き起こすことがあります。また、治療に際してステロイド点眼液を用いることがあるため、眼圧検査を定期的に行います。
細隙灯顕微鏡
眼科の基本的な検査で、直接、目の状態を確認します。硝子体混濁の性状、その原因を精査するために必要です。特に、炎症性混濁の原因となるぶどう膜炎や眼内炎では、前房内に炎症や前房蓄膿などの所見があることがあり、診断に有用であるため重要な検査となります。
眼底検査
硝子体混濁がどのような性状なのか、また硝子体混濁の原因を探すために検査を行います。瞳孔を開く目薬(散瞳薬)を用いて瞳孔を開き、眼球内の炎症を評価します。眼底検査を行った場合、散瞳後は車の運転などが難しいため、症状があれば公共交通機関を使うようにしましょう。
血液検査
硝子体混濁の原因を特定するために血液検査を行うことがあります。採血では、硝子体混濁の性状として、炎症性混濁や腫瘍性混濁が疑われれば、ぶどう膜炎や眼内炎、悪性リンパ腫などの精査のために血液検査を行うことがあります。
培養検査
ぶどう膜炎や眼内炎、悪性リンパ腫などが疑われれば、硝子体液を採取して、その原因精査を行います。
画像検査
硝子体混濁のうち、炎症性混濁や腫瘍性混濁が疑われる場合は画像検査を行います。ぶどう膜炎であればサルコイドーシスなどの原因を調べたり、眼内炎であれば内因性疾患の精査を行います。また、腫瘍性混濁であれば眼内悪性リンパ腫の転移の有無や、転移元の有無を確認するために画像検査を行います。
硝子体混濁の治療
硝子体混濁の治療はその原因によって治療方針が大きく異なります。まず、先天性混濁や変性混濁は視力低下をきたすことはまずないため、通常は治療を行わず経過観察をします。
また、炎症性混濁の場合には、原疾患の治療および抗炎症療法を行います。この際、炎症性混濁の原因によっては硝子体手術を行うことがあります。
出血性混濁の場合には出血が吸収される場合があるため経過観察を行うことがあります。しかし、出血が吸収されない場合には硝子体手術を行います。腫瘍性混濁は原因に対する治療に加えて、抗がん剤の硝子体内注射や硝子体手術を行うことがあります。
硝子体混濁になりやすい人・予防の方法
硝子体混濁は加齢によって起こるため、誰でも起こる可能性があります。炎症性混濁のうち眼内炎は外傷あるいは手術後に起こる恐れがあるため、眼球の保護のため保護メガネの着用が推奨されます。特に、ボールが目に当たるリスクのあるスポーツを行ったり、異物が飛入したりする恐れがある場合は注意が必要です。
関連する病気













