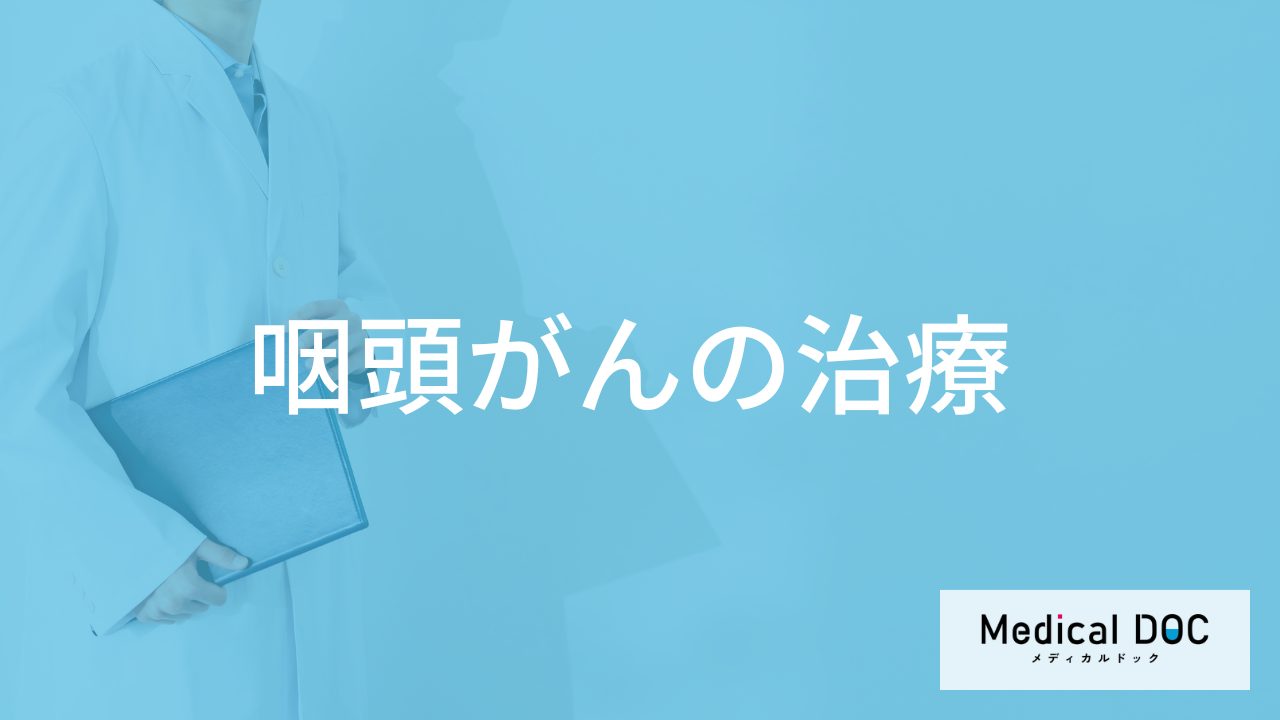「咽頭がん」になると現れる初期症状や原因はご存知ですか?ステージについても解説!

咽頭がんとは、空気や食べ物を分別して送る役割を持つ場所である咽頭にがんができる病気です。
のどの違和感などから始まり、最悪の場合、命にもかかわります。そのため、初期症状などを把握して、早期治療を受けることが大切です。
本記事では、咽頭がんの初期症状についてご紹介します。原因・症状・検査方法から治療法まで解説するので、参考にしてください。

監修医師:
郷 正憲(徳島赤十字病院)
咽頭がんとは?

咽頭がんとはどんな病気なのですか?
一方、咽頭は鼻と口の奥から食道に向かってつながっている部分です。空気が通るだけでなく食べ物も通ります。特に咽頭には、上咽頭・中咽頭・下咽頭の3つに分けられます。上咽頭とは鼻の奥の部分のことで、中咽頭とは口の奥のあたりのことです。そして、下咽頭とは食道の入口部分のことをいいます。咽頭がんは、これらの咽頭全てで発症することがある病気です。
咽頭がんの初期症状を教えてください。
また、上咽頭・中咽頭・下咽頭のどの部位にがんができるかによっても、初期症状が少し異なります。上咽頭がんの場合の比較的初期に見られる症状は、首のしこりです。これは頸部リンパ節に転移したことで感じられるケースがあります。
また、中咽頭がんや下咽頭がんの場合には、のどの違和感を覚えることもあります。飲み込む際に、詰まるような違和感を感じるのです。しかし、これらの初期症状も人によっては非常に些細な違和感です。そのため、気づくのが遅れることも少なくありません。
咽頭がんになるとどんな症状がでるのでしょうか?
- 鼻の異常
- 耳の異常
- 口の異常
- 脳神経の症状
- のどや首のしこり
- 声の変化
鼻の異常としては、鼻づまり・鼻血・鼻水へ血が混ざるなどの症状です。耳の異常としては、耳が詰まるような違和感・聞こえにくい・耳の痛みなどが挙げられます。口の異常とは、口を大きく開けにくい・舌を動かしにくいなどの症状です。
脳神経の症状としては、目が見えにくい、二重に見えるなどの症状があります。さらに悪化すると、のどや首のしこりを大きく感じるようになり、声の変化も現れることがあります。上咽頭・中咽頭・下咽頭のどの部位にがんができるかによっても症状の違いはありますが、さまざまな箇所に異変をきたす可能性があるのです。
咽頭がんになる原因を教えてください。
また、その他の原因としてはEBウイルスが関連するといわれており、特に上咽頭がんの発生原因となっています。中咽頭がんは、喫煙と飲酒以外にもHPVウイルスの感染が原因となって起こる場合があるため注意が必要です。
咽頭がんになりやすい人はどんな人でしょうか?
咽頭がんの検査方法と治療法

咽頭がんの検査方法を教えてください。
- 触診
- 後鼻鏡検査・耳鏡検査
- 喉頭鏡検査・間接喉頭鏡検査
- 内視鏡検査
- 生検
- 画像検査
- 超音波検査
- PET検査
触診は、リンパ節の転移などを確認する方法です。咽頭がんは、リンパ節への転移を起こしやすい特徴があるため、これを利用して検査を行います。後鼻鏡検査・耳鏡検査とは、鼻や耳に現れる症状を確認する方法です。鼻や耳に専用の器具を入れて、鼻・のど・耳の奥の様子を確認します。特に上咽頭がんの検査の際に用いる方法です。
喉頭鏡検査、間接喉頭鏡検査とは、鏡の付いた器具を口から入れて鼻やのどの奥を確認する方法です。中咽頭がんや下咽頭がんの検査に用います。内視鏡検査は、麻酔をしたうえで口や鼻から内視鏡を入れて咽頭を確認する方法です。食道がんや胃がんなど、他のがんを合併していないかも調べます。
生検とは、内視鏡検査を行うと同時にがんの一部を採取して、顕微鏡で詳しく観察する方法です。画像検査には、CT検査・MRI検査があります。
超音波検査では、首の表面から超音波を当ててリンパ節への転移などがないかを確認します。PET検査は、がんの全身への広がりを調べる方法です。画像検査ではわかりにくい、他の臓器への転移などを調べます。
咽頭がんのステージについて教えてください。
しかしステージⅡとなると、がんが咽頭だけでなく外側へ広がっている状態となります。この状態になると、リンパ節転移を認める場合もあります。
ステージⅢになると、頭蓋底・頸椎・副鼻腔などにがんが広がっている状態です。ステージⅣになると、頭蓋内や脳神経などに転移し、最悪の場合は肺や肝臓などの離れた臓器にも転移している可能性があります。
咽頭がんはステージによって治療法が異なるのでしょうか?
中咽頭がんの場合は、ステージⅠなどの初期段階であれば内視鏡治療によってがんを切除します。また、リンパ節への転移がある場合には、手術・放射線治療・科学放射線療法などを選択的に行う流れです。
ステージⅢやステージⅣの場合には、手術と科学放射線療法を行います。下咽頭がんの場合は、ステージⅠやステージⅡでは手術・科学放射線療法・放射線治療を行います。しかし、ステージⅢやステージⅣの場合は、手術などを実施する前に導入化学療法を行うケースもあるでしょう。
咽頭がんの治療による副作用について教えてください。
3ヶ月程度すると症状は改善してきますが、唾液が出にくい状態であるため、咽頭の乾燥や味がわからないなどの副作用は継続する可能性があります。
また、治療終了後半年経過した後でも、副作用が現れる可能性があります。内容としては、中耳炎・開口障害・虫歯の増加などが代表的です。化学療法の場合でも、副作用が現れる可能性があります。主な症状としては、嘔気・食欲不振・手足のしびれ・末梢神経症状・脱毛などです。
咽頭がんの予防法と治療後の注意点

咽頭がんの予防法を教えてください。
咽頭がんの治療を受けた後はどんなことに気を付けたらいいのでしょうか?
咽頭がんの治療後の経過について教えてください。
しかし、経過観察は非常に重要であるため、再発の際の早期発見のためにも治療後5年は通院して定期的な検査を受ける必要があります。検査方法は、その時の状態によって異なりますが、触診・内視鏡検査・画像検査などが必要となるでしょう。
最後に、読者へメッセージをお願いします。
そして、万が一のどの異変を感じた場合には、専門の医療機関に相談して早期受診、早期治療を進めましょう。
また、近年胃カメラで発見されることが多くなっています。
編集部まとめ

咽頭がんは、誰しも発症する可能性のある病気です。症状を自覚することが少ないことから、発見が遅れるケースも少なくありません。
発見が遅れた場合には、リンパ節や他の臓器などに転移する可能性があるため注意が必要です。また、治療を行った後も注意を怠ってはいけません。
再発のリスクや、治療の副作用などが現れるためです。早期改善や治療のリスクを下げるためにも、早期発見が重要です。
異変を感じた場合の受診はもちろんですが、定期的な検査を受けて、早期発見できる状態にしておきましょう。