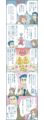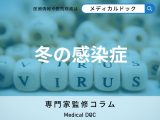監修医師:
林 良典(医師)
名古屋市立大学
【経歴】
東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科、NTT東日本関東病院予防医学センター・総合診療科を経て現職。
【資格】
医学博士、公認心理師、総合診療特任指導医、総合内科専門医、老年科専門医、認知症専門医・指導医、在宅医療連合学会専門医、禁煙サポーター
【診療科目】
総合診療科、老年科、感染症、緩和医療、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、眼科、循環器内科、脳神経内科、精神科、膠原病内科
目次 -INDEX-
野兎病の概要
野兎病(やとびょう、ツラレミア)は、野兎病菌Francisella tularensisを原因とする人獣共通感染症です。
ヒトやノウサギ(野兎)、プレーリードッグ、野生齧歯類から人間に感染します。 感染症法における四類感染症に指定されているほか、家畜伝染病予防法における届出伝染病にも指定されており、対象家畜はウマ、ヒツジ、ブタ、イノシシ、ウサギです。稀な感染症ながら、ごく少量の菌からでも病気を引き起こすほど感染力が強いことが知られています。
人間が感染する経路は、感染した動物と直接接触する、感染した昆虫(ダニやハエ)に刺される、細菌を含んでチリやホコリを吸い込む、汚染された食品や水を摂取する、などです。
野兎病の症状は、感染経路によって大きく異なることがあります。身体のさまざまな部位に影響を及ぼし、多様な症状を引き起こすため注意が必要です。この病気は稀ではありますが、特に農村部では公衆衛生上の課題となっています。野兎病には、感染経路と症状によっていくつかの型があり、潰瘍リンパ節型、眼リンパ節型、口腔咽頭型、肺型、腸チフス型に分けられます。それぞれの型には特有の症状があり、治療方法も異なります。
野兎病の原因
野兎病の主な原因は、感染力が強い細菌 Francisella tularensis(フランシセラ・ツラレンシス)です。この細菌にはいくつかの亜種があり、地域によって病原性や感染しやすさが異なることがあります。野兎病の主な原因には、以下のようなものがあります。
1. 昆虫に刺される
野兎病は、感染したダニやシカアブに刺されることで最もよく感染します。これらの昆虫は草地や森林など、感染動物が生息する場所でよく見られます。
2. 感染した動物との直接接触
感染した動物の皮膚、毛皮、肉に触れることで感染することがあります。特に、狩猟や動物を扱う仕事に従事する人が感染しやすいです。
3. 吸入による感染
細菌を含むちりや粉じんを吸い込むことで感染することもあります。たとえば、庭仕事や建設作業で汚染された土やほこりを吸い込むことが原因となる場合があります。
4. 経口摂取
感染した動物の肉を十分に加熱せずに食べたり、汚染された水を飲んだりすると感染することがあります。
5. 実験室での曝露
実験室でこの細菌を扱う際に適切な安全対策が取られていないと、感染のリスクがあります。
野兎病の前兆や初期症状について
野兎病の症状はペストに似ていると言われることがあり、特に感染初期には症状に特徴がないため早期に診断することは困難です。感染後3日~14日以内に現れることが多く、感染経路により初期症状が大きく異なります。大きくリンパ節腫脹の有無でタイプが分かれ、更にそれぞれ複数のサブタイプが知られています。日本では90%以上がリンパ節腫脹があるタイプで、60%がリンパ節型です。
リンパ節腫脹があるタイプ
1. リンパ節型野兎病
突然の発熱(38~40℃)、悪寒・戦慄、頭痛、筋肉痛、関節痛といった感冒様症状とともに、感染部位に近いリンパ節が腫れます。
2. 潰瘍リンパ節型野兎病
感冒様症状に加えて、感染箇所(刺された場所など)の皮膚に潰瘍を起こします。またリンパ節が腫脹したり潰瘍を形成します。
3. 眼リンパ節型野兎病
目に感染する型で、次のような症状が現れます。
- 片目の痛みと腫れ
- 目の充血と分泌物
- 光に対する過敏反応
- 耳や顎周辺のリンパ節の腫れ
4. 扁桃リンパ節型野兎病
汚染された食品や水を摂取することで発症し、次の症状が見られます。
- 喉の痛み
- 扁桃腺の腫れ
- 口内のただれ
- 吐き気や嘔吐
リンパ節腫脹がないタイプ
5. 肺型野兎病
細菌を吸い込むことで発症する重症の型で、次の呼吸器症状が現れます。
- 乾いた咳
- 胸の痛み
- 呼吸困難
- 発熱
6. 腸チフス型野兎病
稀ではありますが、全身的な症状を引き起こす型で、次のような症状があります。
- 高熱
- 強い倦怠感
- 腹痛
- 下痢
これらの症状が現れた際は一般内科または感染症科を受診しましょう。
野兎病の検査・診断
野兎病は、ほかの病気と症状が似ているため、診断が難しいことがあります。医師は通常、以下の手順で診断を行います。
1. 病歴の確認
最近の活動や、感染の可能性がある状況(昆虫に刺された、動物と接触したなど)について詳しく尋ねられます。
2. 身体検査
皮膚の潰瘍、腫れたリンパ節、呼吸困難など、前述の症状が見られるか確認します。
3. 抗体測定
野兎病に対する抗体を発症から2週間以降に採血で検出します。ELISA法やウェスタンブロットなどの手法も行われます。
4. 培養検査
野兎病は培養が難しいため、リンパ節の膿汁をマウスに接種して発症を確認する検査を行うことがあります。近年はPCR法によって野兎病の細胞成分遺伝子を検出する方法が可能となっています。
5. 画像検査
肺炎が疑われる場合、肺に細菌が感染しているか確認するために胸部X線検査を行います。
6. 鑑別診断
野兎病と、類似した症状を引き起こすほかの病気(ライム病や他の動物由来感染症)を区別することが重要です。
早期診断ができれば、迅速な治療が可能になり、野兎病の放置による合併症を減らすことができます。
野兎病の治療
野兎病は細菌感染症のため、主に抗生物質を使って治療します。
1. 抗生物質治療
- 一般的に、アミノグリコシド系またはテトラサイクリン系の抗生物質が有効です。
- 治療期間は、感染の型や重症度に応じて通常10日~2週間程度です。
2. 補助的な治療
- 腫脹したリンパ節に針を刺して排膿することもあります。
- 進行した肺炎や髄膜炎(脳と脊髄を覆う膜の炎症)などの合併症がある場合は、補助的な治療が必要になることもあります。
適切な抗生物質治療を受ければ、多くの人が野兎病から完全に回復しますが、疲労感などが残る場合もあります。
野兎病になりやすい人・予防の方法
野兎病になりやすい人
野兎病は、職業や活動内容により感染リスクが高まることがあります。
1. 職業リスク
- 獣医師や動物取扱者は、感染した動物と密接に接触する機会が多く、感染リスクが高くなります。
- フランシセラ・ツラレンシスを扱う実験室の作業者は、安全対策を厳重に守る必要があります。
- 農業従事者、造園業者、狩猟者、野生動物管理者などのアウトドア作業者も感染リスクが高まります。
2. 地理的リスク
中部アメリカなどの野生動物が多く生息する地域に住む人は、感染リスクが高いです。
3. 一般市民のリスク
暖かい季節にガーデニングやハイキングなどのアウトドア活動をする人も、昆虫の刺咬による感染リスクがあります。
予防の方法
野兎病の感染リスクを減らすために、次のような予防策が有効です。
1. 昆虫刺咬を避ける
屋外では、DEET(ディート)を含む虫除けを使用する。
ダニやアブが多い場所では、長袖や長ズボンを着用する。
2. 動物を安全に取り扱う
病気の動物や死んでいる動物を扱う際は、手袋を着用する。
具合の悪そうな野生動物には触らない。
3. 食の安全
野生の肉は十分に加熱してから食べる。
自然の水源からの水は飲まない。
4. 周囲の環境に注意を払う
土を掘り起こすときなどは、細菌が含まれている可能性を考慮する。
5. 教育と情報の理解
地域の感染拡大情報を把握し、リスクのある野生動物について知識を持つことも大切です。
これらの予防策を実行し、早期の症状を認識することで、野兎病感染のリスクを大幅に減らし、必要な場合は迅速に医療機関での診察を受けることが可能です。
関連する病気
- 鼠径部リンパ節炎
- 感染性心内膜炎