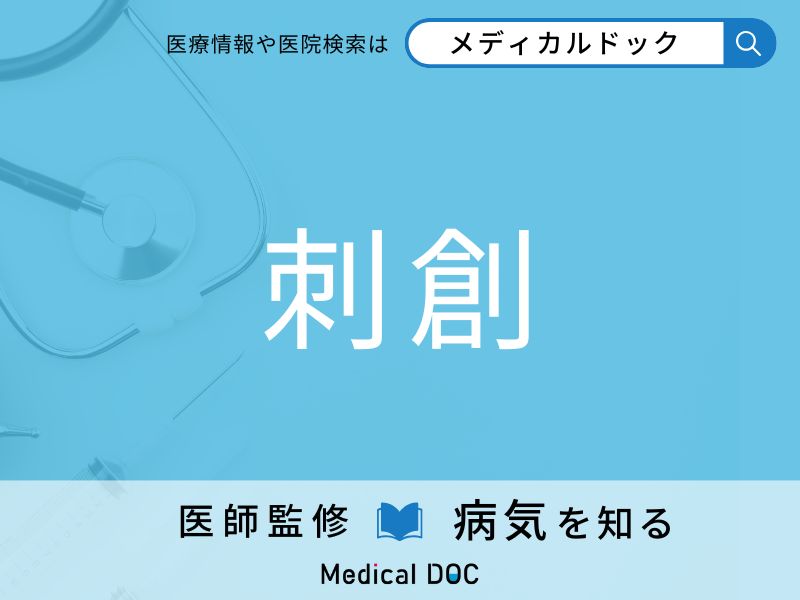

監修医師:
高宮 新之介(医師)
目次 -INDEX-
刺創の概要
刺創とは、先端の尖った鋭利な器具などによって皮膚や組織が突き刺されて生じる外傷のことです。
包丁やナイフ、針、釘、アイスピック、木の枝、鉛筆など、鋭い先端を持つものが刺さったときにできる傷を指します。傷口が小さくても奥まで達しやすいという特徴があり、深部で血管や神経、重要な臓器を損傷する恐れがあります。たとえ表面上は小さな傷に見えても、内部には深いダメージを負っている可能性があるため、注意が必要です。刺さった器具の一部が折れたり、さび・土砂などの汚れが含まれたりする場合には、体内に異物が残るリスクや感染症などの合併症が高まります。
刺創の原因
刺創は日常生活から職場環境、災害現場、事故など幅広い場面で起こる可能性があります。以下に主な原因を挙げます。
家庭内での事故
調理中に包丁やフォークなどを扱うときに発生することがあります。落とした刃物を素手で受け止めようとして、手を刺してしまうケースもめずらしくありません。ガラスの破片や工作用の釘なども原因になります。
職場での事故
鋭利な工具や金属片を扱う建設現場や工場などでは、誤って身体を刺してしまう事故が考えられます。また、医療従事者が注射針などで自分を刺してしまう針刺し事故も含まれます。
屋外での転倒・事故
野外活動中に木の枝を踏んで足裏を刺す、DIY作業で釘やビスを踏む、などの事故が挙げられます。災害時にはガラス片や倒壊した建材による刺創がみられることもあります。
暴力・犯罪
刃物や凶器による刺傷事件も、刺創の原因の一つです。
刺創の前兆や初期症状について
刺創は突発的に起こることがほとんどですが、その直後や数日後に生じる症状が初期段階での重要なサインとなります。主な症状と対処の目安を示します。
疼痛や違和感
刺された部位に痛みを感じたり、内側に何かがある違和感を覚えたりすることがあります。浅い傷でも痛みが軽減しない場合は、異物や深部へのダメージが残っている可能性があります。
出血
表面に見える血液量が少なくても、内部で出血している場合もあります。時間がたつにつれ血腫が大きくなると、腫れや皮膚変色が進むことがあります。
発赤や腫脹
刺し傷から細菌が侵入すると、患部が赤くなり腫れる場合があります。これは炎症反応であり、経過を観察しつつ症状が強くなるようなら受診がすすめられます。
しびれや動かしにくさ
神経や腱、筋肉が傷ついている場合、しびれや可動域の低下が起こる可能性があります。手足を刺した場合には特に気をつけましょう。
破傷風などの感染症初期症状
破傷風では顎のこわばりや筋肉の強いけいれんが起こることがあります。傷口の汚染状況に応じて注意してください。
どの診療科目を受診すればよいか
浅い刺し傷であれば、傷の様子を見ながら近隣の外科や整形外科を受診するケースもあります。ただし、形成外科では皮膚や軟部組織の専門的な治療を行うことが多いため、深い刺創や異物が残っているかもしれない傷などは形成外科が向いています。手足の腱や神経、骨への損傷が疑われる場合は整形外科への受診も検討されます。万が一、大量出血や強い痛み、意識障害などがあるときは迷わず救急外来を受診してください。
刺創の検査・診断
刺創の検査・診断は、傷の深さや異物の有無を詳細に調べることが中心です。具体的には以下のような方法が行われます。
問診と視診
いつ、どのような物が刺さったのか、受傷後の症状、出血量、破片の残留が疑われるかなど、詳しい状況を確認します。視診では傷口の大きさや汚染の有無、腫れや皮膚の変色などを観察します。
触診と神経・血管の評価
指先や医療用器具で触れて痛みやしびれの範囲を調べます。大きな血管損傷があると脈拍に異常が出るため、脈拍の触知や末梢循環の状態を確認する場合があります。
画像検査
レントゲン
金属片やガラス片など異物の種類によっては、残留物を見つけやすい検査です。骨や関節付近への損傷や骨折も判別しやすいとされています。
CTやMRI
深部に及ぶ傷や、木片などレントゲンに写りにくい異物を確認するのに使われます。
超音波検査
軟部組織内の液体貯留や、表層付近の異物探査に使われます。
神経機能検査
細いフィラメントなどを使って皮膚感覚や知覚の有無を調べます。腱や筋肉の動きなども合わせて確認し、機能障害の程度を判断します。
これらの検査を総合して診断し、必要に応じて治療方針を決定します。1種類の検査のみでは異物が見つからない場合もあるため、複数の検査を組み合わせることが多いです。
刺創の治療
刺創の治療は、感染リスクの把握と異物除去が大きなポイントになります。症状や傷の深さに応じて、以下のような治療が行われます。
洗浄と消毒
浅い傷で、刺さったものが抜けて汚染が少ない場合は、傷口周囲をきれいに洗浄して消毒します。ただし、深い傷をむやみに水道水などで洗浄しすぎると菌が広がる可能性があるため、傷口表面をそっと洗う程度でとどめるほうが望ましい場合もあります。
傷口の開放管理
刺創は感染が起こりやすいため、縫合を急がずに開放したまま管理することがあります。特に土などで汚染された傷は、創内に細菌が残っているおそれがあるため、しばらくは消毒や軟膏処置で様子を見ます。
深い刺創や異物除去
深い刺創の場合や異物が残存していると考えられる場合は、形成外科や整形外科での処置が必要です。異物を確実に取り除くために傷口を拡大し、可視化しながら摘出手術を行うこともあります。木片などレントゲンに映りにくい異物は見逃されやすく、再発性の感染を起こすことがあるため注意します。
破傷風予防
土やさびた金属による刺創の場合、破傷風トキソイド注射が検討されます。過去の予防接種歴によっては再接種や、免疫グロブリン投与を行うケースもあります。
抗生物質投与
感染が疑われる場合や感染リスクが高い場合、飲み薬や点滴で抗生物質が処方されます。傷の状況に応じて投与期間や種類が変わります。
筋・腱・神経の修復
深い刺傷で筋肉や腱、神経が断裂した場合、手術で縫合します。ただし感染が強いときに無理に縫合すると、化膿のリスクが高まることから、まず感染を抑えてから縫合する方針がとられる場合もあります。
このように、刺創の治療は傷の深さや汚染状況、組織の損傷範囲などを総合的に判断して進められます。急激な症状の悪化が見られる場合には早急な医療対応が重要です。
刺創になりやすい人・予防の方法
刺創は誰もが起こす可能性がありますが、特定の環境や行動、職業ではリスクが高いと考えられます。また、予防対策を意識することで、受傷を避けたり重症化を防いだりできる可能性があります。
刺創になりやすい人
鋭利な工具を扱う作業現場に従事している人
建設現場や工場などで金属片やガラス片を扱う機会がある人は、刺創のリスクが高まる傾向にあります。保護具(手袋や靴など)の着用を徹底することが大切です。
調理現場など刃物を頻繁に使う人
プロの料理人や料理が趣味の人などは、包丁などを扱う機会が多いため手指への刺創が起こりやすいです。刃物の取り扱いには十分注意してください。
医療従事者
注射針やメスなど鋭利な器具を扱うことから、針刺し事故など刺創を負う可能性があります。針捨て容器の使用や、廃棄手順の順守などが推奨されています。
予防の方法
保護具の着用
作業用手袋や安全靴などを装着することで、刺創のリスクを下げることができます。特に土木や建築、農作業などでは、安全性の高い素材の手袋を選ぶことが推奨されます。
作業環境の整備
足元の見やすさや作業スペースの安全対策など、整理整頓された環境は受傷リスクを下げます。ガラス片や金属片が落ちている場合は速やかに処分しましょう。
適切な刃物管理
包丁などを使用したあとは、決められた場所に置いておく習慣をつけます。刃先がむき出しのまま放置すると、他人が誤って触れて刺創を負う危険性があります。
破傷風ワクチンの定期接種
とくに土壌やさびた金属を扱う機会が多い人は、破傷風の予防接種歴を確認して必要があれば追加接種を検討します。災害時や野外での活動が多い場合も意識するとよいでしょう。
刺創は一瞬の不注意や偶発的な事故で起こる場合があります。日常的な予防策に加え、万が一受傷したときの正しい対処方法を知っておくことも重要です。













