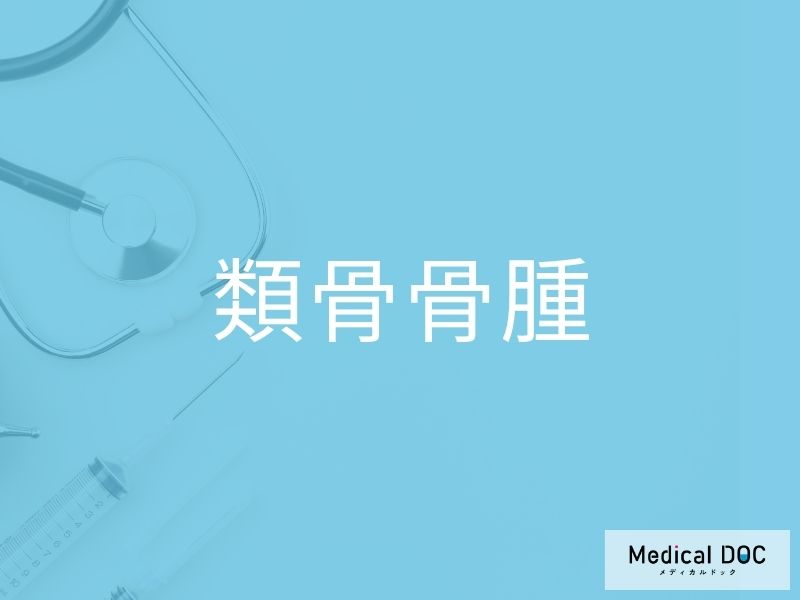

監修医師:
眞鍋 憲正(医師)
類骨骨腫の概要
類骨骨腫とは、骨や筋肉から発生する原発性良性腫瘍の一種です。腫瘍が悪性化する恐れはないと言われています。腫瘍は1.5cm程度と小さいものが多く、特別な治療をしなくても自然消滅することもあります。
20代以下の若年男性の長管骨(腕や太ももなどの長い骨)に発生することが多いことがわかっていますが、はっきりした原因は未だ解明されていません。
類骨骨腫の主な症状は痛みであり、とくに夜間に感じる痛みが特徴的です。痛みに対しては痛み止めの内服が効果的で、症状は徐々に緩和していくことが一般的です。しかし、まれに痛みがなくならないケースもあり、その場合は手術を検討します。
類骨骨腫の診断には画像検査が必須であり、とくにCTによる検査が有効です。ただし痛みの訴えのみであれば、最初はレントゲン検査を実施することが多く、腫瘍の発見が遅れるケースも少なくありません。
治療では身体への負担が小さいラジオ波による治療が有効です。しかし自然と消滅する可能性もあるため、日常生活に支障がないのであれば経過観察となることもあります。

類骨骨腫の原因
類骨骨腫を発症する明確な原因はわかっていません。
遺伝的な要因などが関与している可能性が示唆されていますが、現在のところ十分な科学的根拠はなく、さらなる研究が進められています。
類骨骨腫の前兆や初期症状について
類骨骨腫の主な症状は類骨骨腫周囲の痛みです。初期症状では痛みの増悪と寛解を繰り返し、夜間に痛みが出やすいという特徴があります。この痛みは徐々に強くなっていき、最終的には睡眠を阻害するほど強くなるケースもあります。
類骨骨腫の痛みの原因は、骨が膨らんだ部分の中心にあるナイダス(nidus)と呼ばれる組織が成長していくことだと考えられています。ナイダスは成長に伴いプロスタグランジンというホルモンを分泌し、プロスタグランジンによってナイダス周囲の組織が浮腫みます。
浮腫みによってその周囲が炎症と似たような状態になり、痛みにつながると考えられています。また、ナイダスの内部には神経が増殖することも知られており、その神経の増殖も痛みの原因になると考えられています。痛みのほかには発赤や腫脹といった炎症所見や、神経付近に類骨骨腫ができた場合には神経症状が出現することもあります。
類骨骨腫の検査・診断
類骨骨腫の診断には、はCT画像が用いられます。、CTでは類骨骨腫の特徴であるナイダスがはっきりと映し出されます。ナイダスを確認し、ほかの転移性骨腫瘍や骨芽細胞腫との鑑別ができると、類骨骨腫の確定診断となります。
しかし、類骨骨腫は単純性関節炎や骨髄炎との鑑別が難しく、痛みで来院してから確定診断まで時間がかかるケースが多々あります。関節の痛みで受診した際、通常最初はレントゲン撮影を行いますが、類骨骨腫の腫瘍組織は小さいため、レントゲン画像では見落とすことがあるためです。
また、MRI画像を撮影しても浮腫により感染や炎症と間違われることも多々あります。関節や骨の変形が認められないケースではCTを撮影しないケースも多いため、確定診断まで時間がかかりやすい疾患といえます。
類骨骨腫の治療
類骨骨腫の治療では、特徴的な夜間痛に対して痛み止めの薬(NSAIDs)を使用します。類骨骨腫は自然と消滅することも多い疾患なため、痛み止めで日常生活に支障がないのであれば経過観察となることが一般的です。
自然に消滅せず、痛みが持続する場合には手術の適応となります。手術では類骨骨腫の中心にあるナイダスを摘出しますが、を摘出しきれていない場合には再発の恐れがあるため注意が必要です。
また、近年ではCTを使用しながらラジオ波という特殊な高周波電磁波を利用した治療も実施しています。ラジオ波を発生させる針を患部に刺して、病変にラジオ波を当てる治療方法で、外科手術よりも傷跡が小さく身体への負担が小さいため、早期に社会復帰が可能な治療方法として着目されています。
しかし、ラジオ波による治療は類骨骨腫周囲の組織も焼いてしまう可能性があるため、神経や皮膚に近い類骨骨腫に対しては使用できません。その場合には外科的手術やMRIを使用した超音波での切除術が適応となります。
類骨骨腫になりやすい人・予防の方法
類骨骨腫は20歳以下の若年男性に発症しやすいことで知られていますが、原因はわかっていません。発症しやすい部位は長管骨と呼ばれる長い骨で、上腕骨(腕の骨)や大腿骨(太ももの骨)に発症するといわれています。しかし数は少ないものの、脊骨などにも発生する可能性は留意しなければいけません。
類骨骨腫は原因不明の良性腫瘍と考えられています。そのため、発症予防は困難です
多くのケースでは数年で腫瘍が自然消滅していきますが、まれに消滅せずに痛みが持続するケースもあります。そのようなケースでは手術が適応となるため、大きさの変化を定期的に検査する必要があります。
参考文献













