
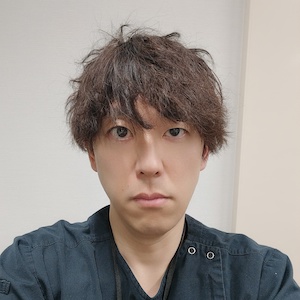
監修医師:
日浦 悠斗(医師)
目次 -INDEX-
特発性てんかんの概要
特発性てんかんは、原因が特定できないてんかんの一種です。脳に明らかな物理的(医学的には器質的という)異常がないにもかかわらず発作が繰り返し起こるのが特徴で、遺伝的な要因が関係していると考えられています。
人の体の細胞には電気的な流れがあり、脳の神経細胞も規則正しいリズムで活動しています。てんかん発作は、このリズムが突然乱れることで起こり「脳の電気的な嵐」と例えられることもあります。
てんかんのある人は100人に1人の割合でいると言われ、日本には約100万人いると推定されています。そのうち特発性てんかんは全体の約30%を占め、多くは小児期から思春期に発症します。
発作の型は大きく全般発作と部分発作に分けられます。全般発作は、発作が起こった時から脳全体が発作に巻き込まれる型で、代表的なものに「強直間代発作」(全身の筋肉が硬直して倒れる)と「欠神発作」(短時間意識が途切れる)があります。
一方、部分発作は脳の一部から発作が始まる型で、体の一部が痙攣したり、既視感や光のようなものが見えるなどの特別な感覚を感じたりします。年齢によって見られやすい発作型が異なり、小児期では欠神発作が、思春期では強直間代発作が多く見られます。
特発性てんかんでは、発作以外の神経症状はなく、知能や運動機能の発達も正常です。多くの場合、適切な治療により発作をコントロールすることが可能で、約70%の患者さんで薬物治療が有効です。
ただし、思春期のホルモンの変化や、睡眠不足、ストレスなどにより、一時的に発作が増えることもあるため、継続的な管理が必要です。

特発性てんかんの原因
特発性てんかんの原因は、完全には解明されておらず、MRIや血液検査などを行っても異常は見つけられません。てんかん発作以外の神経症状がなく、知能や運動機能の発達も正常です。
ただし、脳にてんかん発作を起こしやすい素因があることが分かっています。遺伝子研究の進歩により、一部の特発性てんかんでは原因となる遺伝子が特定されているため、遺伝的な要因が関係していることが明らかになってきています。
特発性てんかんの前兆や初期症状について
特発性てんかんでは、発作の型によって症状が大きく異なります。また、発作の前にめまいや手足のしびれなどの前兆症状を感じる人もいれば、突然発作が起きる場合もあります。
特発性全般てんかん
脳の広い範囲で電気的な興奮が生じるてんかんです。主な発作型として「強直間代発作」と「欠神発作」の2つがあります。
強直間代発作は、突然意識を失い、全身の筋肉が硬くなった後、全身が痙攣する発作です。数分で自然に回復しますが、発作後はしばらくもうろうとした状態が続くことがあります。発作中に舌を噛んだり、尿失禁したりすることもあります。思春期以降に多く見られます。
一方、欠神発作は主に小児期に多く見られ、数秒から数十秒の短い意識消失が特徴です。突然動作が止まり、目を開いたままボーっとした状態になります。周囲からは「ぼんやりしている」ように見えますが、本人は発作を自覚していないことが多く、発作が終わると直前の動作を続けます。
特発性部分てんかん
脳の一部分から発作が始まるのが特徴です。意識が保たれたまま発作が起こる場合と意識が障害される場合があります。
症状は発作が起こっている脳の部位によって異なり、体の一部が痙攣したり、においや味を感じたり、普段と違う感覚を覚えたりします。意識が保たれている場合は、発作中も周囲の状況が分かり、後で状況を説明できます。一方、意識が障害される場合は、周囲の状況が分からなくなり、その間の記憶もなくなります。
また、部分発作が全身に広がり、全般発作である強直間代発作に移行することもあります。
発作の頻度は人によって大きく異なり、1日に何度も起こる人もいれば、数ヶ月に1回程度の人もいます。
特発性てんかんの検査・診断
特発性てんかんは、さまざまな検査を行っても原因が特定できない場合に診断されます。
問診
発作の様子や頻度、発症時期、家族歴などについて詳しく確認します。また、発作時の状況を把握するため、家族や友人などといった目撃者からの情報も必要です。とくに発作の前後の状態、発作時の意識状態、持続していた時間などを確認します。
脳波検査
脳波検査は診断の中心となる検査です。睡眠中の脳波がとくに重要で、てんかんをもつ患者には特徴的な波形があらわれることがあります。また、光刺激や深呼吸を行い、異常な波が誘発されるかどうかも確認します。
画像検査
MRIやCTなどの画像検査を行います。腫瘍や血管の異常、外傷後の変化など、他の原因がないことを確認するために行われます。
血液検査
血液検査も同様に、他の病気がないことを確認するために行われます。電解質バランスの異常、血糖値の異常、感染症、代謝性疾患などの検査が行われます。治療開始後は、抗てんかん薬の血中濃度を測定することで、投薬量の調整にも役立ちます。
特発性てんかんの治療
治療の中心となるのは抗てんかん薬による治療です。薬は通常、1種類から開始します。代表的なものとしては、バルプロ酸や、カルバマゼピン、レベチラセタムなどの各種の抗てんかん薬が使われます。
最初の薬で効果が不十分な場合や副作用が強く出る場合は、他の薬に切り替えたり、複数の薬を組み合わせたりすることがあります。ただし、むやみに薬を増やすことは避け、必要最小限の薬で最大の効果が得られるよう調整します。
また、定期的な血液検査で薬剤の血中濃度を確認し、副作用の早期発見にも努めます。副作用には、眠気、めまい、吐き気などの比較的軽いものから、重篤な皮膚症状や血液障害までさまざまな可能性があります。
特発性てんかんになりやすい人・予防の方法
特発性てんかんは、家族歴のある人で発症する可能性が高くなりますが、遺伝的な要因がどの程度関係しているのかは、まだ完全には解明されていません。また、家族歴があっても必ずしも発症するわけではありません。
発作を完全に予防することは難しいですが、薬物治療を受けている場合は、服薬を継続することが発作予防の基本となります。自己判断での服薬中止や用量の変更は発作を引き起こす危険があるため、必ず医師の指導のもとで行いましょう。
日常生活では、発作による事故を防ぐための注意が必要です。入浴は家族が近くにいるときに行い、高所での作業は避けましょう。
関連する病気
- 若年ミオクロニーてんかん
- 小児欠神てんかん
- 若年欠神てんかん
- 良性ローランドてんかん
- 良性後頭葉てんかん
- 熱性けいれん
- 思春期ミオクロニーてんかん
- 良性家族性新生児けいれん
- 良性乳児てんかん
- 光過敏性てんかん
- 家族性側頭葉てんかん
- 乳児ミオクロニーてんかん
- レノックス・ガストー症候群
- ウェスト症候群
- 遅発性小児後頭葉てんかん
- 進行性ミオクローヌスてんかん
参考文献













