
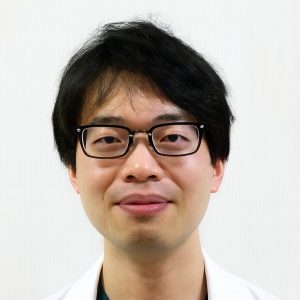
監修医師:
栗原 大智(医師)
目次 -INDEX-
開放隅角緑内障の概要
開放隅角緑内障は目の中にある「房水(ぼうすい)」という液体の流れが悪くなり「眼圧」が上昇し、視神経がダメージを受ける病気です。初期には自覚症状がないケースが多いのですが、放置すると神経が徐々に傷み、視野が欠ける恐れがあります。
緑内障には、今回説明する開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障の2種類に分けられます。両者の違いは、以下のとおりです。
| 開放隅角緑内障 | 閉塞隅角緑内障 | |
|---|---|---|
| 房水の出口 (隅角) |
広く開いている | 閉じているもしくは狭い |
原発開放隅角緑内障
原発開放隅角緑内障とは、先天異常やほかの病気など、特定の原因がないのに発症する緑内障のことです。眼圧が統計的な正常範囲内(日本では20 mmHg以下)を超えており、眼圧の上昇が神経の損傷に関わるとされています。
しかし、眼圧は季節や時間によって変動するため、測定するタイミングによっては眼圧が正常値に収まるケースもあります。
正常眼圧緑内障
正常眼圧緑内障は、眼圧が統計的な正常範囲内であるにもかかわらず、視神経に損傷が生じるタイプの開放隅角緑内障です。日本人の多くはこの正常眼圧緑内障です。
続発開放隅角緑内障
続発緑内障とは、ほかの眼科疾患や全身疾患、薬の使用が原因となり眼圧が上がるタイプの緑内障です。眼圧を上げる要因の例は、以下のとおりです。
- 長期的な副腎皮質ステロイドの使用
- ぶどう膜炎や異色性虹彩毛様体炎
- 眼科手術後の炎症
- 眼内の腫瘍や異物
若年開放隅角緑内障
若年開放隅角緑内障は、小児緑内障の一種です。発症タイミングは4歳以上とやや遅く、先天性の眼形成異常や全身疾患などはないのが特徴です。
開放隅角緑内障の原因
開放隅角緑内障の原因は、眼内の房水の流れが悪くなり、視神経に圧力がかかることです。
房水とは、眼球の中を満たす水分です。目の中にある水晶体や角膜に栄養を与え、眼球の形を保つ役割をしています。
通常であれば、房水は目の中の「毛様体」と呼ばれる部分で作られ、「隅角」という部分を通って血管内に流れていきます。しかし開放隅角緑内障になると、房水の出口が開いているにもかかわらず、眼圧が上昇します。
眼圧が高い状態が続くと、視神経が圧迫されてダメージを受けます。その結果、目からの情報が脳に伝わらなくなり、視野が欠けたり視力が下がったりするのです。
開放隅角緑内障の前兆や初期症状について
開放隅角緑内障は、初期段階ではほとんど症状が現れません。視野が一部欠けていても気づかず、気づいたときにはかなり症状が進行しているケースも珍しくありません。
もし「以前よりも見にくい気がする」「特定の一部だけ視野が欠けている気がする」などを感じた場合は、速やかに眼科を受診しましょう。
開放隅角緑内障の検査・診断
開放隅角緑内障の診断には、以下のような検査が行われます。
視力検査・屈折検査
視力の低下があるか、そして、近視や遠視、乱視などを確認する
細隙灯顕微鏡検査
スリット状の光を目に当て、顕微鏡を使って目の表面や水晶体など、組織の状態を観察する
眼圧検査
眼に空気や直接機械を接触させて、眼圧が正常範囲を超えているかを確認する
隅角検査
専用のコンタクトレンズを眼の表面にあてて、房水の出口(隅角)の状態を確認する
視野検査
特定の場所に出た光が見えるかを片目ずつ確認し、視野の欠けの有無を調べる
眼底検査
眼底にある視神経の状態を直接見て、その緑内障の有無や進行の程度を調べる
角膜厚測定
角膜の厚さを測定し、緑内障のリスクを評価する
複数の検査結果をもとに、緑内障のうちどの病態(開放隅角/閉塞隅角)なのか、どの程度症状が進行しているかなどを眼科医が判断します。
開放隅角緑内障の治療
開放隅角緑内障の基本的な治療は、眼圧を下げてこれ以上の視神経へのダメージを防ぐことです。
一度失われた視野は、現在の技術では回復が難しいとされています。そのため、眼圧を下げることで視神経へのダメージを防ぎ、視野の欠損や、それに伴う生活の質の低下を防ぐことが大切です。また、眼圧が正常な「正常眼圧緑内障」も、眼圧を下げると病気の進行抑制が期待できます。
具体的な治療法を、いくつか紹介します。
薬物療法
基本的な治療法で、眼圧を下げる目薬を使用する
レーザー治療
房水の排出を良くする治療(効果があるのは、一部の開放隅角緑内障のみ)
手術療法
薬物療法やレーザー治療の効果が不十分なときに行われる
また、病気やケガが原因となる「続発開放隅角緑内障」の場合は、眼圧が上がる原因を治療することで、緑内障の進行が抑えられるケースもあります。
開放隅角緑内障の治療に使われるおもな目薬
開放隅角緑内障では、眼圧を下げる目薬が一般的に使われます。
代表的な目薬と、特徴を以下にまとめました。
(表はスクロールできます)
| 主にどうやって 眼圧を下げるか |
成分の例 | 薬の特徴・注意点 | |
|---|---|---|---|
| FP受容体作動薬 | 房水の排出を促進する |
|
|
| EP2 受容体作動薬 | 房水の排出を促進する |
|
|
| β遮断薬 | 房水の産生を抑える |
|
|
| α1β遮断薬 | 房水の排出を促進する +房水の産生を抑える |
|
|
| α2作動薬 | 房水の排出を促進する +房水の産生を抑える |
|
|
| 炭酸脱水素阻害薬 | 房水の産生を抑える |
|
|
| ROCK阻害薬 | ROCK阻害薬 |
|
|
眼圧や持病の有無などにより、適する薬は異なります。また、効果が不十分だったり、視野の進行があったりすれば、複数の目薬を併用します。
近年は「配合剤」と呼ばれる複数の作用機序の薬を併せ持つ製品も発売されており、目薬のさし忘れによる眼圧上昇を防ぐのに役立てられています。配合剤を処方する際は、同じ作用機序の薬が重複しないよう、確認してから医師は処方を決定しています。
目薬を使用する際の注意点
眼圧を下げる目薬を使用する際は、以下の点に注意しましょう。
- 使用する前は手を洗い、清潔な手で目薬を使用する
- 目薬の先がまつ毛に触れないように注意する
- 1回1滴が目に入るよう、出しすぎに注意する
- 効果がしっかり得られるよう、点眼後は静かに目を閉じて目頭を軽く抑える
- かぶれや色素沈着を防ぐために、あふれた目薬はふき取る
- 複数の目薬を使う際は5分以上の時間をあけ、指示された順番を守る
副作用を減らす、目薬の効果を高めるなどのために必要な注意点です。しっかりと守るように心がけましょう。
開放隅角緑内障になりやすい人・予防の方法
緑内障は、年齢が上がるにつれてかかりやすくなります。40歳以上の日本人における緑内障の有病率は5%(20人に1人)という報告もあります。
また、強い近視の人や、家族に緑内障の患者さんがいる人などは、緑内障になりやすいとも言われています。
緑内障を完全に予防することは困難です。しかし、眼圧の高さや視野の欠けに早く気付ければ、進行を抑え、生活面での不便を減らすことはできます。
緑内障による生活の不便を最小限に抑えるために、定期的に眼科検診を受け、目で気になることは早めに相談するようにしましょう。
関連する病気
- 高眼圧症
- 視神経萎縮
- 糖尿病網膜症
















