
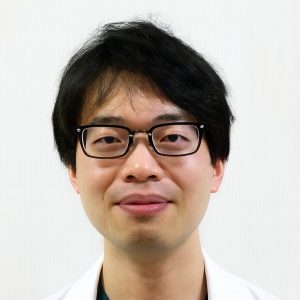
監修医師:
栗原 大智(医師)
目次 -INDEX-
網脈絡膜炎の概要
網脈絡膜炎(もうみゃくらくまくえん)は、眼球の後ろ側にある網膜と脈絡膜に炎症が生じる疾患です。後部ぶどう膜炎と呼ぶこともあります。眼球を包む膜は眼球側から網膜、脈絡膜、強膜の3層で構成されています。網脈絡膜炎は網膜と脈絡膜に炎症を起こす疾患の総称です。
網膜は眼球の水晶体から入った光を視神経に繋げる、大事な役目があります。炎症で網膜を傷つけられると視神経へ情報が送れなくなり、視力低下や失明など、重篤な症状をきたします。網脈絡膜炎は原因がとても多いため、早急に正しい診断を行うことが求められます。ただちに原因を究明し、早急な治療につなげることで患者さんの視力を守ります。
網脈絡膜炎の原因
網脈絡膜炎の原因はウイルス感染から自己免疫疾患まで、多岐にわたります。
感染性と非感染性に分けられ、感染性ではウイルス、細菌、真菌、原虫(寄生虫)など、さまざまな原因があります。
非感染性では自己免疫疾患が主な原因ですが、稀に薬の副作用に関連することがあります。網脈絡膜炎を放置すると白内障などが進行することもあります。
サイトメガロウイルス感染
ヘルペスウイルスの一種、サイトメガロウイルスの感染で網脈絡膜炎を起こすことがあります。HSV、VZVなど、ほかのヘルペスウイルスが原因となることもあります。
網脈絡膜炎などの後眼部の疾患は健康な人はほぼ発症しません。免疫抑制剤の使用やAIDSなど、免疫機構が著しく阻害されているときに発症すると言われています。
ただし、急性網膜壊死などの劇症は、免疫が正常な状態でも発症することがあります。
結核など細菌感染
結核菌など細菌感染で発症することがあります。(脈絡膜結核腫)
肺で増殖した結核菌が全身に広がり、脈絡膜で発症することがあります。結核菌の保菌者が加齢など、何らかの原因で免疫が低下したときに発症します。通常は片眼性です。
原虫(寄生虫)
トキソプラズマ原虫(トキソプラズマ性網脈絡膜炎)など、寄生虫が原因で発症することがあります。トキソプラズマ原虫はネコのフンに排出されることがあり、ネコのお世話をする人に感染リスクがあります。獣肉の生肉にも含まれているので、生の牛肉や鶏肉を食べる習慣があると感染することがあります。
自己免疫疾患
ベーチェット病、サルコイドーシスなどの自己免疫疾患の症状で現れることがあります。ベーチェット病は30代後半に多い傾向があり、眼症状は患者さんの約5割に現れます。治癒しても再発を繰り返します。両眼に症状が現れ、網脈絡膜炎や眼前部の虹彩、毛様体に炎症が発生します。
男性の発症リスクが高いのが特徴です。放置しても数日から14日ほどで回復しますが、早期に適切な治療を行うことで網膜を守り、視力を維持することができます。
サルコイドーシスは男性は若年者と女性は高齢者に多い疾患です。発症原因は不明で、ベーチェット病と同様の眼病を繰り返し発症することがあります。
網脈絡膜炎の前兆や初期症状について
初期症状は急激な視力の低下、目のかすみ、まぶしさ、視界の中央部の歪み、蚊のような黒い点が飛び回るように見える(飛蚊症)などです。
痛みは少ないですが、稀に急性網膜壊死に進行し、強い痛みに襲われることがあります。重症化すると視力の大幅な低下や、白内障を併発することがあります。軽症でも何度も発症すると、網膜にダメージが蓄積して、視力が低下したり、その部位の視野が欠けることがあります。
診断と治療のためには眼科を受診しましょう。特に自己免疫疾患の方は再発しやすい疾患です。定期的に検診を行い、眼底検査を受けることをおすすめします。自己免疫疾患が原因の場合は、前眼部の虹彩毛様体にも炎症を併発することがあります。
網脈絡膜炎の検査・診断
網脈絡膜炎は原因が多く、できるだけ早急に診断しなければなりません。
眼底検査や蛍光眼底造影、血液検査などの検査を行い、診断および原因検索を行います。
問診
原因が多い網脈絡膜炎は、病歴を探ることは大変重要です。
- ヘルペス感染の有無
- 結核と診断されたことがあるか
- 猫を飼っているか。野良猫などの猫に接することがあるか。獣肉の生肉を食べることがあるか。(トキソプラズマ感染)
- 自己免疫疾患の治療中か
- AIDSの発症、がん治療による免疫抑制剤などで、免疫機構が著しく低下していないか。
- 妊娠中か
これらの問診事項が診断につながることがあります。
眼底検査
眼底検査を行い、網膜の状態を確認します。特徴的な所見が見られるため、眼底検査で確定診断を行います。硝子体混濁、網膜血管炎、網膜動静脈閉塞症、網膜外層の点状病変、網膜滲出斑などを認めます。
PCR検査
ヘルペスウイルスを疑う場合は、前房水からPCR法によるDNA検出を行います。
網脈絡膜炎の治療
治療法は原因に応じて異なりますが、基本はステロイドを投与し、炎症を抑えます。
後眼部の炎症のため、ステロイド点眼では患部に届きにくいとされています。そのため、ステロイド後部テノン嚢下注射、ステロイド内服薬などを使用します。
症状が収まれば、ステロイドの量を徐々に減らす「減薬」期間に入ります。治療は長期戦になるため、患者さんの負担が少ないスケジュールを組む必要があります。
ぶどう膜炎を併発し、前眼部にも炎症がある場合は、ステロイド点眼薬を併用します。
感染性の場合、併せて抗菌薬や抗ウイルス薬、抗真菌薬、抗原虫薬など、原因に応じた治療薬を投与します。抗原虫薬は腎臓に負担がかかるため、腎機能障害など副作用が懸念されます。そのため、用法、用量に細心の注意が必要です。
ぶどう膜炎により白内障が進行した場合、無発作期間を6ヶ月以上あけてから、白内障手術を行うことがあります。
網脈絡膜炎になりやすい人・予防の方法
ベーチェット病など自己免疫疾患、妊娠中、AIDSなど後天的な免疫疾患、がん治療薬など、何らかの理由で免疫機構が著しく低下した方には発症リスクがあります。
一度でもサイトメガロウイルスの感染歴があると、症状が収まった後にも長期間体内に潜伏します。免疫機構が低下すると活性化し、網脈絡膜炎を発症することがあります。
特に、ベーチェット病の男性は悪化しやすいため、眼底の定期検診は欠かせません。繰り返し発症しても早期発見、早期治療で網膜のダメージを減らし、視力を守りましょう。
ネコと触れ合う機会が多い方、生の獣肉を食べる習慣がある方も注意が必要です。ネコのふんに含まれるトキソプラズマ原虫が口や目に入ることで感染し(接触感染)、トキソプラズマ性網脈絡膜炎を発症することがあります。牛肉、鶏肉、豚肉、羊肉など獣肉にも寄生していることがあるため、これらの肉を生焼け、生食することもリスクがあります。
一度でもトキソプラズマに寄生されると抗体がつき、再感染しにくくなります。しかし抗体がなければ高い確率で寄生されます。妊娠中など免疫機構が低下した方は猫のふんに触らない、汚染された土や草むらなどに入らない(触った後は、よく手を洗う)、獣肉の生肉を避け、きちんと加熱するなどで、感染リスクを下げることができます。
妊娠中にトキソプラズマに寄生されると、胎児にも寄生し、先天性トキソプラズマ性網脈絡膜炎を起こすことがあります。
関連する病気
- 全身性の免疫疾患
- 感染症による網脈絡膜炎
- 眼疾患
- 腫瘍
- 栄養不足













