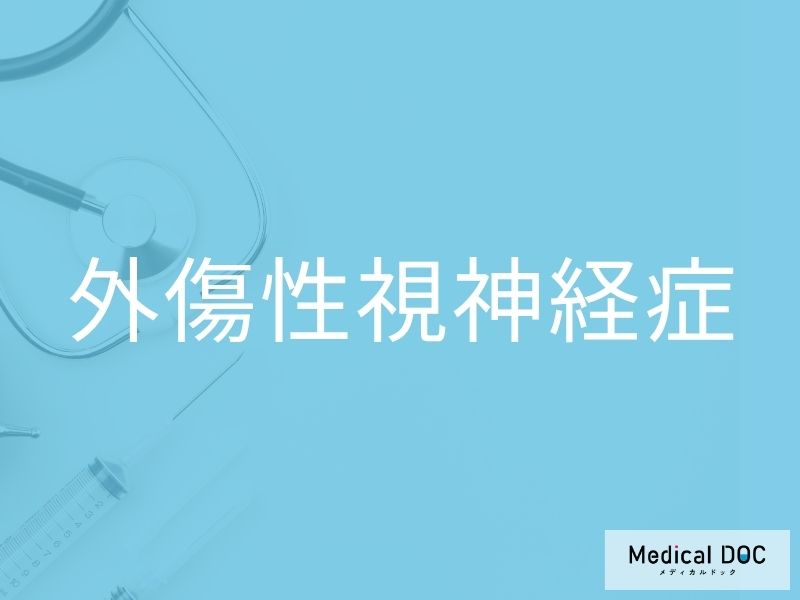

監修医師:
柳 靖雄(医師)
目次 -INDEX-
外傷性視神経症の概要
外傷性視神経症とは、眉毛の外側部分を強く打つことで急激に起こる視神経の損傷です。視神経の束が通る「視神経管」に衝撃が伝わることで、視力や視野に異常をきたします。
外傷性視神経症では、視神経管内の出血や浮腫により視神経が圧迫され、視力や視野に影響を及ぼします。そのまま放置すると視力低下につながるため、できる限り早期に治療を受けることが重要です。治療では視神経の圧迫を軽減する目的で、ステロイド投与や手術が行われます。
外傷性視神経症は、どの年代であっても発症することがありますが、若年から中年の男性に多くみられる傾向があります。転倒や事故をきっかけに起こるため、日頃から転倒予防や安全管理に気を配ることが大切です。

外傷性視神経症の原因
外傷性視神経症は、主に眉毛の外側部分に前方から衝撃を受けることで生じるケースが多いです。転倒や転落、交通事故などが受傷の主なきっかけとなります。
外力により、眼の周りの骨を介して、衝撃が視神経管まで伝わり、視神経管骨折が起こることもあります。これにより、管内にある視神経の断裂や損傷、出血が生じ、視力障害を引き起こします。
また骨折がなくても、視神経管にゆがみが生じることで、循環障害や浮腫が起こり、視力や視野の障害を引き起こします。
外傷性視神経症の前兆や初期症状について
外傷性視神経症の初期症状は、受傷後に急激に起こるのが特徴です。衝撃を受けた側と同じ側の目に障害があらわます。
症状の程度は、視神経管が受けた衝撃の強さによって異なります。
「視野が暗くなった」「目が見えにくくなった」と感じる程度の軽度の症状のこともあれば、光を感知できない(医学的失明状態)こともあります。眉毛の外側部分に傷があるケースでは、顔の損傷が軽度でも視力障害が強くなる傾向があります。
外傷性視神経症の検査・診断
外傷性視神経症の診断では、まず眉毛の外側部分に打撲があるかどうか、視力や視野に障害がないかを確認します。とくに外傷性視神経症を見分けるポイントとなるのが、受傷直後に急激な視力低下があるかどうかです。受傷から数日後に視力低下がみられる場合は、他の病気の可能性が疑われます。
外傷性視神経症についてさらに詳しく調べるには、瞳孔検査や眼底検査、眼窩CT検査が行われます。
瞳孔検査は、眼に光を当て瞳孔が縮小するかどうかを確認する検査です。外傷性視神経症になると、眼に光を当てても瞳孔の縮小が不十分であるか、全くみられません。
眼底検査は、瞳孔の奥にある眼底の血管や網膜、視神経を調べる検査です。外傷性視神経症では、受傷後7~10日程度経ったころに、視神経の束が眼球を突き抜ける部分である「視神経乳頭」が青白くなることがあります。
眼窩CT検査は、眼の内部構造や周りの骨について調べる検査です。場合によっては、視神経管の骨折が確認できないことがあります。
そのほか、外傷性視神経症の診断のために、特定の色を見分けられるかを調べる「色覚検査」、筒の内部の光の点滅が見えるかを調べる「中心フリッカー検査」、光を当てて瞳孔の変化をみる「イリスコーダー」などを行うことがあります。
外傷性視神経症の治療
外傷性視神経症の治療では、薬物療法や手術を行います。
治療は、あくまで出血や浮腫による視神経への圧迫を軽減するものであり、視神経の損傷そのものを改善することはできません。
薬物療法
薬物療法では、ステロイドの大量投与を3日程度行うことが一般的です。また視神経管内の浮腫に対して、眼圧降下剤を投与することもあります。受傷後の早期の薬物療法で改善がみられない場合は、手術が検討されます。ただし受傷後、すでに光を感知できない場合は、視力の改善が見込めないため、手術の適応になりません。
手術(視神経開放術)
視神経開放術は、視神経管を開いて一部の骨を除去し、視神経に対する圧迫を解除する手術です。外傷性視神経症に対する手術は、受傷後できれば1週間以内、遅くとも3週間内に行うことが推奨されています。これは受傷後2週間程経過すると、視神経の萎縮がみられ、受傷後1か月程では、視神経の損傷が元に戻らないためです。
手術のアプローチ法には、開頭して頭蓋骨からアプローチする方法と鼻からアプローチする方法があります。頭蓋骨からのアプローチは、眼の減圧を行いやすいですが、体への負担が大きく、脳の損傷リスクをともないます。鼻からのアプローチは、体への負担は小さいものの、眼の減圧を十分に行うことはできません。
外傷性視神経症の予後について
外傷性視神経症に対する薬物療法と手術では、視力の改善率に大きな差はありません。具体的な視力の改善率は、薬物療法が40~70%、手術が40~90%というデータがあります。
手術は合併症リスクがあることから、実施には賛否両論があります。一方で、受傷後に適切な治療を受けなければ、視力の改善率は20~30%と報告されてます。
外傷性視神経症は、受傷後早期に治療を受けることが重要です。治療を受けるのが遅れると、視神経管内の循環障害が悪化し、視力低下につながります。
外傷性視神経症そのものは、命に関わる病気ではありません。しかし、眼が持つ「見る機能」は日常生活を送るうえで欠かせないものです。QOL(生活の質)を維持するためにも、外傷性視神経症が疑われるときは、早めに医療機関を受診しましょう。早期に診断を受けて治療を開始することで、視力低下を抑えることが期待できます。
外傷性視神経症になりやすい人・予防の方法
外傷性視神経症の発症例で多いのが、20~40代の男性です。若年から中年でアクティブな男性は、額(眉毛の外側部分)に衝撃を受けるリスクがあり、外傷性視神経症の発症率も高くなります。
とくに転倒や交通事故、落下事故は、外傷性視神経症の直接のきっかけとなるものです。転倒と交通事故では、受傷時の衝撃の強さが大きく異なります。しかし、眉毛の外側部分に衝撃を受ければ、その強さに関わらず外傷性視神経症になる可能性があります。
そのため、眉毛の外側部分から衝撃を避けることは、外傷性視神経症の予防に役立ちます。転倒に関しては、自転車に乗る際はヘルメットをかぶり、飲酒後に転ばないように注意しましょう。また交通事故を防ぐために安全運転を心がけ、現場作業を行うときは安全管理に気を配ることが大切です。
関連する病気
- 視神経管骨折
- 頭部外傷
- 外傷性くも膜炎













