
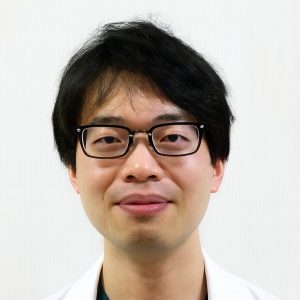
監修医師:
栗原 大智(医師)
虹彩離断の概要
「虹彩離断」という病気の説明に入る前に、まず「虹彩」についてご説明します。虹彩とは簡単に言うと、目において色の付いている部位のことです。日本人の多くは茶色の虹彩を持っています。中でも虹彩の中心の黒い部分を瞳孔と呼び、目の中に入る光の量を調節するため、虹彩が伸び縮みして瞳孔の大きさを変えています。明るいところでは瞳孔が縮み、反対に暗いところでは瞳孔を広げ、私たちの視界を保つ働きをしています。この虹彩の端の部分を虹彩根部と言い、いわゆる白目である強膜、および毛様体という組織とつながっています。ちなみに、虹彩の色やパターンは個人ごとに異なり、全く同じ虹彩のパターンを持つ人はいないとされています。このため、個人識別のための生体認証に用いられることもあります。
虹彩離断とは、この虹彩根部が強膜や毛様体から剥がれてしまう現象のことです。虹彩断裂と呼ばれることもあります。虹彩離断が起こると、程度にもよりますが視力の低下やまぶしさ、ものが二重に見える、眼内の出血、痛みを伴う、眼圧が上昇する、といった症状が見られます。虹彩離断の範囲が小さく、症状がない場合においては治療の必要がないこともありますが、上記の症状や虹彩離断の範囲に応じて、薬物による治療や外科的な治療など、適切な治療法が検討されます。虹彩離断を起こしている場合、眼内の出血や眼圧の上昇を伴うことも多く、治療やその後の経過観察にあたってはこれらの症状についても注意する必要があります。
虹彩離断の原因
虹彩離断は、眼球に対して外からの圧力がかかることで生じます。具体的には打撲、転倒、衝突などの衝撃をきっかけとして起こります。外部からの圧力によって虹彩が引き伸ばされ、裂けてしまった状態が虹彩離断です。虹彩離断の原因によく挙げられるのは、ボクシングなど目に衝撃が加わる可能性の高いコンタクトスポーツ、自動車のエアバッグの展開によるもの、また、ゴム製のひも、高圧の水、その他ボールなどが目に当たることによって起こる可能性があります。
虹彩離断の前兆や初期症状について
虹彩離断の程度が軽い場合は無症状のこともありますが、離断を起こしている範囲が大きい場合、目が充血する、ものが二重に見える、まぶしさが強くなり見づらくなる、目に痛みや不快感が生じる、といった症状が現れます。虹彩離断が起こっている時は、多くの場合で隅角(ぐうかく)が後退しています。目における隅角とは、角膜と虹彩が交わっている部分のことです。この隅角には、目に栄養を送る房水を目の外に出す排出口があります。隅角が後退し、排出口を塞いでしまうと房水の排出がうまくいかなくなり、結果として眼圧が高くなる恐れがあります。眼圧が上昇した状態が続くと、緑内障を発症するリスクが高まり、最悪の場合は失明の可能性もあります。
また、虹彩離断は前房出血を伴うことも多いです。前房とは、角膜と水晶体で囲まれた部分のうち、虹彩よりも前の部分を指します。外傷などをきっかけに、この前房部分に出血が生じると、目のかすみや痛みなどの症状が現れることがあります。出血が軽度の場合は、数日ほどで自然に血液が吸収されて治まっていくことも多いです。しかし、前房内に溜まった血液の量が多い場合や、再出血をした場合などでは角膜の色素沈着を招いたり、眼圧の上昇からくる緑内障、血液による角膜の汚れなどで視力低下が起こる可能性もあります。虹彩離断や前房出血が疑われるような症状が見られた場合は、速やかに眼科を受診してください。
虹彩離断の検査・診断
虹彩離断の診断にあたっては、視力検査、細隙灯(さいげきとう)顕微鏡検査、眼圧測定、隅角鏡(ぐうかくきょう)検査、眼底検査などが行われます。
視力検査
虹彩離断で前眼部の損傷、また炎症や出血などが生じると視力の低下を起こすため、視力に異常がないかを確認するために視力検査を行います。
細隙灯顕微鏡検査
細隙灯と呼ばれる拡大鏡を用い、縦に長く細いスリット状の光を目に当て、主に前眼部を検査します。この検査では角膜の状態、前房の濁り具合、前房の深さ、虹彩や瞳孔の状態、水晶体に偏位や脱臼が生じていないか、などを確認します。
眼圧測定
隅角後退が起こっていたり、前房出血が多かったりする場合は眼圧の上昇を伴うことがあります。眼圧の異常は視力低下を招く恐れがあり、定期的に経過を確認する必要があります。
隅角鏡検査
眼球の打撲では隅角の検査も重要です。角膜にレンズを当てて、虹彩根部周囲の隅角を観察します。点眼での麻酔や角膜保護剤を使用しますが、検査の際は圧迫感を伴います。
眼底検査
目の外傷による網膜振盪症、眼底出血、硝子体出血、網膜剥離などが起きていないかを確認するための検査です。目薬で瞳を大きく開いた状態にし(散瞳)、眼底と呼ばれる目の奥や水晶体の状態を詳しく調べます。散瞳により瞳を大きく開くと、そのぶん目の中に普段より多くの光が入るようになり、いつも以上に光がまぶしく感じたり、ピントを合わせづらくなったりします。そのため、眼底検査を受ける日は車やバイクの運転は避けてください。
虹彩離断の治療
虹彩離断の治療では、散瞳薬やステロイド薬の点眼で炎症を鎮めるアプローチが取られます。眼圧が高くなっている場合は、内服薬や点眼薬で眼圧を下げる治療が行われます。離断の範囲が大きく、瞳孔の位置が虹彩の中心からずれている瞳孔偏位を伴う場合や、眼球の変形、光を受けた際の強い眩しさや痛み、不快感といった羞明(しゅうめい)と呼ばれる現象、ものが二重に見える複視、瞳孔が複数になる多瞳孔症といった症状が出ている場合は外科手術での治療が行われます。また、前房出血に対しては、自然に吸収されるのを待ち、吸収が進まない場合は出血を洗浄する前房洗浄と呼ばれる手術が検討されます。
虹彩離断になりやすい人・予防の方法
虹彩離断の原因は外的な圧力が目にかかることです。そのため、虹彩離断になりやすい人はボクシングなどの格闘技や球技、その他、生活において目に衝撃が加わる可能性の高い行動を取ることが多い人と言えるでしょう。予防についてはやはり目への衝撃を避けることです。目を保護するゴーグルなどの装具を用いる、原因となる物や行動を避ける、といった対策が考えられます。また、目に衝撃が加わった場合、受傷してしばらく経った後、時間を置いて眼圧が上昇する場合があります。このため、過去に目を打撲した経験がある人は、特に自覚症状が無くても定期的に眼科を受診し、経過を観察することをおすすめします。













