
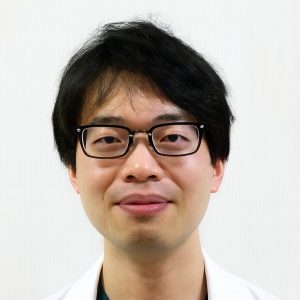
監修医師:
栗原 大智(医師)
目次 -INDEX-
仮性近視の概要
仮性近視は、目のピントを合わせるための筋肉、毛様体筋が緊張して、一時的に近視のような症状が起こる疾患です。「調節緊張症」「偽近視」と呼ぶこともあります。一次的な状態なので、早期に適切な処置を行えば正常な視力に戻すことができます。しかし放置していると真性近視になり、根治できなくなります。早期に適切な治療を行い、仮性近視を起こしにくい習慣を付けることが、視力を保つために何より必要です。特に、お子さんの弱視は見逃すことが多く、学校の集団健診で初めて指摘されることが珍しくありません。検診で「要精密検査」と指摘されたら、できるだけ早めに眼科を受診して下さい。
仮性近視の原因
仮性近視は、目のピントを調整する筋肉、毛様体筋が緊張し続けて、一時的に視力が低下する状態です。一時的な症状なので、筋肉の緊張がほぐれると改善します。しかし、症状は近視と同じです。外見からでは仮性近視か、本物の近視かを区別することはできません。仮性近視の原因は「近くばかりを見続けている」ことです。スマートフォンやタブレット、携帯ゲームなど、手元ばかりを見ていると毛様体筋が緊張したままになり、遠くを見ても緊張が解けなくなります。勉強やデスクワークが続いても同様の症状が起こります。
遠くのものを見るとき、近くのものを見るときには、目のピント調整を行います。レンズの役目をするのが水晶体ですが、人体は水晶体の厚みを変化させてピントを調整します。水晶体の厚さを変えるのは、眼球内部の「毛様体筋」という筋肉が担います。近くの物を見るときには毛様体筋が収縮して水晶体が厚くなり、光が網膜上に正確に集まるようにピントを合わせます。一方、遠くの物を見る際には毛様体筋が緩み、水晶体が薄くなって焦点が遠くに合うようになります。仮性近視は、この毛様体筋が緊張(収縮)したままの状態になることで発生します。
仮性近視の前兆や初期症状について
仮性近視の症状は、近視と全く同じです。遠くのものが見えにくくなり、教室の黒板が読みにくい、つまずき転倒を何度も繰り返す、スポーツなどでケガをしやすいなど、日常生活に大きな支障が現れます。遠くがぼやけて見える場合は、できるだけ眼科を受診して下さい。
気を付けたいのは、お子さんの発症です。お子さんは病状を説明することが難しく、仮性近視である、という自覚がないことがあります。小学校入学時の健康診断(就学時健診)で要検査の結果が出たら、できるだけ眼科で検査と治療することをおすすめします。仮性近視なら治す方法がありますが、放置すると近視が固定され、生涯治ることはありません。近視は緑内障などのリスクを上げるため、放置せずに眼科を受診しましょう。ほかの病気と同様に、仮性近視も早期発見、早期治療で予後が良くなります。ただし、真性近視は早期に発見できても、眼鏡やコンタクトレンズ着用以外の矯正法はありません。
仮性近視の検査・診断
仮性近視は毛様体筋の緊張が続くのが原因です。近視は眼球が奥に伸びて楕円形に変形し、網膜に焦点が合わなくなることで発症します。どちらも遠くのものがぼやけて見えるのは同じですが、仮性近視は毛様体筋がゆるむと正常な視力に戻ります。検査は「仮性近視と真性近視を区別する」ことが求められます。
サイプレジンテスト
毛様体筋を麻痺させる点眼薬(サイプレジン・ミドリンP点眼液)を点眼して、視力検査を行います。毛様体筋の緊張を緩めて視力が回復するなら、仮性近視と判断できます。真性近視は毛様体筋を緩めても視力は回復しません。通常の視力検査より正確な近視や遠視、乱視の度数が測れる検査です。サイプレジンは毛様体筋を麻痺させるので、副作用のまぶしさ、視力障害に注意する必要があります。12~48時間ほど以下の症状が続きます。
- 瞳孔が開いたままになり、まぶしく感じる
検査後に外に出ると、目が開けられないほどまぶしく感じます。サングラスをかけるとまぶしさが軽減するので、症状が心配であればサングラスを持参しましょう。サングラスをかけても検査した当日は車両の運転は厳禁です。車はもちろん、自転車など軽車両も乗ることはできません。必ず運転が出来る同行者の同伴か、公共交通機関をご利用下さい。 - 近くがぼやけて見える
近くにピントを合わせるためには、毛様体筋を緊張させて、水晶体を厚くする必要があります。毛様体筋が麻痺すると遠くにしかピントを合わせることができません。検査当日は勉強やゲームなどはお休みして、帰ってからは暗い部屋で安静にしましょう。
仮性近視の治療
仮性近視と診断されたら、治療で根治を目指します。治療は点眼薬を行いますが、治療薬だけでは効果が限定的です。「屋外で遊ぶ」など毛様体筋を鍛える生活習慣を身に付けましょう。仮性近視の治療はさまざまな方法が模索されていますが、中にはエビデンスレベルが低いものがあります。必ず眼科で治療を受け、エビデンスレベルが高い治療を受けて下さい。
アトロピン点眼薬
毛様体筋を緩めるはたらきがある点眼薬(アトロピン点眼薬)を定期的に点眼します。アトロピン点眼薬は瞳孔を広げるはたらきがあるので、就寝前に点眼する必要があります。アトロピン点眼薬の効果は6時間ほど。就寝中に毛様体筋が緩み、起床する頃には毛様体筋は動き始めます。「寝ている間だけ毛様体筋の動きをリセットする」ことで、過度な緊張をほぐします。しかし数ヶ月点眼しても改善しない場合は、真性近眼に移行したと考えられます。近視は眼球が楕円形に伸びることで発生しますが、いちど伸びた眼球を元に戻すことはできません。眼鏡などで視力矯正を行い、日常生活を快適に過ごしましょう。
生活習慣の改善
仮性近視は近いものを見続けることで発生します。そのため一定時間で遠くを見るなど、生活習慣の改善が必要です。近くを見続けることが疾患の原因なので、点眼薬だけでは効果は限定的です。(生活習慣の改善法は後述します)
仮性近視になりやすい人・予防の方法
仮性近視は近くばかりを見る習慣がある人がなりやすい疾患です。日本では小学校就学前~小学生のお子さんに起こりやすく、そのまま近視になるケースもあります。アジア人は遺伝的に近視になりやすいと考えられ、両親とも近視の場合はそうでない場合に比べて5倍の近眼リスクがあります。予防法はただ一つ、仮性近視になる前に「遠くを見る習慣」を付けることです。文部科学省では以下の習慣で近視リスクを下げることができると指導しています。
タブレットを使うときは部屋を明るく、30cm以上離す
タブレットやゲーム機、勉強など、近くを見る活動をするときは、以下の3つを守りましょう。小学生向けの指導ですが、大人も有効な方法です。
- 部屋を明るくする
- 目は画面から30cm以上離す
- 30分に1回は遠くを見て、毛様体筋を休ませる。20秒以上目を休ませる。
1日2時間は外で過ごす
日中に屋外で過ごすお子さんは、一日中家にいるお子さんよりも近視の進行が少ないことが分かっています。無理のない範囲で良いので、1日2時間は外で遊ばせるようにしましょう。建物の陰や木陰でも、視力低下を防ぐ十分な光(1,000ルーメン以上)が得られます。(1,000ルーメンは夕暮れ時に信号の光が目立つほどの明るさです)屋外遊びに夢中になると対象物に集中するため、近くや遠くを何度も見ることになります。この動作は毛様体筋の運動にもなるので、仮性近視の悪化や視力低下を防ぎます。屋外で昼食を摂るなど、運動以外の活動も良いでしょう。
しかし夏場の屋外は熱中症リスクがあるので、無理な外遊びは禁物です。十分な水分補給を促し、明るい室内で遊ぶなど、臨機応変に対処しましょう。屋内は感染症対策も必要です。屋内で遊ぶ際はお子さんにマスクを着用させる、換気を徹底する、体調が優れない場合は休むなど、感染リスクを抑えて遊べる環境を整えましょう。
関連する病気
- 屈折異常
- 眼精疲労













